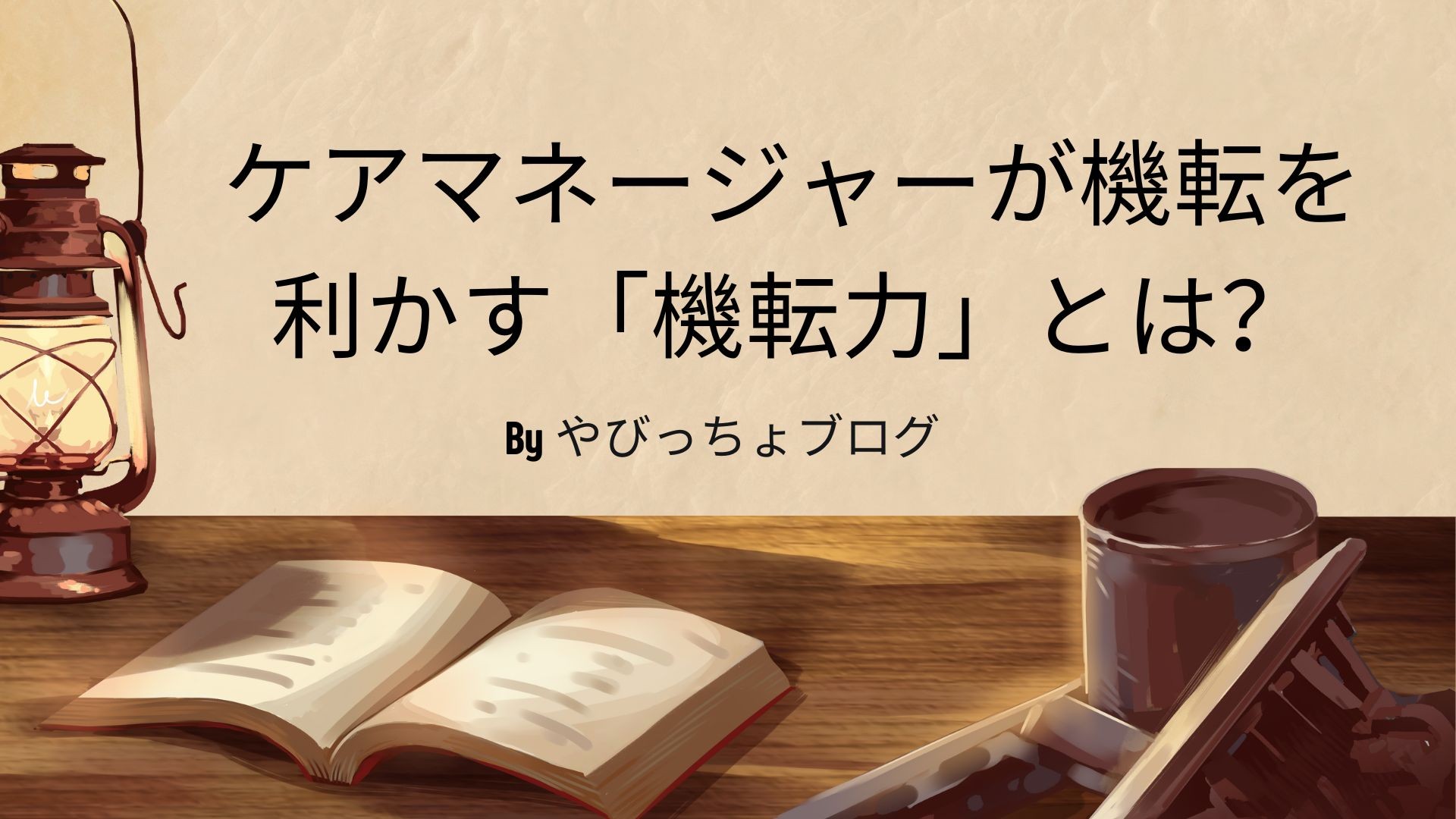月の初めになると、市役所などで新人のケアマネージャーさんが慣れない様子で先輩の後をついて教えを乞う風景を見かけます。どこの事業所でも新人のケアマネージャーを大事に育てたい!そんな思いもありながら、実際には忙しさから「走りながら覚えて!」と、ついつい放任してしまいそうで反省してしまいます。
その、忙しさの原因の中の一つとして、現場でケアマネジャーの仕事をしていると、介護保険の調整だけでなく様々な問題が起こってきます。中には無理難題な問題に対して「それ、ケアマネの仕事じゃ無いですよね?」と、開き直れるなら苦労はない私ですが…毎日のように起こる難題に対して必要な能力は「機転を利かす」ことだと思い知らされます。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

この記事はどのような人に読んで欲しいか
- ケアマネージャーと言う業務にとらわれず「機転が利く」人が気になる
- ケアマネージャーとして業務にあたっているが利用者対応で煮詰まっている
- ケアマネージャーってどんな仕事をしているの?って、興味がある
「ケアマネージャー」の業務すべての対応に対して、マニュアルがあるなら苦労はしないと思います。たとえ話を出して良いのか悩みますが、がんで苦しみながら死を迎える人になんて声をかけてい良いか解らず、涙をこらえて話を聞くだけだった…なんてこともあり反省しきりです。

必死になって現場で汗をかくケアマネージャーさんにリスペクトしながら記事を書いていきたいと思います。まずは、「機転を利かす」の定義から確認してきます。
機転が利く人ってどんな人?
機転が利くとは、「状況に応じて、臨機応変な行動をスピーディーに取れること」を意味します。
例えば、トラブルが起こった際にスムーズに解決まで導いてくれる人、その場の状況に合わせて柔軟に対応できる人などが挙げられるでしょう。
では、ケアマネージャーとしてどのような時に「機転を利かす」(状況に応じて、臨機応変な行動をスピーディーに取らなければならない)場面に遭遇するのか?いくつか挙げてみたいと思います。

あくまで私個人の見解と経験談ですので、他のケアマネさんすべてに当てはまるわけではないこともご了承ください(汗)。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
「機転を利かす場面とは」

- 介護保険サービス(マニュアル)では解決しない状況に陥ったとき
- 利用者を含め、関係者の利害が衝突するとき
- どう対応しても変えられない状況に遭遇したとき
今までの現場経験の中で思いつく、三点を挙げてみました。恐らくは「機転を利かす」場面に遭遇する環境として、「困難事例」の利用者への対応が挙げられると思います。そのことも踏まえて、詳しく見ていきたいと思います。
介護保険サービス(マニュアル)では解決しない状況に陥ったとき
ケアマネジャーのお仕事として、利用者のニーズに合った介護保険サービスを提案し調整することが基本的な業務になります。
一方で、介護保険サービスでは解決しないニーズが出現する場面に遭遇します。基本的には「介護保険」以外の社会資源のコーディネートは、他法(障がい福祉サービス・生活保護法)の制度の活用、家族や地域等のボランティア、民間サービスを活用する「インフォーマルサービス」の活用がセオリーです。
ですが、利用者を取り巻く状況の中で制度に当てはまらない(制度から零れ落ちてしまうとも表現されます)ことも多々あります。又、地域にインフォーマルサポートが不足しているなど、ケアマネ個人ではどうにもならない状況に遭遇してしまうこともあります。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
利用者を含め、関係者の利害が衝突するとき
利用者を中心とした人間関係に課題がある場合に遭遇しやすいと思います。サービスの方向性でもめる分には理解も出来ますが、夫婦関係や親子関係が疎遠だった。財産などお金が絡んで親子、親族で争っている等、家族関係の仲が悪いと関係の修復や調整に入らざるを得ない場面も遭遇します(もちろんケアマネージャーの業務の範囲外です)。
最近多い事例として、結婚歴も無く生涯孤独で生きてきたなど、身寄りが居ない独居高齢者ですと、支援者全体に課題が広がります。その矢面に立たされることが多いのがケアマネージャーだったりします。
どう対応しても変えられない状況に遭遇したとき
例えが非常に難しいのですが、過去にあった事例から振り返ると「歳をとって孤独を感じる。独りで寂しい」「県外に住む親族の元に移住したい(何年も疎遠で連絡先も知らない)」「若い頃に騙されたお金を取り戻したい」でしょうか。
他にも、女性の方では「好きな人と別れたくなかった」男性の方なら「女を紹介しろ」なんで相談をお受けいたします。
時間(過去)や距離、お金、人間関係など、すでに失ってしまった物事に対して執着が強いと、利用者の生活の質を大きく下げてしまうことになりかねません。神でも仏でもない私には解決は不可能だと言えます・・・。

ちなみに「女とお金の相談には乗れないよ」が私の口癖です。異性との関係や金銭面のトラブルは信頼関係を損ねるので注意しています。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
追記:もちろん、生活費に困るほどお金に苦労されている事例の場合には生活保護を申請してセーフティーネット繋げることなども対応しています。
【関連記事:ケアマネージャーが業務を効率化するための5つの戦略】
それでも生活は前に進む訳で
それでも、利用者の生活は続きます。幸福の実現と言う目標の達成のために、今日も利用者の相談業務に応じます。さまざまな無理難題から業務範囲外の相談まであの手この手を使って問題解決していきます。その時に必要となるスキルが「機転を利かす」ことだと思います。
状況は利用者それぞれで個別(パターン)化できないので、具体的な事例は避けますが、口先だけの対応にならぬように、利用者本人のおかれている状況や環境をアセスメントしつつ、より良い提案が出来ないものかと思案に暮れる日々です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》


ちなみに機転が利く人の特徴として…
機転が利く人の特徴
機転が利く人の特徴を、3つほどご紹介します。
状況判断が上手い
機転が利く人は視野が広く、状況判断力に優れているタイプが多いです。
目の前のみならず、常に全体の流れや周囲の動きまで幅広く捉えています。
さらに、現状だけで物事を判断するのではなく、その先まで見据えた上で最適な選択肢を選んでいるのです。
また、自分なりの判断軸があるため、「どれを選ぶべきか」「どれを選ばないべきか」という基準が明確であることも特徴のひとつ。
立ち返る原点があるからこそ、いざというときに筋の通った意志決定を行えます。洞察力がある
洞察力とは、「物事の本質を見抜く力」のことです。
機転が利く人は、人間や物事を深く観察する能力が高い傾向にあります。
普段からいろいろなことを観察し、「人はどんなときにどのような行動を取るのか」といった行動パターンを抽出しているためです。
例えば、上司に意見を提案するというシーンでは、「提案後に上司からどんなフィードバックが返ってくるか」「その場合、自分はどのように対応するべきか」など、多様な切り口でシミュレーションを行います。
洞察力を養うことで、先を見据えた行動を取れるようになるでしょう。考え方が柔軟
機転が利く人の共通点として挙げられるのは、「柔軟に物事を考えられる」「思考の幅が広い」ということです。
例えば、アイデアがパッと思い浮かんだとしても、すぐに飛びつくことはありません。
ひとつの視点や自分の意見だけにこだわるのではなく、「もっと別の方向から見てみよう」「逆にこんなことも言えるのではないか」「ほかの人の意見も参考にしてみよう」と多面的に考えた上で結論を出します。
このように、さまざまな視点や意見を取り入れられるからこそ、どんな場面でも最適解を導きだすことができるのです。
上記の点を踏まえて機転が利くようになるためには
その①:ある程度、業務としての経験値があること
その②:好奇心があること(洞察力に繋がる)
その③:その分野(この場合はケアマネ業務)に対して知識がある…からこそ、多視点で物事をとらえられる
その特徴を活かして問題解決を図る、目的を達成しやすくなると説明します。そう、ケアマネに求められる能力の一つに「問題解決能力」が挙げられるように、問題解決能力とは必然的に「機転が利く」という「機転力」が必要になるのです。
【関連記事:理想のケアマネージャーの探し方について】
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
結論:知識の研鑽を積みながら現場で経験を重ねる
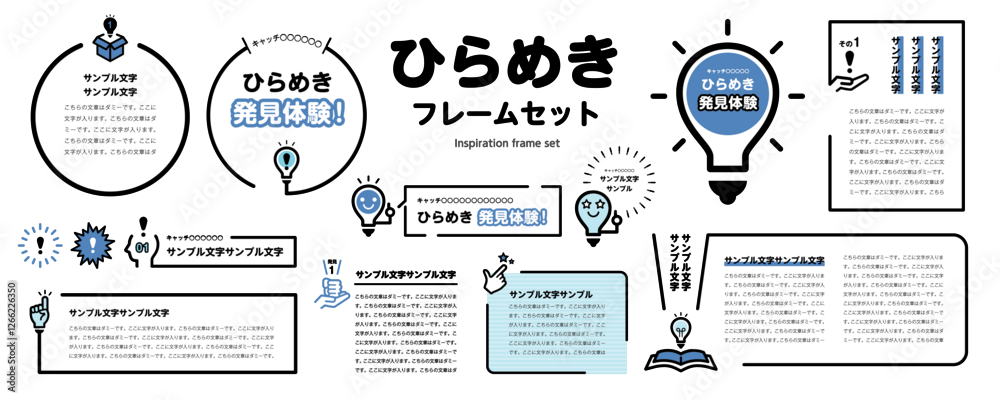
ありきたりな結論ですが、知識の研鑽を積みながら現場で経験を重ねる。学びと経験を両輪でフル回転・・・。これに勝る対応は無いと思います。マニュアル通りでは問題は進展しません(これは真理)。

今日も無理難題がやってきます。マニュアルに載っていません。機転を利かすべく己の頭で物事を考える毎日です。この記事は「困難事例」とは何か?への導入部分となります。やびっちょでした。記事を読んでくださりありがとうございます。
【関連記事:ケアマネとして独立したいと考えるあなたへ3つのアドバイス】
【関連記事:坂口恭平著、道草晴子漫画/生きのびるための事務を読んで実践してみた】
【関連記事:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』を読んで考える~一生モノのキャリアを構成する3つのポイント~】
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》