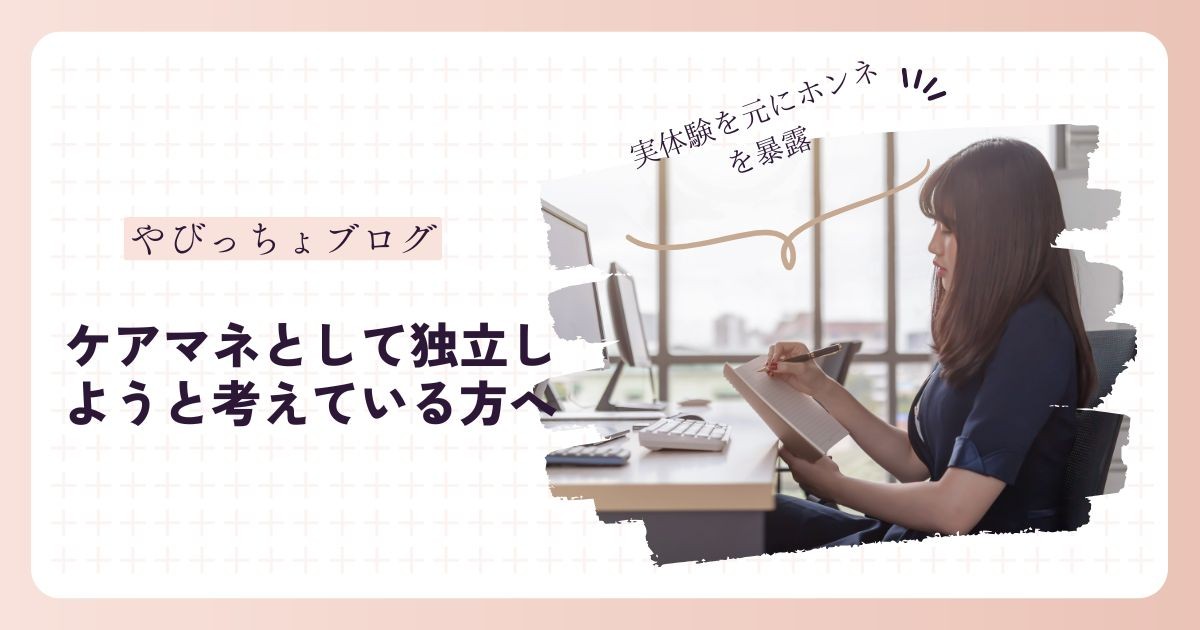ケアマネージャーとして、資格を取得したら一度は考えるかたもいると思います「自分で法人を立ち上げてケアマネージャーとして独立したい」と。
一方で、「失敗したら怖いし、借金もしたくない。そもそも、何から手を付けたら良いのか解らないことだらけ」と、不安に思うかたもいらっしゃると思います。
高齢化が加速する現代社会において、ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割はますます重要になっています。その中で「いつかは自分で事業を立ち上げたい」「より自由な働き方を実現したい」と、高い理想を掲げ独立を考える方も少なくありません。
実際に、居宅介護支援事業所を立ち上げて自らの理想とするケアを提供したいと考えるケアマネも増加傾向にあります。
理想だけでは乗り越えられないのが独立の世界。資金計画、営業活動、法的手続き、そして人材確保や地域との連携といった、現場経験だけではカバーしきれない多くの壁が待ち受けています。とはいえ、正しい準備と視点を持てば、ケアマネとして独立し、地域に根ざした信頼あるサービスを提供することは十分に可能です。

こんにちは、やびっちょです。沖縄県で独立型の居宅介護支援事業所を運営して5年になります。この記事は「ケアマネジャーとして独立したいと考える」あなたへ「最低限押さえておきたい3つのアドバイス」をお届けします。夢を現実にするために、まずは何から始めればよいのか――そんな疑問に答える、実践的なヒントをお伝えします。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
ケアマネジャーとして独立を考える背景や動機

ケアマネジャーとして働いていると、「もっと自分らしいケアを実現したい」「現場の理不尽な制約から解放されたい」といった想いを抱く場面は少なくありません。
実際、ケアマネジャーが独立を考える背景には、現場での理想と現実のギャップ、職場環境への不満、そしてキャリアアップへの意欲など、さまざまな要因が存在します。
次に「ケアマネジャーが独立を考える背景や動機」について考察していきたいと思います。
組織のしがらみから解放されたいという願い
まず一つ目の背景として挙げられるのが、「制度や組織に縛られた支援」に対する違和感です。言い換えるなら「組織のしがらみから解放されたい」と言う願いです。多くのケアマネジャーは、利用者一人ひとりの生活背景や希望を丁寧にくみ取り、その人に最適なケアプランを提供したいと考えています。
しかし、実際の現場では、会社のマニュアルや業務効率、収益性といった“組織の都合”が優先され、十分に利用者の要望に応えられないケースが少なくありません。
たとえば、時間的な制約から訪問回数が制限されたり、予算の都合で必要なサービスが削られたりすることもあります。こうした状況に、現場のケアマネはもどかしさを感じ、「本当にこれで良いのか?」と自問自答を繰り返すようになります。
また、上司と意見が合わない。同僚の人間関係が悪いなど「人間関係のしがらみ」も課題になりえます。
その中で芽生えてくるのが、「自分の理想とする支援を、誰にも縛られずに実践したい」という強い想いです。利用者本位の支援を追求するには、自らがルールを決められる立場になるしかない――そう考えたとき、「独立して自分の事業所を持ちたい」という決断に至るのは、ある意味ごく自然な流れです。
制度の枠内であっても、その運用の仕方やサービスの工夫次第で、より利用者に寄り添った支援を実現することは可能です。独立とは、その自由度を最大限に活かす手段のひとつでもあるのです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
労働環境や収入面での課題について
次に挙げられる動機が、「労働環境や収入面での課題」です。ケアマネジャーの業務は、単なる事務処理にとどまらず、高齢者やその家族の人生に深く関わる重大な役割を担っています。
利用者ごとの状況に合わせたケアプランの作成、各関係機関との調整、さらには精神的なケアまで、多岐にわたる責任を日々背負っているのが現実です。
しかし、その重責に見合った報酬が得られていないと感じている人は少なくありません。また、職場によっては人手不足により過重労働が常態化していたり、有給が取りづらい、残業が多いなど、働き方に対する不満を抱えているケースも多く見受けられます。
そうした背景から、「もっと自由に働きたい」「自分の頑張りが正当に収入に反映される環境をつくりたい」と考え、独立を目指すケアマネジャーが増えてきています。独立すれば、自らの裁量で働く時間やスタイルを決めることができ、効率的な業務運営によってワークライフバランスの向上も見込めます。さらに、経営努力や工夫によっては、収入アップも十分可能です。もちろん、経営リスクや責任は伴いますが、それ以上に「自分で自分の価値を決められる」という魅力が、独立という選択を後押ししているのです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
自分の理想とする支援を、誰にも縛られずに実践したい
そのような現場での葛藤を繰り返す中で、次第に芽生えてくるのが、「自分の理想とする支援を、誰にも縛られずに実践したい」という強い想いです。
マニュアル通りの対応や組織の利益を優先した支援ではなく、本当に必要とされているサービスを、必要なタイミングで提供できる体制を自分自身の手でつくりたいと考えるようになるのは、ケアマネとしての責任感や誠実さの現れとも言えるでしょう。
多くのケアマネジャーは「利用者本位」という言葉を胸に日々業務にあたっていますが、その理想を実現するには、組織の方針に従う立場では限界があると痛感する瞬間があります。
そうしたとき、「独立して自分の事業所を立ち上げる」という選択肢が現実味を帯びてくるのです。自分が代表となることで、支援の方針やサービスの在り方を一から考え、地域の実情や利用者のニーズに即した柔軟な運営が可能になります。
たとえ制度の枠内での支援であっても、その運用次第で提供できるケアの質には大きな違いが生まれます。独立とは、そうした自由度と創意工夫の余地を最大限に活かせる手段であり、自分の信じるケアを貫くための新たなステージなのです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
独立するメリットやデメリットについて
自身で事務所を立ち上げ独立する上で、夢や希望と同じくらい不安を誰もが考えると思います。いわゆる独立をするうえで「メリットやデメリット」はどのようなものがあるのだろうか。
私が、実際に運営してみて良かったこと、「もっとこうすればよかった」など反省したことを挙げていきます。たくさん思いつく中で上位3点をピックアップしてみました。

ちなみに私に限っては、独立をしてからというモノ反省な毎日ですが、後悔したことは今のところ一度もありません。

独立してよかったメリット3点について
- 理想の支援を実現できた
- 収入の上限がなくなった
- 自分の時間を自由に使える(在宅ワークが出来る様になった)
独立してよかったメリットについては、上記の三点を実感として感じました。自由になったことに関しては、人間関係やお金なども挙げられますが、特に「時間」から自由になれたことは人生の質を大きく上げる要素になったと思います。

趣味が読書な私としては本の購入代を経費で落とせることはありがたいです。自分の自宅を事務所にできるなら、状況によっては家賃や光熱費も経費で落とせます(条件はありますが)。ガソリン代を含めた車両代も経費にすることで税金対策にもなります。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

理想の支援を実現できる
独立する最大のメリットのひとつは、「理想の支援を実現できる」ことです。組織に属している場合、どうしても会社の方針や上司の判断、収益目標などに沿った業務が求められ、利用者一人ひとりのニーズに寄り添いたくても、現実には制限が多いものです。
例えば、「もっと時間をかけて話を聞きたい」「本当に必要なサービスを導入したい」と思っても、業務量や採算性といった組織の事情で断念せざるを得ないことも少なくありません。
その点、独立して自分の事業所を立ち上げれば、サービスの方針や運営体制をすべて自分で決定できます。自分が大切にしたい支援の価値観や信念を事業に直接反映させることができるのです。
訪問頻度や相談対応の柔軟性、地域資源との連携の方法など、細かな部分に至るまで「自分ならではのケア」を形にできます。これは、利用者本位の支援を実現したいと願うケアマネジャーにとって、大きな魅力と言えるでしょう。
もちろん、自由な運営には責任も伴いますが、その分、利用者やご家族との信頼関係も深まり、やりがいや満足感も一層大きなものとなります。独立は、自分の理想を現実に変えるための力強い一歩です。
収入の上限がなくなる
ケアマネジャーとして独立することで得られる大きな利点のひとつが、「収入の上限がなくなる」という点です。企業や法人に勤めている場合、どれだけ成果を出しても給与は基本的に固定されており、昇給にも限界があります。
評価制度による差はあるものの、年功序列や会社の方針に左右されることも多く、「これ以上は望めない」と感じている方も少なくないでしょう。
一方、独立して自ら事業所を運営する立場になれば、自分の努力や工夫、経営手腕次第で収益を伸ばすことが可能です。利用者数の増加や地域との連携による紹介、サービスの質向上による信頼獲得など、自分が働きかけた結果がダイレクトに収入として反映されます。ま
事業所を拡大したり、他のサービス(訪問介護や福祉用具など)と連携・展開することで、さらなる収益の柱を築くこともできます。
もちろん、安定した収入を得るまでには時間と戦略が必要ですが、「自分の力で稼ぐ」ことができるというのは、大きなやりがいとモチベーションになります。努力が正当に報われる環境を自らつくり出せる点で、独立は非常に魅力的な選択肢となり得るのです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
働き方の自由度が高い
ケアマネジャーとして独立するもう一つの大きなメリットは、「働き方の自由度が高い」ことです。企業や法人に所属している場合、勤務時間や休日、働き方に関する裁量は限られており、決められたシフトや業務量に従うのが一般的です。子育てや介護、プライベートな事情と仕事の両立が難しく、心身に負担を感じている方も少なくありません。
独立すれば、自分が経営者となるため、勤務時間の設定や休暇の取得、訪問スケジュールの調整、業務の優先順位などを自分のライフスタイルに合わせて柔軟に決めることができます。たとえば、子どもが学校に行っている時間帯だけ働く、週に一度は必ず休みを取るといった働き方も可能です。また、スタッフを雇用する際も、フルタイムだけでなくパート勤務といった多様な雇用形態を選ぶことで、組織全体の働き方も柔軟にデザインできます。
このように、時間や働き方の自由度が高まることで、ストレスや疲労を軽減しながら、より長く、健康的に働き続けることが可能になります。自分の人生や家庭と仕事をバランス良く両立させたい方にとって、独立は理想的な働き方を実現する大きなチャンスと言えるでしょう。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
デメリットについて
次に、デメリットについても考察していきます。一番に考えそうなデメリットとして「不安」や「心配」なことが頭を過ぎると思います。「失敗したくない」など、リスクを取りたくない、またはリスク回避の方法を知りたいと思うかたも多いと思います。私が実際に、起業してみて感じたデメリットは下記の3つになりました。
- 経営上の責任が重たい
- 安定収入が保証されない
- 法制度や行政対応に精通する必要がある
デメリットに関しては「独立しても稼げるのか?」という不安が一番ですよね(汗)。立ち上げて事業の運営を始めてみたは良いものの実績が上がらず、場合によっては家族にも苦しい思いをさせるのはないか等、不安は大きいと思います。

実際に、私も立ち上げ初年度は赤字でした。二年目から人員を増やし特定事業所加算を算定したことで黒字にのせることができました。
【関連記事】ケアマネージャーって独立しても儲かるの?
また、1人で立ち上げて運営を始める際に解らないことを相談できないと言う不安もありました。人見知りで友人がいない私は、相談相手がいない事にとても困りました(今も困っています)。
事前に相談に乗ってもらえる仲間を作っていれば、無駄な失敗をせずに済んだものだと反省しています。日頃からお付き合いの大切さを身に染みて感じました。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
デメリットその①:経営の責任が重い
独立してケアマネジャーとして事業所を運営する際に直面する大きなデメリットのひとつが、「経営の責任が重い」という点です。企業や法人に勤務している場合、経営や事務作業に関する責任は経営陣や上司が担うことが一般的であり、ケアマネジャーは現場での業務に集中できます。
しかし、独立後は収益の確保や人材管理、契約業務など、事業運営に関わるすべての判断を自身で行わなければなりません。
まず、収益の確保が最大の課題となります。利用者数を増やすための営業活動や、事業所運営に必要な経費の管理など、利益を確保するための努力は一切手を抜けません。
さらに、ケアマネジャーとしての本業に加えて、経営者としての業務が増えるため、精神的・時間的な負担が大きくなります。経営に失敗すると事業の存続が危うくなり、従業員の雇用や利用者のサービス提供にも影響が出るため、その責任は非常に重く感じることが多いでしょう。
また、人材管理や労務管理の部分でも責任があります。スタッフの採用、教育、シフト管理、給与計算など、経営者としての仕事が多岐にわたります。これらの業務をうまくこなさなければ、業務が円滑に進まないだけでなく、スタッフのモチベーションにも影響を及ぼし、ひいてはサービスの質にも関わります。
このように、独立には自由度の高い働き方や収入の向上といった魅力がありますが、その分、経営者としての責任や負担が大きくなることを理解しておく必要があります。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
デメリットその②:安定収入が保証されない
独立してケアマネジャーとして事業を立ち上げる際に直面するリスクのひとつは、「安定収入が保証されない」ことです。特に開業初期は、事業が軌道に乗るまでに時間がかかるため、収入が不安定になることが避けられません。
独立して事業を開始すると、最初は利用者数が少なく、収益が安定しないため、収入が大幅に減少する可能性があります。ケアマネジャーとしての業務に加え、営業活動や新規顧客の獲得が必要となり、それらがうまくいかない場合には、生活費を含めた十分な資金が確保できないリスクが高いのです。
また、事業の安定化には一定の期間が必要です。新規事業を立ち上げる際は、一定のマーケティング費用や運営資金がかかりますが、初期投資を回収できるまでに数ヶ月から数年を要することもあります。その間、収入が限られている状況では、生活資金を確保するために自己資金や借入れを活用する必要が出てきます。これにより、資金繰りに追われることとなり、精神的な負担も大きくなります。
さらに、安定した収入を得るには、地域での評判を築き、信頼を得る必要があります。これには時間がかかるため、事業初期においては十分な収益を上げることが難しく、生活面での不安定さが続くことを理解しておくべきです。そのため、独立する前に十分な運転資金や生活資金を確保することが重要となります。
このように、独立後の収入が安定するまでには多くの努力と時間が必要であり、短期的な収入の不安定さを乗り越えるための準備が求められます。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
デメリットその③:法制度や行政対応に精通する必要がある
ケアマネジャーとして独立する際には、「法制度や行政対応に精通する必要がある」という点も重要なデメリットです。独立後、事業を適法に運営するためには、介護保険制度や福祉関連法規の知識だけでなく、指定申請、報酬請求、各種届出など、事務的・法的な手続きに対して細かく対応しなければなりません。
介護保険制度については、定期的に変更や改定が行われるため、最新の法令や制度に常に精通している必要があります。これに加えて、事業所として介護保険サービスを提供するためには、適切な指定申請を行う必要があり、その申請内容は非常に多岐にわたります。
例えば、事業所の立ち上げに際して、運営規定の作成やスタッフの配置基準を満たすための準備が求められますが、それらすべての手続きを自分で行う必要があります。
報酬請求についても注意が必要です。介護報酬は、サービス提供に基づいて定期的に請求することが求められますが、請求内容やフォーマット、期日を守ることが非常に重要です。請求の不備があると、報酬の支払いが遅延したり、最悪の場合は支払いが取り消されるリスクもあります。そのため、事務作業や法的な対応を円滑に進めるためには、専門的な知識と手続きの正確さが求められます。
法令遵守については、介護事業の運営において最も重要なポイントとなります。例えば、個人情報保護法や労働基準法をはじめ、数多くの法令に従いながら事業を運営しなければなりません。これらの法的対応が不十分だと、法的トラブルや行政の指導を受けるリスクが高まります。
独立して事業を行うためには、法制度や行政対応に精通し、適切な事務手続きを行うことが求められます。これらをこなすためには、日々の勉強や外部の専門家への相談を通じて、しっかりとした準備が必要です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

その他にも・・・
独立開業にあたっては、法人の設立が前提になります。法人登記に対する手続きから始まり、設立後も社会保険の手続き、事務所を構えるなら不動産で物件探しや契約。必要備品の購入や事業所としての指定を取る為の手続き…。考えるだけで尻込みする気持ちになりますよね(もちろん、私もそうでした)。
何よりも、居宅介護支援事業所を立ち上げるにあたってスケジュール管理が必要になります。ここでも繰り返しになりますが、ネットからの情報や書籍から情報収集をしていた私ですが、実際に独立しているケアマネさんから、直にお話を聴ければよかったと反省しています。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
ケアマネとして独立したいと考えるあなたへ3つのアドバイス

と言う訳で、独立開業をする上でのメリット、デメリットを挙げてみました。最後に「ケアマネとして独立したいと考えるあなたへ3つのアドバイス」を伝えたいと思います。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
その①:ICT機器を使って業務の効率化をはかる
アドバイス1つ目は「ICT機器を使って業務の効率化」を図ることです。

介護ソフト(カイポケ)と「e-FAX」との相性が良く,ICT化も進めたことで業務の効率化と同時に在宅ワークができる環境も整えることができました。
前の職場では、パソコンは原則、事務所での使用のみ。ガラケーでの連絡調整、lineはおろか管理者しかサーバーに接続できない為、メール送信も出来ない。基本的にガラケーのショートメールしか使えない状況でした。
紙ベースで書類を管理している為、FAXを確認するだけの為に休日に出社・・・。そんな(無駄)ことも無くなりました。在宅ワークへの環境が創れたことで出勤へのストレスはかなり軽減されました。
【関連記事:ケアマネージャーが業務を効率化するための5つの戦略】
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
その②:「時間という有限な資源を自由に使える」という魅力はお金に勝る
在宅ワークができる環境を作れたことによって、家族との時間が取れたことが一番大きいと感じます。当時は、娘もまだ幼く雇われたままの環境では保育園の送り迎え等で業務の調整が困難な状況でした。
妻に送り迎えをお願いすれば、その分だけ負担が妻へ重くなってしまいます。ですが、実際に独立を経た後では、在宅ワークをする環境が作れました。保育園(こども園)への送り迎えや、急の発熱や学校の行事なども対応できることが多くなりました。
現在は、小学校に上がったおかげで、子どもに対する手が少し離れたこともあり時間的にも負担も軽くなりました。

ウチの事務所で働く職員の中には「子育て世代」や「親の介護世代」も働いています。在宅ワークができる環境で働きやすい環境つくりができました。
その③:「借金」としてお金を借りるという考え方から「時間を買う」という考え方にシフト」
独りケアマネを運営されている方の中には、自己資金(親族からの協力も含め)で経営されているかたも何人かいらっしゃいました。リスクを取りたくない、リスク回避という考えから自己資金で運営したいと考えるかたも有ると思いますが、私はあえてリスクを取る選択をしたことになります。
その中で「借金は悪い事ではない。返済する事で信頼を作る事ができる」と言う考え方で、金融公庫や地元の金融機関からの借り入れで、設備資金や運転資金の調達ができました。
ご縁にも恵まれて、事務所物件や必要な物品に関しても創業資金を使ってスムーズに導入が可能でした。そのことが事業を開始した後に業務の効率化へ繋がり、実績に結び付いたと思います。もちろん、利益が出るまでは安い報酬で踏ん張ったことも良い思い出です。

資金面に関しては貯蓄もない私。前職の退職金と併せて金融公庫からの借り入れで、申し込みに関しては早い段階で動いていました。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
専門の職種に任せるということ

独立開業にあたっては様々な手続きが必要になります。そのような時に、専門職(ケアマネジャー)として働いているうえで学んだことが大いに役に立ちました。「他職種連携」の大事さです。
法人の登記や社会保険に税金等、専門外の手続きに関しては士業と言われる先生方(行政書士、司法書士、税理士)にお任せして、事業の運営に関わる大事な業務(事業所指定の手続きや営業等)に集中した事でスムーズに独立開業に向けて準備できたと思います。
ネット等で検索すると「介護事業立ち上げ専門」の行政書士や司法書士事務所もありました。税理士に関しては介護ソフト業者と連携している税理士さんに依頼しています。
運営に関する書類等の準備も大変な作業です。運営規定のひな形や各種マニュアル等の作成も一から作るとなると膨大な作業になります。
ネットからのテンプレートを引用をすることで、各様式やマニュアルを無料で作ることも可能ですが、長い目でみると「デジタルコンテンツ」として販売している商品を購入した方がクオリティも高く時間もかからない為、業務の効率化につながると感じました(ここも反省点)。
デジタルコンテンツとして、おすすめは「ヒトケア」さんのテンプレートは、どのコンテンツもクオリティーが高くお勧めです。
【関連記事:テンプレート | ヒトケア(一人ケアマネ)の仕事術】
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

さいごに

以上、「ケアマネジャーとして働いてはいるけれど、このまま雇われた方が良いのか?それとも独立して自分で運営した方が良いか」と悩むあなたに読んで欲しい記事構成で書いてきました。
あくまで一個人の意見ではありますが紹介しました。もちろん、メリットデメリットに関して、ここでは書ききれないこともたくさんあります。

大切なのは「お金」と「時間」を自分の裁量で使うことが出来ます。令和7年3月現在ですが、この春から独立して居宅介護支援事業所を立ち上げようと、頑っているケアマネさんが私の働く地域でもいます。
このことが一番大きいと感じました。正直な話、居宅介護支援事業所の経営は小規模で展開していくには難しい事業だと思います。様々な意見を聞いたうえで決断をしてみても良いと思います。以上、やびちょでした。
【関連記事:ケアマネージャーが業務を効率化するための5つの戦略|ICT機器活用術】
【関連記事:『ゆるストイック』な生活で見つける「運をコントロール」できる生き方について】
《プロモーション:本ページはアフィリエイト広告を利用しています》