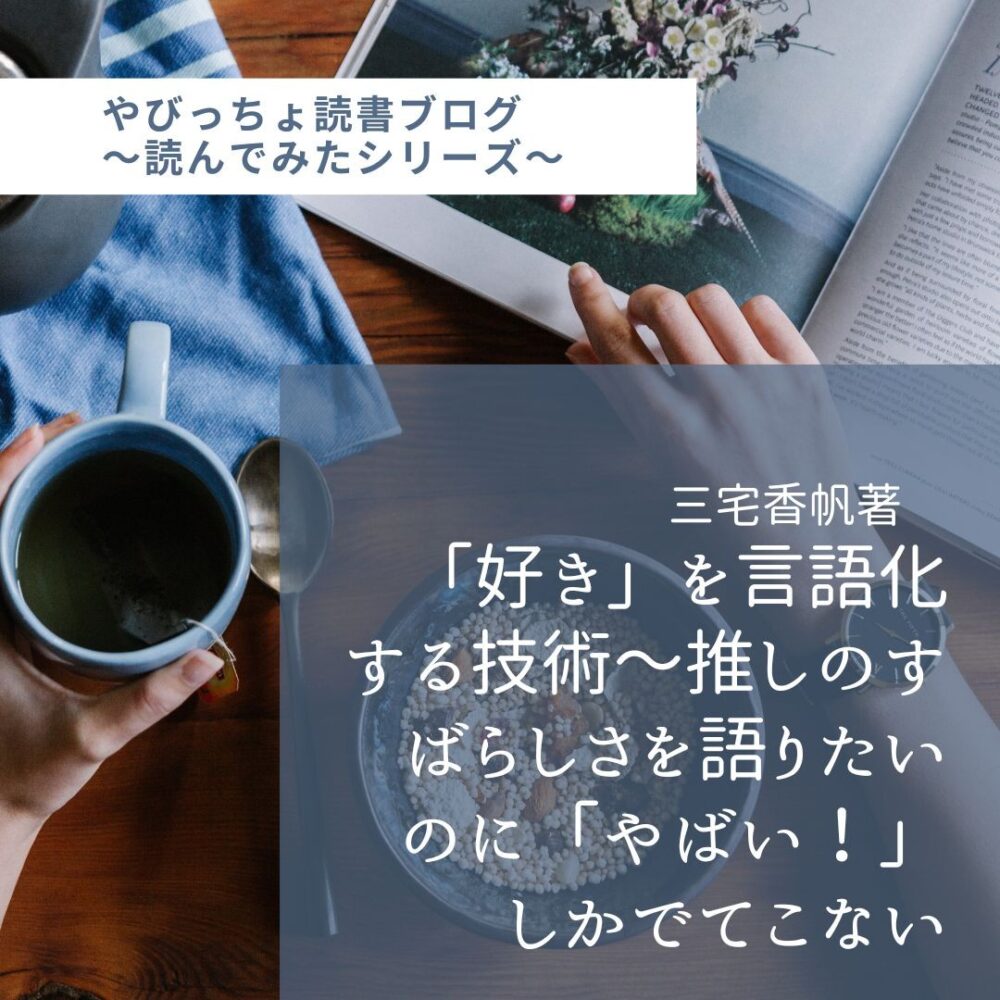SNSや会話で「やばい!」「尊い!」といった短い言葉を使って気持ちを表現しても、「本当はもっと伝えたいのに…」と感じることはありませんか?
読書感想文で「面白かった」としか書けなかったり、推し活で自分の熱量を語りきれなかったり──そんな言葉にできないもどかしさを解消してくれるのが、三宅香帆さんの著書『「好き」を言語化する技術』です。
自分の言葉で、自分の想いを言語化して相手に伝えることは、簡単そうに見えて以外に難しいと著者の香帆さんも語ります。
本書は、感情をただの一言で済ませずに「どこが」「なぜ」「どのように」好きなのかを表現するための具体的なテクニックを解説した一冊です。
言葉にする力は特別な才能ではなく、視点や思考の習慣を変えることで誰でも鍛えられる「技術」であることを著者は繰り返し強調しています。

さらに、ビジネスやマネジメントの現場で「伝える力」を客観的に高めたい人には、『コミュニケーション検定(初級/上級)』 が相性抜群。
本書の“言語化力”と資格の“対人理解力”を掛け合わせることで、
あなたの発信・リーダーシップ・仕事の成果は劇的に変わります。

パパ!「言葉にする力」と「人への理解力」、二つの力をあわせるって面白い考え方だね♬
この記事では、本書のエッセンスと検定の概要をまとめ、
今日から言葉がスラスラ出てくる自分に変わるための実践法 を紹介します。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
『「好き」を言語化する技術』の概要と特徴について
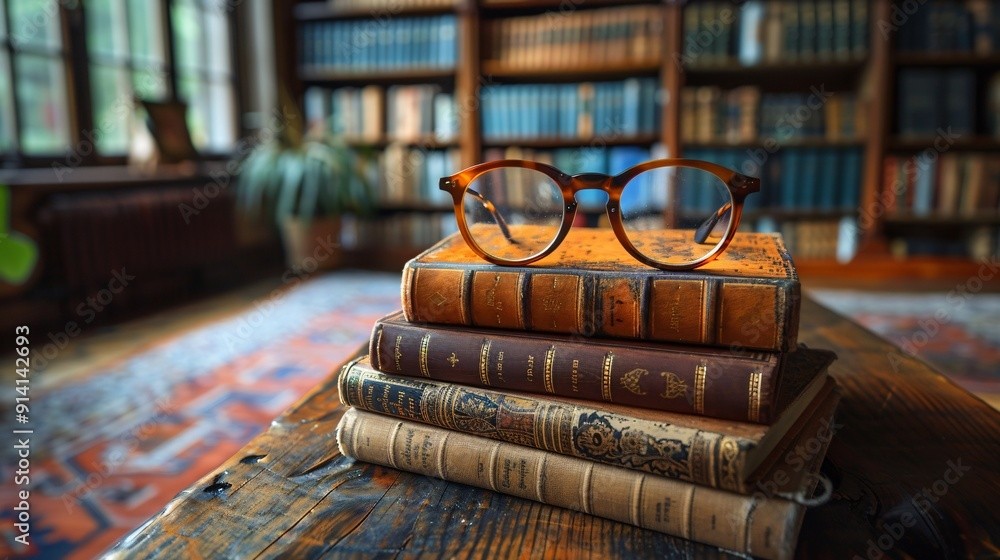
三宅香帆著『「好き」を言語化する技術』は、「好き」という気持ちを、うまく言葉に(言語化)できない人のための実用書です。
読書感想や推し活、日常のコミュニケーションまで幅広く応用できる内容で、「どこが」「なぜ」「どのように」好きなのかを具体的に言語化する方法を丁寧に解説しています。
本書、『「好き」を言語化する技術』は、実例も豊富で、自分の感情を他者に伝わる形で表現するための視点や、トレーニング法が詰まった一冊です。
📖 忙しいあなたも、移動中に“聴く読書”を。
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
こんな人にこそ読んでほしい
・著者(三宅香帆氏)は「はじめに」で言います。
その推しに感動したとき、
「推しについて誰かに語りたい!」
「推しの魅力をみんなに知ってほしい!」
「推しの素晴らしさについて、発信したい!」
と思う。
けれども、いざ語ろうと思うと
「やばい!」という言葉しかでてこない。
「好き」を言語化する技術~推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しか出てこない(三宅香帆著/4ページ)より引用
現代は、YouTubeチャンネルやサブスクリプションなどのコンテンツを通して、エンターテインメントが充実していて、しかもそのコンテンツに気軽にアクセスできる時代です。
だからこそ、自分の推し(好きなこと)に出会えた感動を、自分の言葉で語りたいという想いを、誰もが一度は感じたことがあると思います。

この本は、「この感動を、自分の言葉で語りたい!もっと世界に知って欲しい」と言う、あなたの気持ちを後押ししてくれる一冊なんだよ!

昭和生まれ平成育ちの私としては「語りたいことは山ほどあるのに、語れる場所も友人もいない」と、悔し涙を流したことが思い出せます(←ただのオタク)
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
自分の好きなものや人を語ることは、自分の人生を語ること
本書では、具体的に推しの定義から丁寧に説明します。
これまでも「ファン」や「贔屓」といった言葉はありましたが、「推し」という言葉の特徴は、「推薦したい」、つまりは誰かに薦めたい、という感情が入っていること。単にこの対象を好きなだけじゃなくて「他人に紹介したい!」「魅力を言葉にして素晴らしさを分析したい!」という欲望を持つことが、推しの条件かもしれません。
「好き」を言語化する技術~推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しか出てこない(三宅香帆著/24ページ)より引用
著者は(第一章)で「自分の好きなものや人を語ることは、自分の人生を語ること」と説明します。
「好き(推し)を」言語化するうえで、まっさきに注意することは、「他人の感想を見ない」、「自分だけの感情が一番大事」だと説明します。
注意すべき点として、何も考えずに言葉にすると「ありきたりな言葉」しか出てこないと解説されています。他人の言葉に支配されず、ありきたりな言葉を使わない「オリジナルな感想」こそが大切だと説きます。

本著では、語彙力がない、言語化が下手。すぐに他人の言葉に影響を受けてしまう人でも「自分の言葉をつくる」ための、ちょっとしたコツも紹介されていますので、そこは実際に読んでお楽しみください。
誰でも言語化の力を鍛えることができる
本書の大きな特徴は、「誰でも言語化の力を鍛えることができる」と明確に提示している点にあります。
言語化の力は、センスや文学的な素養が必要な特別な能力ではなく、視点と思考の習慣を変えることで育てていける「技術」であると著者は繰り返し説いています。
この視点は、文章を書くことや伝えることに苦手意識を持っている人にとって、大きな励ましとなるでしょう。
さらに、巻末では実際の読書感想分の例文やレビューを書く際のテンプレートや練習問題のような例題も紹介されており、「読んで終わり」ではなく、「読みながら試す」「読み終えてすぐ実践できる」構成となっているのも実用書としての魅力です。

この本は、「好き」をただの感情で終わらせるんじゃなくて、それを他の人に届く言葉へと変えてくれる魔法のような本だね♬
何となく心を動かされたその瞬間を、自分の言葉で丁寧にすくい上げていく――その繰り返しが、言葉の力を磨いていくのだということを、そっと教えてくれる一冊です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
言語化はビジネス・チーム運営でも武器になる

三宅香帆さんの『好きを言語化する技術』が強調するのは、
「自分の感じたことを、相手に届く言葉へと変換する力」 です。
このスキルは、ブログやSNSはもちろん、ビジネスやチーム運営の現場でも“圧倒的な武器”になります。
しかし、実際の現場ではこうした課題を多く耳にします。
- 伝えたつもりが誤解される
- スタッフごとに響く言葉が違う
- 会議で説明が長く、結局何が言いたいのかわからなくなる
- 子育て・家庭でも、言葉が伝わらず関係がギクシャクする
こうした課題は「言語化不足」だけでなく、
相手の性格タイプとの“ズレ” が原因になっていることがよくあります。

ここに強力に効くのが、伝え方コミュニケーション検定で学ぶ 「性格統計学」 の視点です。
📖 忙しいあなたも、移動中に“聴く読書”を。
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
コミュニケーション検定で学ぶ 「性格統計学」とは?
性格統計学は、稲場真由美氏が 16年間・12万人のデータを解析 して体系化した、
「どうすれば相手に伝わるのか」を科学的に導き出したメソッド。
人を ビジョン・ピース・ロジカル の3タイプに分け、
それぞれが“響く褒め言葉”“逆効果になる禁句(タブー)”を明確に示します。
この理論を知ると、日常のコミュニケーションが驚くほど変わります。
たとえば、同じ「頑張ったね」という言葉でも、
タイプごとに響く言い方はまったく異なります。
- ビジョンタイプ:「未来にどうつながるか」を示すと動く
- ピースタイプ:「気持ちに寄り添う言葉」が安心材料になる
- ロジカルタイプ:「理由・根拠」を示すと納得する

言語化 × 性格統計学 = “相手に合った伝え方”ができるようになる
ということなんだね!
チームリーダーであれば、スタッフ育成や会議運営がスムーズになり、
ケアマネであれば、利用者や家族ごとに響く説明ができ、
家庭では、子どもやパートナーへの声かけが劇的にうまくいきます。
これこそが、ビジネスでも家庭でも“言語化が武器になる”理由です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
コミュニケーション検定で“伝える力”を可視化
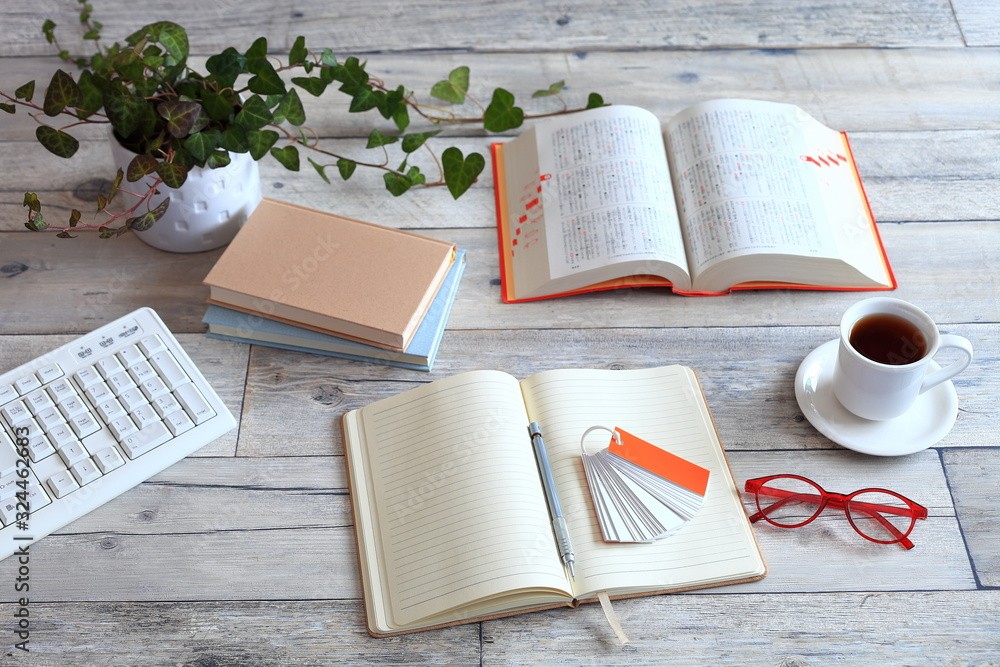
三宅香帆さんの本で“自分の言葉を磨く力”を身につけたら、
次に取り組みたいのが 『伝え方コミュニケーション検定(中級)』 です。
この検定の特徴は、単なる資格ではなく
「相手に伝わる話し方を“科学的に学べる”講座であること」。

具体的にどのような内容なんだろう・・・?
✔ 学べる内容は超実践的
中級では、性格統計学の3タイプ(ビジョン・ピース・ロジカル)それぞれに対して
- 響く言葉
- 禁句
- よくあるコミュニケーションギャップ
- 子育て・夫婦・職場での具体例
を徹底的に理解します。

相手に「刺さる」言葉や「言ってはいけない」NGワードは理解できるけど、コミュニケーションギャップや具体例を挙げてくれるとわかりやすいね。
加えて、
- 自己肯定感のつくり方
- リフレーミング
- 家族構成別のケーススタディ
など、日常の悩みに直結するテーマも学習できます。
視聴時間は 170分 とコンパクトなのに、内容はかなり濃いことが特徴です。
✔ “すぐに使える”と評価された実績
この性格統計学は、2016年度に 文部科学省の調査研究事業 の一部にも採用。
実施校の 98%の先生が肯定的評価 をし、
87% が実践して「役に立った」と回答 するほど、現場に効果が出ています。

家庭でも「子どもに合う言葉がわかって自己肯定感が上がった」という声が多数。
まさに、実生活レベルで効くコミュニケーション技術です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
✔ 履歴書にも書ける“資格”
中級に合格すると、
「日本ライフコミュニケーション協会認定:コミュニケーション検定・中級」
の資格が取得できます。
これは企業が求めるスキル1位「コミュニケーション力」を
エビデンスとして示せるため、就職・転職でも強い武器になります。

自分のコミュニケーションの力が履歴書に書けるってなんだか不思議な感じ♬
試験はWebで 選択式15問・所要15分 ほど。
動画視聴と合わせても 約3時間で取得可能 と効率的です。
📖 忙しいあなたも、移動中に“聴く読書”を。
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
✔ 学びやすく、続けやすい
『伝え方コミュニケーション検定』は学びやすく、続けやすいことがポイントです。
具体的には以下の4点が挙げられます。
- 6ヶ月間動画見放題
- 家族3名分の診断レポート付き
- ZOOMフォロー講座が月1回(2回まで無料)
- スマホ・PC・タブレットで受講可能
忙しい人でも確実に受講できる仕組みになっています。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
まとめ:

三宅香帆さんの著書、『好きを言語化する技術』は、自分の感じたことを“自分の言葉”で伝える力を磨いてくれる一冊です。
どこに心が動き、なぜ魅力を感じたのかを言語化できるようになると、ブログやSNSだけでなく、会議、スタッフ育成、家族との対話まであらゆる場面でコミュニケーションがスムーズになります。
さらに「伝え方コミュニケーション検定」で学べる性格統計学を組み合わせると、相手のタイプに合わせた“届く伝え方”が身につきます。
ビジョン・ピース・ロジカルそれぞれの響く言葉、タブーを知ることで、誤解や衝突が減り、人間関係のストレスも大幅に軽減。言語化スキルと伝え方の科学を掛け合わせることで、リーダーシップ、発信力、家庭内コミュニケーションまで劇的に変化します。
三宅香帆『好きを言語化する技術』=自分の言葉を整える力
コミュニケーション検定(性格統計学)=相手に届く言葉を磨く力
この2つを組み合わせると、
あなたの発信・仕事・家庭のコミュニケーションが劇的に変わります。

三宅香帆『好きを言語化する技術』が気になったかたは、ぜひ一度、本を手に取って読まれることとをお勧めします。本を開いた瞬間から「言語化」への道が開きます。

コミュニケーション検定(性格統計学)が気になった方も一度、チェックしてみてね。
📖 忙しいあなたも、移動中に“聴く読書”を。
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
【関連記事:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』を読んで考える|一生モノのキャリアを構成する方法】