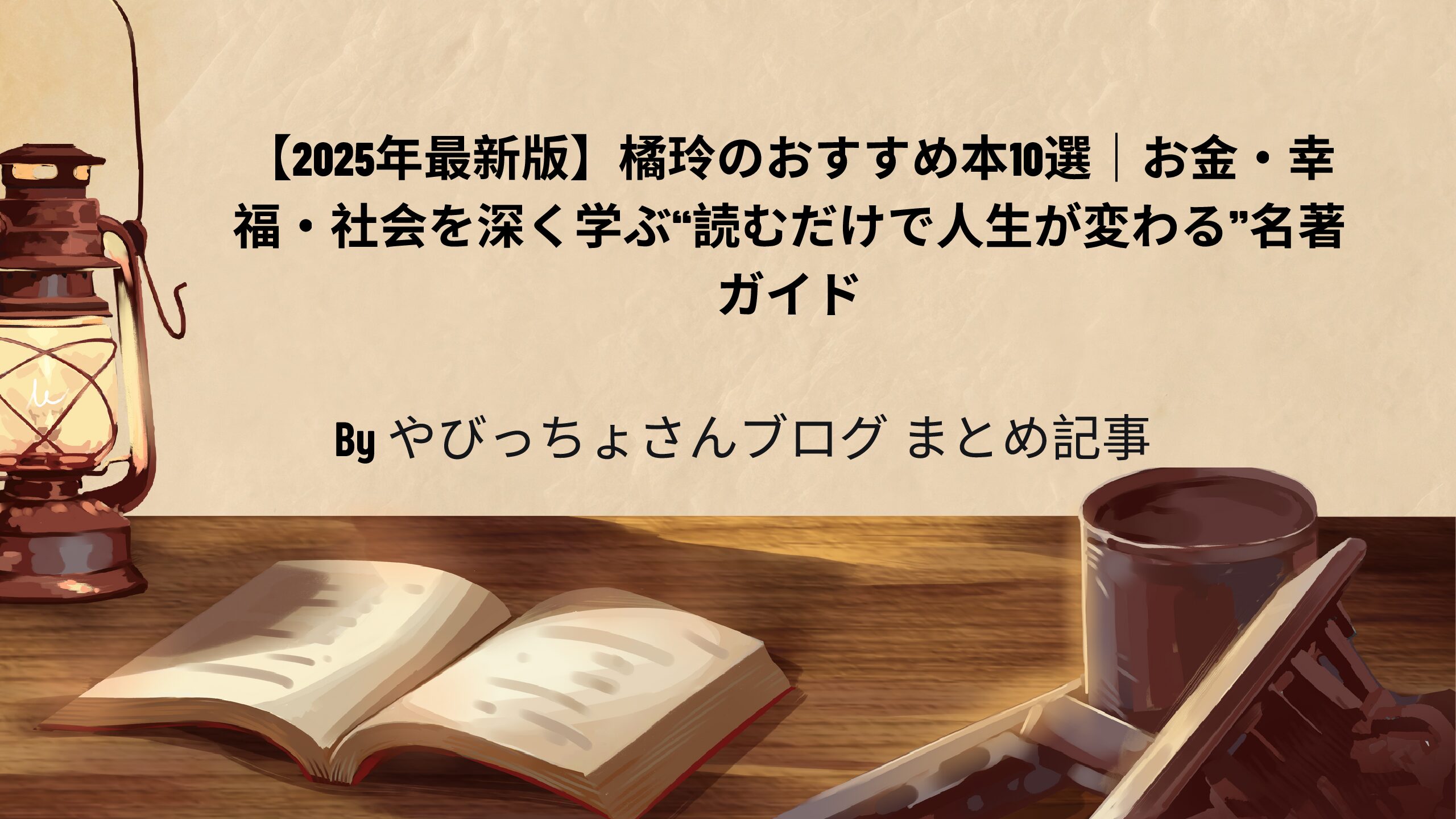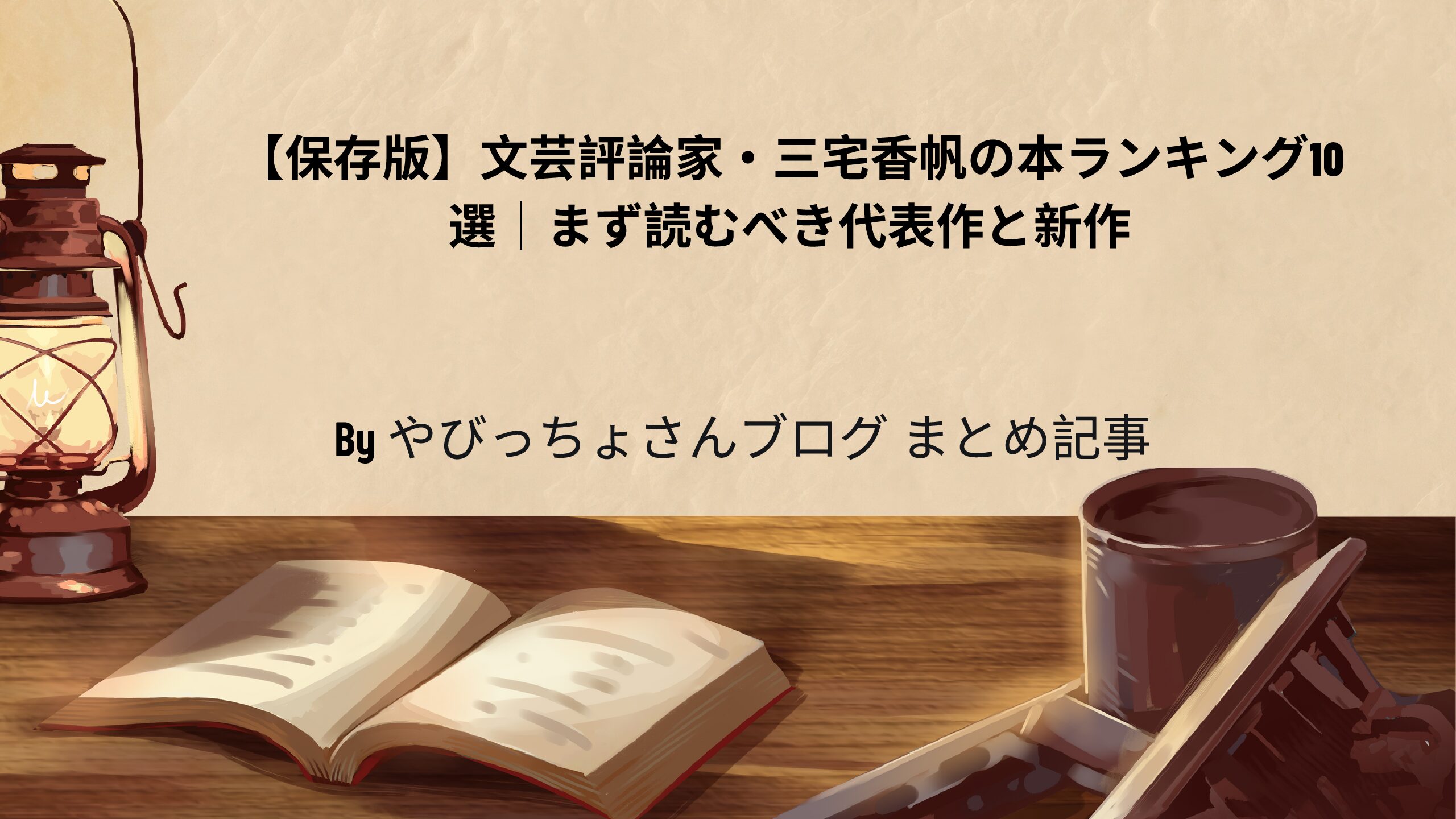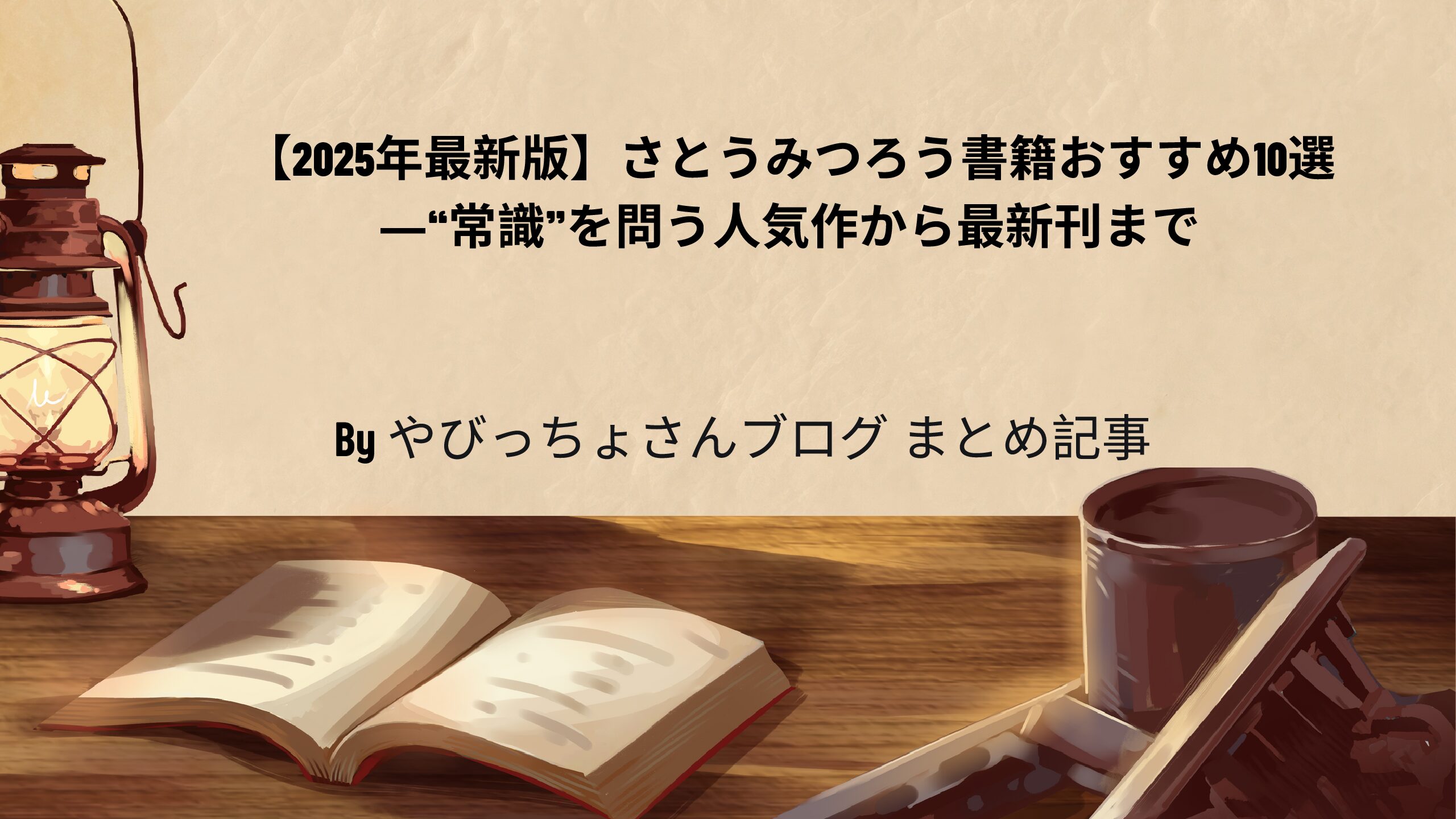データで社会を読み解き、「お金」と「幸せ」の本質を問い続ける作家――それが**橘玲(たちばな あきら)**です。
彼の本は、単なるマネー本でも自己啓発書でもありません。私たちが無意識のうちに信じている“常識”を裏返し、人生のルールを「再設計」するための知的ツールです。
本記事では、2025年最新版として、橘玲の著作から厳選したおすすめ10冊をテーマ別に紹介します。
代表作『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』や、社会のタブーをえぐる『言ってはいけない』、そして親子で楽しく学べる新定番『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』まで――。

「自由に生きたい」「幸せの正体を知りたい」「お金との賢い付き合い方を学びたい」そんなかたにこそ読んでほしい、 “読むだけで人生が変わる”橘玲の世界を、わかりやすく案内していきます。

この記事で紹介する本のレヴューに関しては『紀伊国屋書店』さんのホームページを参考にしました。気になる本があれば、『紀伊国屋書店』さんのホームページもチェックしてみて下さいね♬
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
橘 玲(たちばな・あきら)プロフィール

橘 玲(たちばな・あきら)さんは、1960年、東京都生まれ。作家・評論家。早稲田大学第一文学部卒業します。
出版社勤務を経て、2002年に小説『マネーロンダリング』でデビュー。以後、経済・投資・幸福・社会構造を横断的に論じる著作で高い評価を受ける。
代表作『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』では、**「資本主義のルールを理解すれば、誰もが自由に生きられる」**という理念を提示。
さらに『言ってはいけない』『幸福の「資本」論』『上級国民/下級国民』などで、社会のタブーや構造的格差、そして人間の幸福のメカニズムに切り込んだ。
その主張は、経済学・心理学・進化生物学・社会学など幅広い分野の知見を融合させた“知の実践”として、多くの読者に影響を与えている。
特に「お金」「自由」「幸福」をテーマにした分析は、ビジネスパーソンから教育関係者、親子世代まで幅広く支持されています。

橘玲さんの活動として、近年では子どもと一緒に金融リテラシーを学ぶための書籍『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』を発表し、次世代教育の分野にも活動を広げているんだ。

橘玲さんは、メディアへの顔出しをされておらず、YouTubeチャンネルも開設はしていませんが、岡田斗司夫さんが橘玲さんのことをリスペクトされており何本も動画に挙げているよ♪
【橘玲さんのYouTubeを観るなら】
なぜ今、橘玲を読むべきなのか

今の社会は、努力すれば報われるという“古い物語”が通用しなくなりつつあります。学歴や年収だけでは幸せを測れず、誰もが「どう生きるか」の答えを探しています。そんな時代にこそ読むべきが、橘玲の本です。
橘玲は「お金」「幸福」「自由」「社会構造」を科学的に分析し、感情論ではなくデータと論理で人生を読み解きます。
『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』では資本主義のルールを解説し、自由に生きる力を。『言ってはいけない』では社会のタブーを明らかにし、現実を直視する勇気を。さらに『幸福の「資本」論』では、幸福をお金ではなく「資本」という概念で捉え直します。
橘玲の魅力は、冷徹な現実分析の奥にある“希望を捨てない現実主義”。彼の本は、投資家やビジネスパーソンだけでなく、学生や親世代にも広く読まれています。

ネットやSNSと言った、膨大な情報に惑わされる今だからこそ、橘玲さんの著作は“思考の軸”を取り戻す道しるべとも言えるんだ。彼の言葉は、「自分の頭で考える力」を呼び覚ますはずだよ。

うん、なんかわかる気がする!スマホとかSNSって、いろんな人の考えがいっぱい出てくるけど、どれが本当かよくわかんなくなるんだよね。でも、 “自分の頭で考える”ってかっこいいね。ちゃんと考えられる人になりたいな。
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
橘玲のおすすめ本10選【最新版2025】
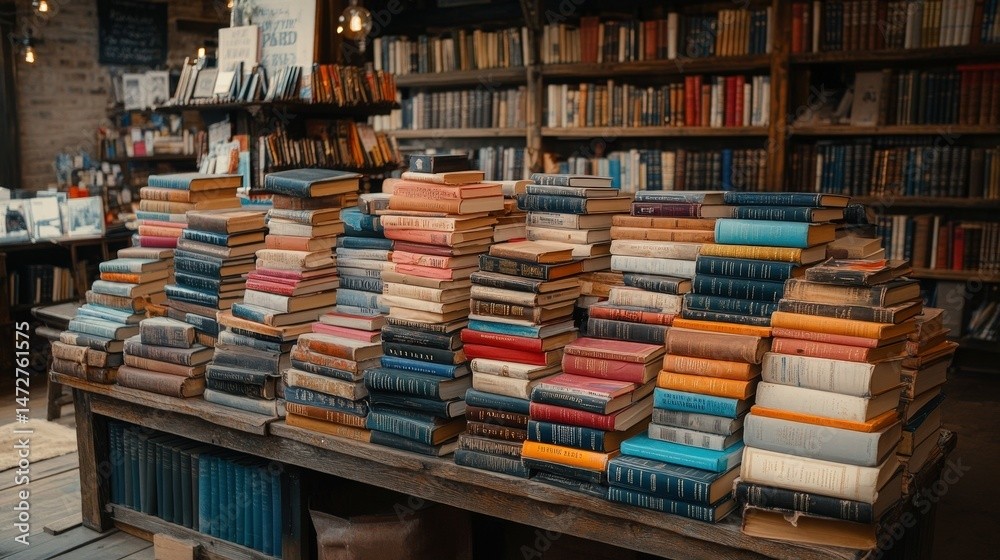
橘玲の著作は、「お金」「幸福」「自由」「社会構造」というテーマを、データと論理で読み解く知の冒険書です。
難解な理論をやさしく噛み砕きながら、私たちが生きる社会の“ルール”と“幸福の正体”を明らかにしてくれます。

ここでは、初めて橘玲を読む人から長年のファンまで楽しめるように、2025年最新版として必読の10冊を厳選しました。

お金を賢く使いたい人、自由に働きたい人、人生の意味を考えたい人――それぞれの目的に合った一冊が、きっと見つかるはずだよね!
| No. | 書籍タイトル | 解説(約80字) |
|---|---|---|
| ① | お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 | 資本主義のルールを理解すれば自由に生きられる。お金の「仕組み」を解き明かす実践的バイブル。 |
| ② | 言ってはいけない 残酷すぎる真実 | 社会のタブーを科学的データで分析。遺伝や格差など“残酷な現実”を直視する問題作。 |
| ③ | 幸福の「資本」論 | 金融・人的・社会の3資本から幸福を設計。お金に依存しない「豊かさ」の理論書。 |
| ④ | 上級国民/下級国民 | 日本社会の分断構造を分析。教育と情報が生む“見えない格差”を描く社会批評。 |
| ⑤ | バカと無知 | 人間の非合理性を進化心理学で解説。思い込みや愚かさを笑いながら学べる教養書。 |
| ⑥ | スピリチュアルズ 「わたし」の謎」 | 科学と宗教を越えて「自己とは何か」を探求。橘玲の哲学的一面が光る異色作。 |
| ⑦ | 新・貧乏はお金持ち | 雇われずに生きる力を提案。自由と自立を重視した“個人時代”の働き方論。 |
| ⑧ | 臆病者のための株入門 | 感情に左右されず投資する思考法を伝授。初心者が資産形成を学ぶ最良の入門書。 |
| ⑨ | 世界はなぜ地獄になるのか | AIと資本主義の暴走を警告。現代社会のリスク構造を読み解く知的サバイバル論。 |
| ⑩ | 親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの? | 子どもと一緒に「お金の仕組み」を楽しく学べる入門書。家庭での金融教育に最適。 |
橘玲さんの著作は大きく4つのジャンルに分けられます。
- 「お金・資産形成」では、資本主義のルールを理解し、経済的自由を得る方法を学ぶ。
- 「幸福・人生設計」では、幸福をお金だけでなく“人的・社会資本”で再定義。
- 「社会・格差分析」では、遺伝・教育・情報などが生む構造的格差を読み解く。
- 「思想・哲学」では、「自分とは何か」「どう生きるか」という根源的な問いに迫ります。

知識だけでなく“生き方の軸”を得られるのが橘玲作品の真価と言えるんだ。

パパ!次に1冊づつ、橘玲さんの書いた本を具体的に紹介していこうよ♪
1冊目:『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』
橘玲氏の『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方―知的人生設計のすすめ(新版)』は、「自由な人生」を実現するための経済的独立の指南書として高く評価される一冊です。
著者は「国・会社・家族に依存せずに生きるには、1億円の資産が目標」とし、それを勤勉・倹約・共働きで誰でも達成可能だと説きます。
本書のタイトルにある「黄金の羽根」とは、制度の歪みが生む偶然の幸運を意味し、それを見抜いて活用する知恵こそが“賢く生きる力”だと定義。
税制や金融の仕組みを理解し、合法的に利益を最大化する具体策が提示されています。資産形成の公式「(収入-支出)+(資産×運用利回り)」を軸に、人生設計を数式で整理する点も特徴です。

読者からは「これほど納得感のある投資本はない」「自分が言語化できなかった理論を明快に説明してくれた」との声が多く寄せられています。特にPART2の法人化ノウハウは、小規模経営者やフリーランスにとって実用的で、「日本版・金持ち父さん」とも称されます。
一方で、金融リテラシーに自信のない読者には難解な部分もありますが、それでも「経済的自立を志すすべての人に一読の価値あり」と評されます。
制度を理解し、合理的に生きるための“現代の知恵”が詰まった一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
2冊目:『言ってはいけない 残酷すぎる真実』
橘玲の著書『言ってはいけない―残酷すぎる真実』(新潮新書)は、進化論・遺伝学・脳科学の知見をもとに、社会の「きれいごと」を切り裂く衝撃作です。
著者は「人間は平等」「努力は報われる」といった信念を幻想とし、私たちが避けてきた“不都合な現実”を突きつけます。
たとえば、「努力は遺伝に勝てない」「美人とブスの間には残酷な格差がある」「子育ての苦労はほぼ無意味」といった主張が展開され、読者の常識を根底から揺さぶります。
本書の魅力は、誰もが心の奥で感じながらも言葉にできなかった社会の矛盾を、科学的データをもとに冷徹に分析している点にあります。
一方で、その内容はあまりに残酷で、読む人によっては強い不快感や反発を覚えるでしょう。賛否が分かれるのも当然で、「良薬口に苦し」と評されるように、受け止め方次第で“人生の見方”が変わる書でもあります。
2017年の新書大賞を受賞した本作は、「現実を直視する勇気」を問う知的挑発書です。遺伝・格差・性・親子関係などのテーマに興味がある人にとって、避けては通れない一冊といえるでしょう。

“努力は遺伝に勝てない”とか、 “かわいい子とそうじゃない子のあいだにはすごい差がある”とか……ちょっとショックかも。でも、もしかして“本当のこと”をちゃんと考えようって言いたいのかな?うーん……むずかしいけど、気になる~
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
3冊目:『幸福の「資本」論』
橘玲著『幸福の「資本」論―あなたの未来を決める3つの資本と8つの人生パターン』(ダイヤモンド社, 2017)は、「幸福とは何か」をデータと構造から読み解く画期的な一冊です。
著者は、「人間は幸福を求めて生きるが、幸福になるように設計されていない」という前提のもと、幸福を構築するための3つの資本を提示します。すなわち…
- ①自由をもたらす「金融資産」
- ②自己実現のための「人的資本」
- ③他者とのつながりによる「社会資本」
これらの組み合わせにより、「超充」「リア充」「ソロ充」「プア充」など8つの人生パターンが導かれ、自分がどのタイプに属し、どう変化していくかを考える手引きとなります。
本書の魅力は、経済・社会・心理・生物学を横断する知的な構成と、抽象論に終わらない実践的な提案にあります。
たとえば、幸福のポートフォリオとして「金融資産の分散投資」「子供時代のキャラを活かす仕事選び」「家族と仲間による二重の愛情空間」などが紹介されます。

読者からは、「理屈と感情のバランスが取れた幸福論」と高く評価されています。『言ってはいけない』のような挑発的な語り口を保ちつつも、本書はより温かく、現実的です。ユヴァル・ハラリの幸福論よりも“仏教的な悟り”に近いと評する声も。自分の幸福を設計するための実践的指針として、一度は手に取りたい人生設計書です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
4冊目:『上級国民/下級国民』
橘玲氏の『上級国民/下級国民』は、現代日本に深く刻まれた「見えない階級社会」を暴き出す一冊です。
著者は「下級国民に一度落ちると、這い上がれないまま老いと死を迎える」という冷厳な現実を指摘し、共同体や性愛から排除される人々の存在を「残酷な運命」として描いています。
その背景には、世界的な「知識社会化・リベラル化・グローバル化」の潮流がある。全体としては豊かになりながらも、教育や情報を持つ“上級国民”と、それを持たない“下級国民”に分断されていくという構造が、アメリカのトランプ現象やブレグジットとも通じると論じる。
本書は、
- ①平成以降の労働市場に生まれた「下級国民」層
- ②「モテ/非モテ」という性愛格差
- ③リベラル社会が生む究極の自己責任
という三部構成。特に「学歴=階級」を決定づける最大の要因とする視点や、「事実上の一夫多妻社会」という分析は衝撃的だ。
読者からは「身も蓋もないが、現実を鋭く突く」との評価が多く、後半のグローバルな階級論や知識社会批判は「読む価値が高い」と評されます。一方で、「毒薬のような本」として、自己責任論を短絡的に受け取らぬように注意も促されています。

うーん、 “幸福”とか“公正”ってむずかしい言葉だね😅でも、 “みんなが幸せに生きられるようにするにはどうしたらいいか”ってことでしょ?そういうのを考えるのって、なんか大人の宿題みたいだね。わたしだったら、みんなが仲よくできる社会がいいな〜って思う✨
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
5冊目:『バカと無知』
橘玲氏の『バカと無知―人間、この不都合な生きもの』(新潮新書、2022年)は、人間という存在を「合理的ではない、厄介な動物」として冷静に分析した一冊です。
著者は、科学的知見や国際的データをもとに、人間の「バカさ」と「無知さ」が社会や個人の行動にどう影響しているかを明らかにしていきます。

特に印象的なのは、**「正義は最大の娯楽である」という指摘です。人は自分が正しいと信じることで快感を得るが、それが他者への攻撃や差別を正当化する力にもなるという。さらに、「バカとは自分がバカであることに気づかない人間」であり、「知らないことを知らない」という二重の無知こそが社会の混乱を生むとする洞察は鋭いの一言です。
**「記憶は偽物である」**という主張も衝撃的です。人の記憶は再生ではなく再構成されるものであり、感情や状況によって容易に書き換えられる。これが冤罪や誤解を生む原因になるという科学的事実は、倫理や司法にも深い示唆を与えます。
読者からは、「耳の痛い現実を突きつけられるが、納得してしまう」という声が多く聞かれました。日本人の数的思考力が国際的に見ても低いというデータの提示など、自己評価の甘さを戒める部分もあります。
本書は「人間の本性を否定せず、理解したうえでどう生きるか」を考えさせる。きれいごとを排し、現実を直視することでこそ、人は少し賢く、寛容に生きられる――そんな痛烈で実践的な「人間論」であるといえます。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
6冊目:『スピリチュアルズ 「わたし」の謎』
橘玲氏による『スピリチュアルズ―「わたし」の謎』(幻冬舎文庫、2023年)は、人間の「無意識」と「性格」を科学的に読み解く意欲作です。
タイトルから精神世界を想起しますが、実際にはパーソナリティ心理学と脳科学を融合させた人間理解の書だと言えます。
著者は、人間の性格は「無意識(無スピリチュアル意識)」に支配され、わずか8つの要素の組み合わせで成り立つと説きます。
その要素とは「明るい/暗い」「楽観的/悲観的」「共感的/冷淡」など、誰にでも当てはまる軸で、これらを知ることで“自分のキャラ”を理解し、最適な環境で生きるヒントが得られると言います。
理論の背景には、心理学で知られるビッグファイブ理論が挙げられます。
- 外向性
- 協調性
- 誠実性
- 神経症傾向
- 開放性
といった性格特性をベースに、橘氏は「無意識のプログラムとしての人格」を解説します。さらに、心理プロファイルが政治やマーケティングに応用されている現実にも触れ、「人は自分を知らぬまま操作される存在である」と警鐘を鳴らします。

この本ではね、“心理プロファイル”っていう、人の考え方や気持ちのパターンを分析する技術が、政治とかマーケティングに使われてることにも触れてるんだ。たとえば、ネットで好きな動画を見たり、検索したりするだけで、“この人はこういう考えを持ってる”って分析されて、知らないうちに広告とかニュースの内容が変わったりするんだよ。

えっ!じゃあ、わたしもスマホ見てるだけで“操作されちゃう”ってこと⁉
うーん……。じゃあ、わたしもちゃんと考える力を育てなきゃだね💪
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
7冊目:『新・貧乏はお金持ち』
作家・橘玲氏による『新・貧乏はお金持ち』(プレジデント社、2025年3月発売)は、2009年版を現代向けにアップデートした“自由な生き方の実践書”です。
テーマは、「雇われない生き方で格差社会を逆転する」。インフレや手取り減少が続く令和の時代に、どうすれば「ビンボー」から抜け出せるのかを、制度的・構造的に読み解きます。
その核心にあるのが**「マイクロ法人」**という仕組み。個人が小さな法人を設立することで、税制優遇を最大限に活用し、社会保険料を最適化しながら「会社に依存しない自由」を手にする方法を紹介しています。
節税・損益通算・キャッシュフロー管理といった実践的な財務知識が満載で、「フリーエージェントとして生きる」ための具体的戦略書となっています。
一方で、内容はやや専門的で、CAPMなどの金融理論が登場する点に「難しい」と感じる読者も多いようです。
しかし、「知れば実践したくなる」「節税と脱税の境界がリアル」といった声もあり、知的好奇心を刺激する一冊として高く評価されています。
社会制度への批判も鋭く、「働き方」「お金」「自由」を再考する現代版サバイバル指南書といえるでしょう。

パパも会社を興した時には、この本を参考にしたって話してたなぁ~
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
8冊目:『新・臆病者のための株入門』
橘玲氏による『新・臆病者のための株入門』は、株式投資を「臆病者」の視点から捉え直した画期的な入門書です。
初版(2006年)のロングセラーを大幅に刷新し、2020年代の新制度「新NISA」に対応した新版として再登場しました。
著者は、株式投資を“世界で最も魅力的なギャンブル”と位置づけ、リスクを恐れる人にも合理的に勝つ方法があると説きます。特に、「臆病者には臆病者の戦い方がある」というメッセージが全編を貫いています。
内容は、ライブドア事件やホリエモン、バフェット、B・N・Fといった具体例をもとに、株価の動きや複利・金利の仕組みをわかりやすく解説。
さらに、臆病者に最適な投資法として「全世界株式インデックス(オルカン)をNISAで長期積立する」戦略を提案します。短期売買のデイトレードについては「一般人には不向き」と明快に指摘しています。
読者からは、「18年経っても内容が色褪せない」「投資の本質を知る知的な入門書」と高評価。金利・複利の理解が深まり、実践的な指針を得たという声が多く見られます。

“正しくないことをする自由”って、なんかちょっとドキッとするね😳でもさ、まじめなだけじゃなくて、ちょっとユーモアがある人のほうが好きかも。なんか、 “頭で考える大人”ってこういう人のことを言うのかな〜✨
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
9冊目:『世界はなぜ地獄になるのか』
橘玲氏の『世界はなぜ地獄になるのか』(小学館新書、2023年8月刊)は、現代社会を覆う“正義の暴走”を鋭く描いた社会分析書です。
著者は「誰もが自分らしく生きられる社会」という理想が、SNSを通じて他者を断罪するキャンセルカルチャーへと変質し、人々が互いを監視・攻撃し合う地獄のような状況を生み出していると指摘します。
その姿を、天国(ユートピア)と地獄(ディストピア)が融合した「ユーディストピア」と名付けています。
本書では、小山田圭吾の炎上事件やポリコレ騒動、会田誠のキャンセル問題など具体例を通して、社会正義の名の下に生じる“宗教裁判”のような同調圧力を分析。

人々はSNS上で他者を裁き、**「80億人のステイタスゲーム」**に巻き込まれ、終わりなき比較と嫉妬の中で消耗していると描かれます。
読者の感想でも、「正義」が「暴力」へ転化する構造への警鐘が高く評価されています。一方で、著者はこの世界を生き延びるための処方箋として、「地雷原に近づかないこと」や「受け入れたふりをする」といった現実的なサバイバル術を提示。
理想と現実のねじれを冷静に観察しながら、SNS時代を生き抜くための知的防衛策を提示する一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
10冊目:『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』
橘玲氏による本書(筑摩書房、2024年11月刊)は、「社会は合理的に考える人が豊かになるようにできている」という前提のもと、親子で楽しみながら“お金の仕組み”を学べる一冊です。
目的は、家庭という安全な場で、子どもが市場経済のルールを理解し、合理的思考を身につけることにあります。
全体は初級・中級・上級の3段階構成で、「トレードオフ」「複利」「限界効用」「時間割引」「大数の法則」など、経済学や行動経済学のエッセンスをやさしく解説しています。
読者からは、「子ども向けながら大人にも示唆が多い」「経済の原理を家庭で自然に学べる」と高評価。特に、**“お金はトレードオフを解決する手段であり、無闇な金儲けをすすめる本ではない”**という姿勢が好感を呼んでいます。
複利やコスパ、ニッチ戦略、ダンバー数など、社会を理解するキーワードも豊富に紹介され、AI時代における「合理的に生きる力」を育む内容です。

この本にはね、“宿題をサボると格差は複利で広がる”とか、“親の言うことを聞いたほうがコスパが良い”とか、面白いたとえがたくさん出てくるんだよ。
少しのサボりが積み重なると、あとで大きな差になるってこと。勉強でもお金でも、コツコツ続ける人が強いって話だね。

え〜!?“宿題サボると格差が広がる”ってどういうこと?😳
それに“親の言うこと聞いたほうがコスパが良い”ってのもウケる😂
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
おまけ:橘玲の本から学べる“人生を変える3つの問い”
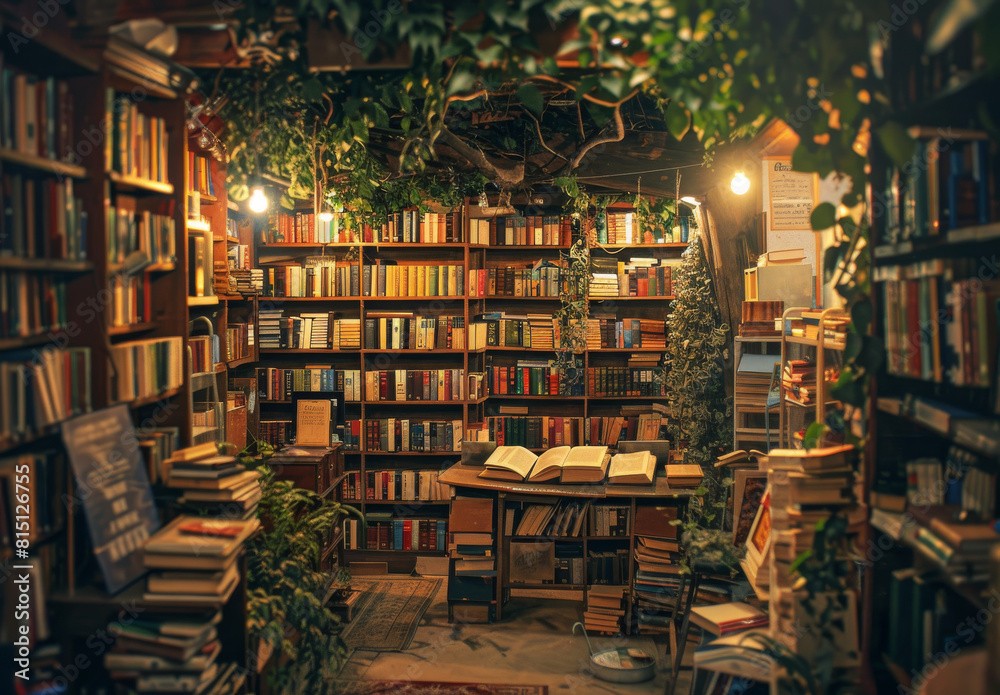
橘玲の著作を読み進めると、どの作品にも共通して流れる「思考の軸」が見えてきます。それは、単なるお金や知識の話ではなく、 “どう生きるか”を自分の頭で考えるための3つの問いです。

次に、橘玲の本から学べる“人生を変える3つの問い”について解説していきます。
①つ目の問い: 「お金」と「幸せ」はどんな関係にあるのか?
橘玲さんは、「お金は幸福の一部であって、すべてではない」と語ります。『幸福の「資本」論』では、金融資本だけでなく、人的資本(自分の能力)と社会資本(人とのつながり)が幸福を決めると説きます。
“豊かに生きる”とは、お金を増やすことではなく、自由に選べる力を手に入れることです。お金に囚われてしまうと『大切な何か』を見失ってしまうと警鐘をならします。
②つ目の問い: 「努力」だけで社会は変えられるのか?
『言ってはいけない』や『上級国民/下級国民』に描かれるのは、努力では越えられない現代日本の「構造的な壁」を描きます。
しかし橘玲さんはは、諦めを促すのではなく、「現実を知ることこそが自由への第一歩」と説きます。社会を知れば、より賢く、より戦略的に自分の人生を設計できるのです。
③ つ目の問い:「自分らしく生きる」とは何か?
『スピリチュアルズ』や『新・貧乏はお金持ち』では、「自分とは何か」「自由とは何か」を問い直します。他人の価値観に縛られず、自ら選び、責任を引き受ける――その覚悟が“自分らしさ”の本質です。
橘玲さんの本は、答えを教えてくれる本ではなく、問いを贈ってくれる本です。この3つの問いに向き合うことで、あなた自身の“人生の羅針盤”が見えてくるはずです。

“人生の羅針盤”かぁ……なんかかっこいい言葉だね✨でもそれって、“自分がどっちに進めばいいか”がわかるってことだよね?
“どう生きたいか”とか“なにを大事にしたいか”って、ちゃんと考えないと見えないのかも。わたしも、ちょっとずつ“自分の方向”を見つけていけたらいいな🌈
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
まとめ|橘玲の本は“思考の筋トレ”である
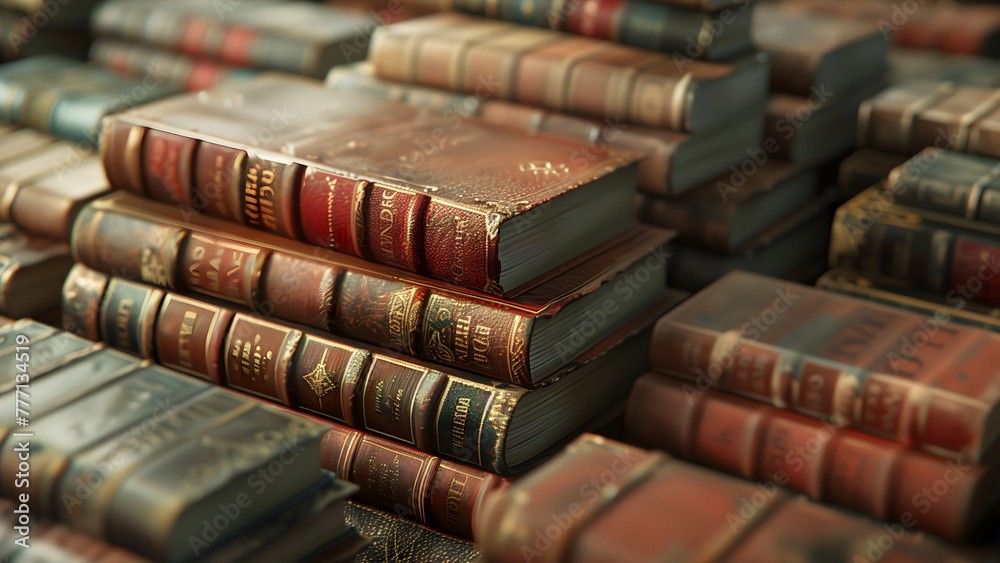
橘玲の本を読むことは、単に知識を得ることではなく、自分の思考を鍛える行為です。経済、幸福、社会構造といった複雑なテーマを、データとロジックをもとに読み解く彼の文章は、私たちの「思い込み」や「感情的判断」を静かに揺さぶります。
読むたびに、世界を少し違う角度から見つめ直すことになる――まさに“思考の筋トレ”なのです。
橘玲の魅力は、現実を突きつけながらも、決して悲観に終わらないこと。どんなに不合理な社会でも、「構造を知り、仕組みを理解すれば、人生は自分の手に取り戻せる」と語り続けます。
この姿勢は、単なる評論家ではなく、 “生き方の実践者”としての言葉です。
また、彼の著作群は読者のステージに合わせて寄り添ってくれます。働き方やお金に悩む人には『黄金の羽根の拾い方』がお勧めです。
幸福を見つめ直したい人には『幸福の「資本」論』、そして次世代と学びたい親には『親子で学ぶ どうしたらお金持ちになれるの?』が入り口になると思います。
どの一冊からでも、「自分で考える力」が確実に鍛えられていきます。

情報が溢れる時代だからこそ、
“考える力”を磨くことが、最大のリスクヘッジであり、最良の自己投資です。
橘玲の本は、そのための最強のトレーニングジム――
ページをめくるたびに、あなたの思考は確実に強く、自由になっていくでしょう。

著書の紹介については『紀伊国屋書店』さんのレヴューを参考にしました。気になる著書があれば、是非『紀伊国屋書店』さんのホームページもご覧ください♬
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
【関連記事:「読書の効用とは?人生を変える効果とおすすめ本15選【保存版】」】
【関連記事:【保存版】文芸評論家・三宅香帆の本ランキング10選|まず読むべき代表作と新作】
【関連記事:40代からのキャリア戦略|山口周『人生の経営戦略』に学ぶ人生の転換点の迎え方】
“PR:アフリエイト広告を利用しています”