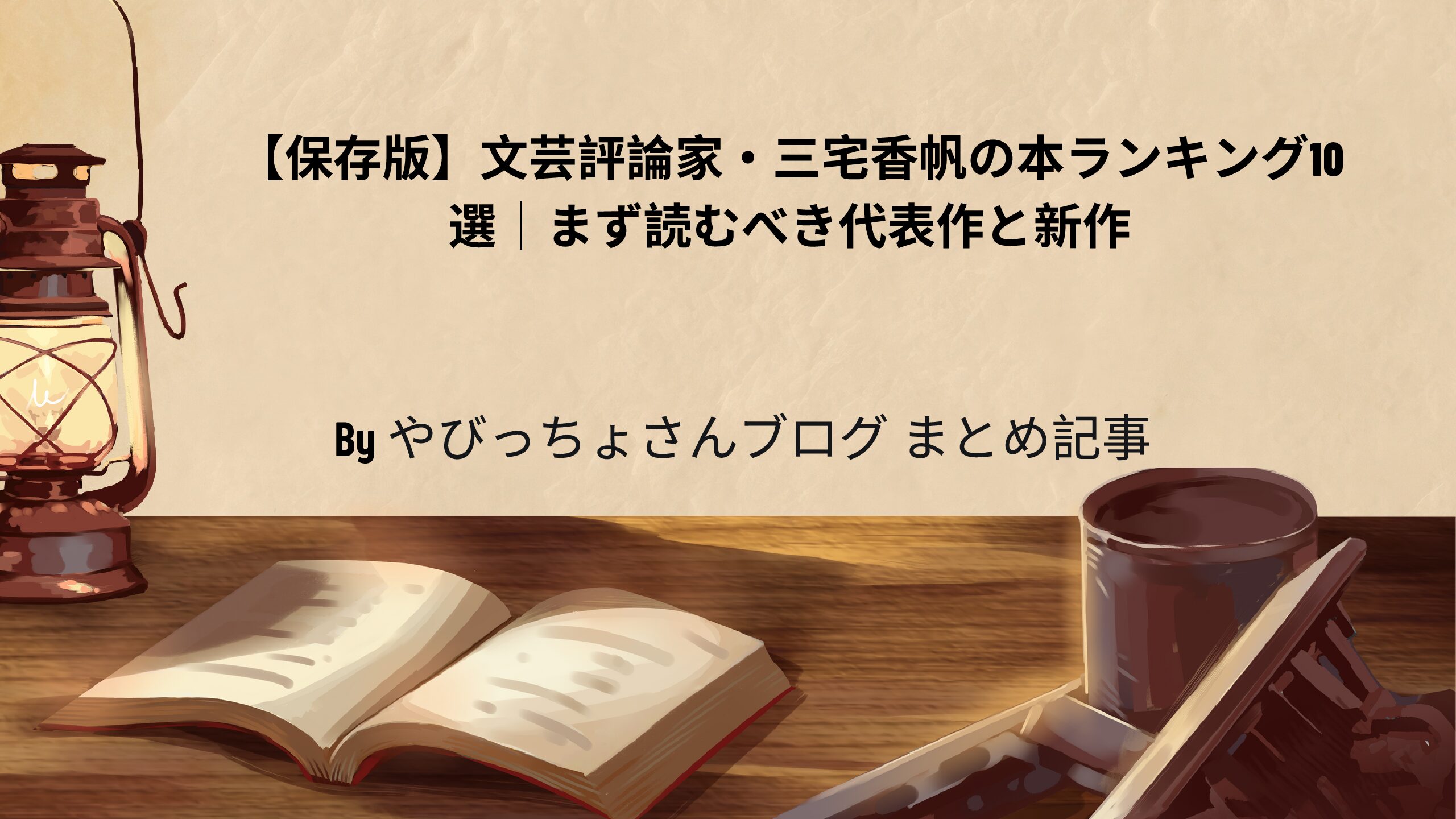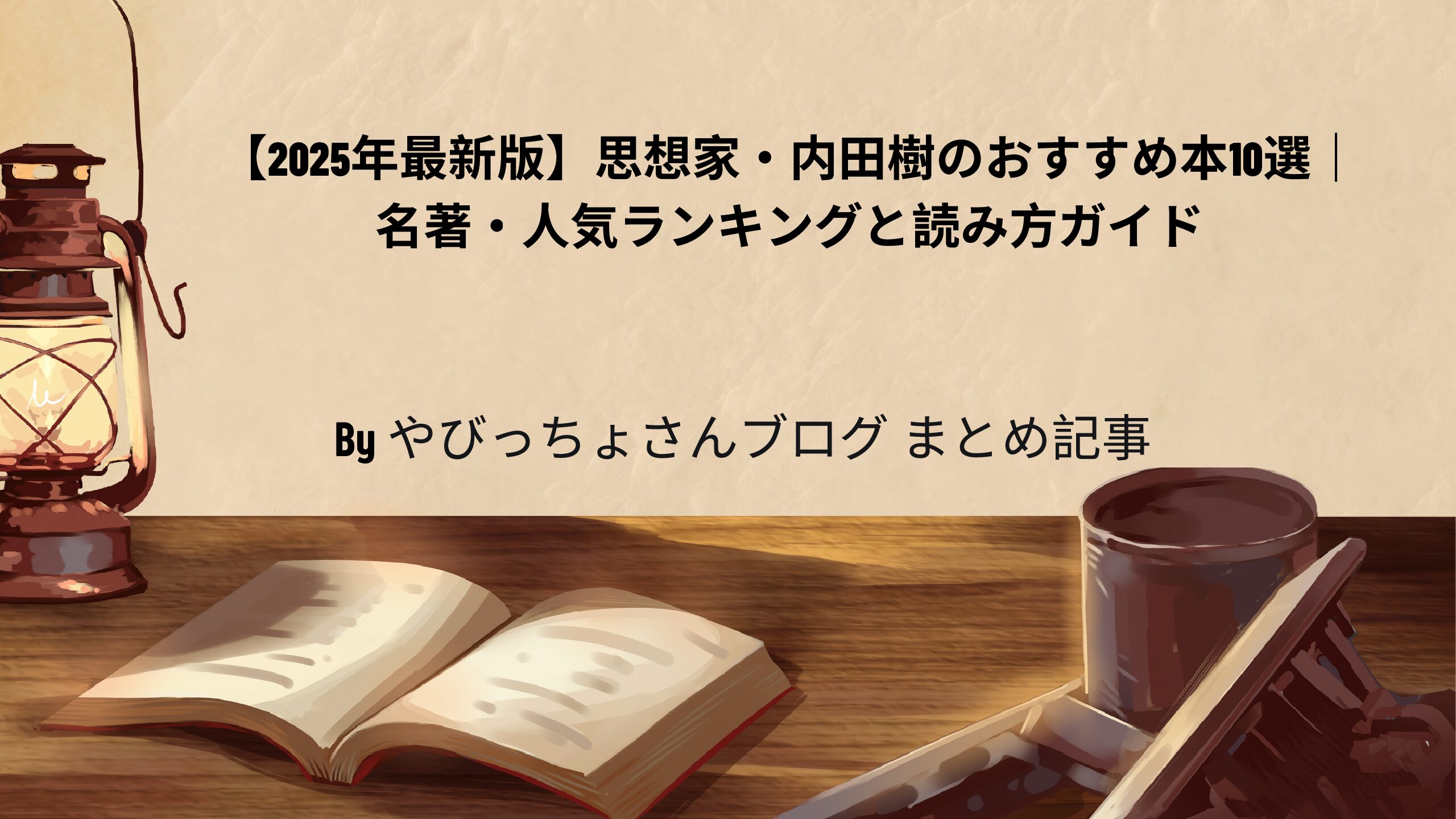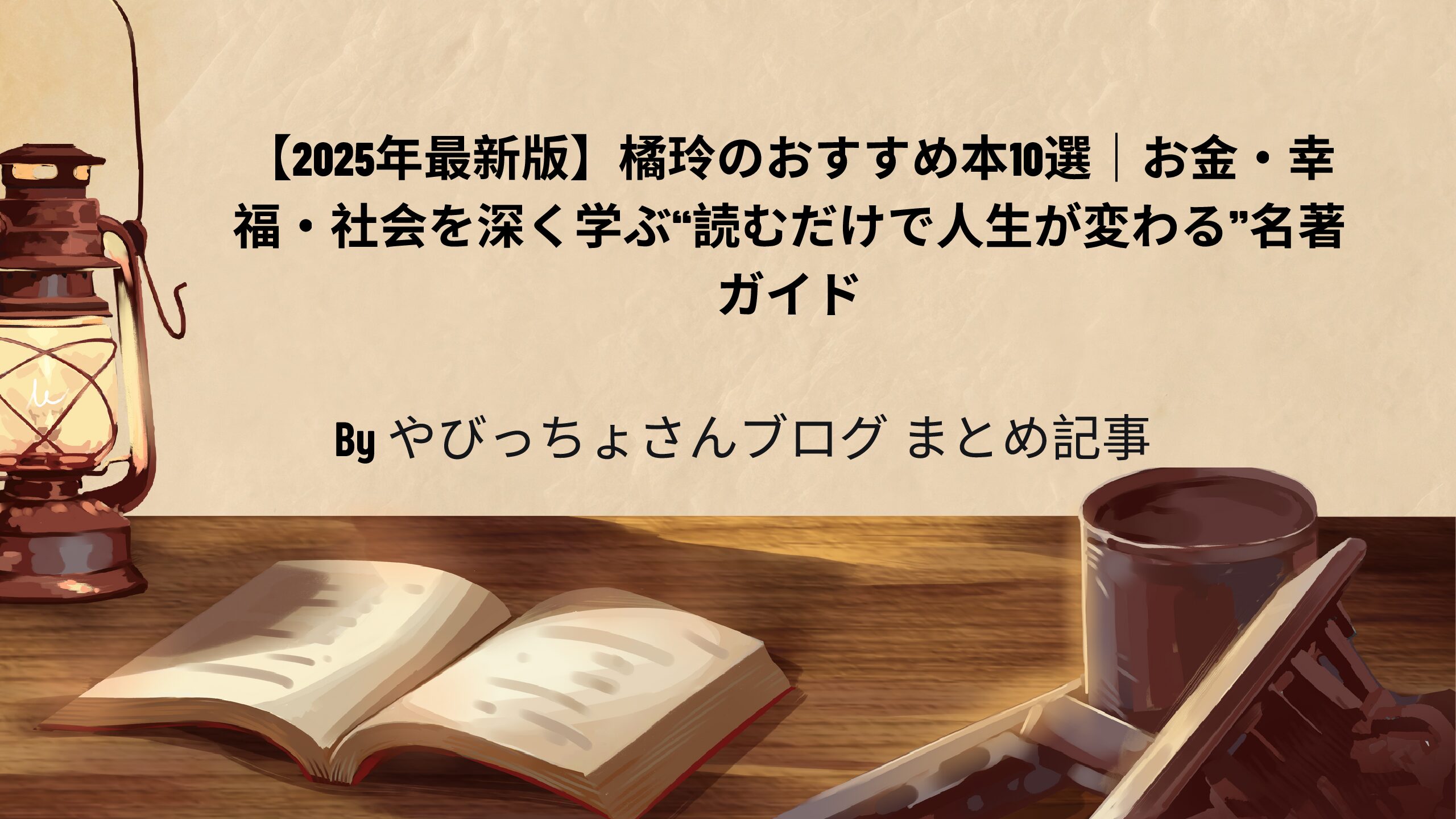現代を代表する文芸評論家・三宅香帆(みやけ・かほ)さん。
彼女の本は、単なる「読書案内」を超えて、私たちが“なぜ読むのか”“どう生きるのか”を静かに問いかけてきます。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が大ヒットを記録し、新書大賞やノンフィクション大賞を受賞したことで一躍脚光を浴びた三宅さん。
近年は『「好き」を言語化する技術』や『話が面白い人は何をどう読んでいるのか』など、ビジネス・教養・推し活の枠を越えて幅広い読者層を魅了しています。

この記事では、そんな三宅香帆さんの売れ筋・話題作・新刊をすべて網羅したランキングTOP10をお届けします。代表作の読みどころから、新作の注目ポイント、初心者におすすめの一冊まで── “読む喜び”をもう一度思い出させてくれる、彼女の言葉の世界を丁寧に案内します。

本記事では、著書の紹介として『紀伊国屋書店』さんのサイトを参考にしました。記事を観て気になった方は、『紀伊国屋書店』さんのサイトもチェックしてみて下さいね♬
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
三宅香帆さんのプロフィール
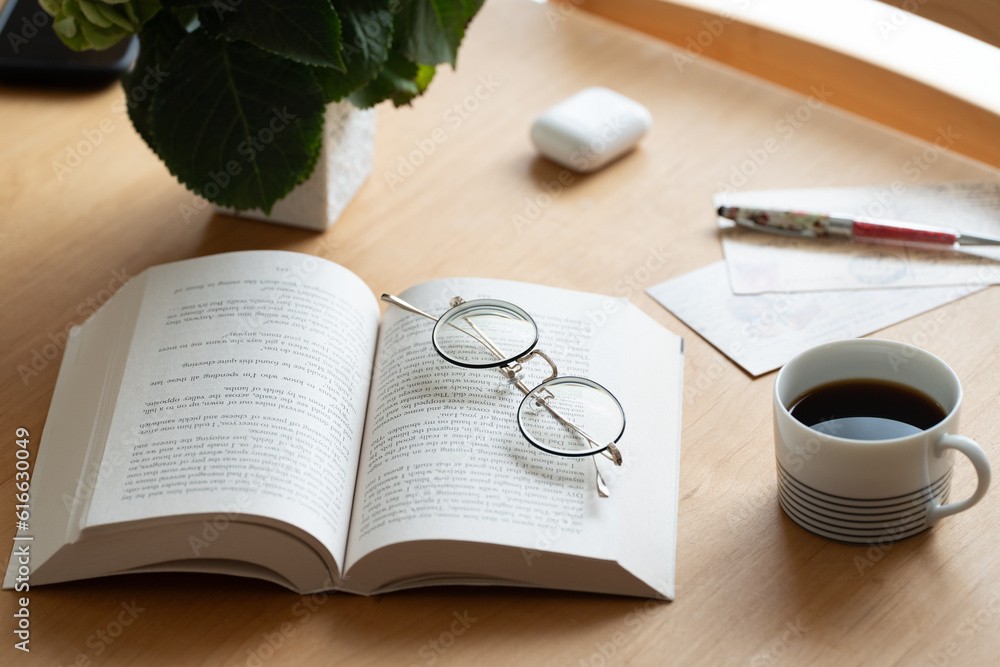
三宅 香帆(みやけ・かほ)
1994年生まれ。高知県出身。京都大学文学部を卒業後、京都大学大学院人間・環境学研究科で修士号を取得。専門は日本近代文学。
在学中から文芸評論や書評を執筆し、鋭い分析力と柔らかな文体で注目を集めました。
書店員・編集者を経て、現在は文芸評論家として、文学・思想・ポップカルチャー・ジェンダー論など幅広い分野で活動中です。
2024年刊行の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が20万部を突破し、
第10回「書店員が選ぶノンフィクション大賞」および「新書大賞2025」をW受賞。
そのほか『人生を狂わす名著50』『「好き」を言語化する技術』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』など、読書の楽しさを再発見させてくれる著作を次々と発表しています。

三宅 香帆さんは、YouTubeチャンネル『三宅書店【本を読むモチベを上げるチャンネル】三宅香帆 Kaho Miyake』を開設していて、2025年10月末時点で8.7万人の登録者数がいるんだ

沖縄県の那覇市にあるジュンク堂那覇店を紹介するチャンネルは何回も観たよ!パパと何回も来ている本屋さんがYouTubeで観れるとは思わなかった(笑)
【三宅香帆さんのYouTubeを観るなら】
三宅香帆おすすめ本ランキングTOP10【保存版】

読書の喜びを現代に取り戻す文芸評論家・三宅香帆さん。彼女の著作は、文学の奥深さを軽やかに語りながら、私たちの“生き方”や“言葉の使い方”を見つめ直させてくれます。
本記事では、受賞作から話題の新書まで――三宅香帆さんの代表作・人気作を網羅したおすすめ本ランキングTOP10【保存版】を紹介します。
| 順位 | 書名/出版社 | 内容紹介(約200字) | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書/2024) | 読書できないのは怠けではなく、社会構造のせい——。働くことと読むことの関係を、文学・思想・ジェンダーの観点から読み解く革新的な評論。読めない罪悪感を優しくほどき、再び本を開く勇気をくれる。新書大賞&ノンフィクション大賞受賞作。 | 仕事に追われて「本が読めない」と感じている人 |
| 2位 | 『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書/2024) | 「推しが尊い」「やばい」しか言えない――そんなもどかしさを言葉に変える実践的エッセイ。三宅流の“感情と言語化”メソッドで、好きなものをもっと深く語れるようになる。 | 推し活や創作で“伝わる言葉”を磨きたい人 |
| 3位 | 『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書/2025) | 「面白い人」は本をどう読んでいるのか? 会話や発想を豊かにする“読書の使い方”を指南。知識をストックではなく“物語として話す”力に変える最新作。 | プレゼンや雑談で話を広げたいビジネスパーソン |
| 4位 | 『人生を狂わす名著50』(ライツ社/2017) | 文学・思想・SF・恋愛小説など、ジャンルを超えて“人生を変えた本”を紹介。単なる書評ではなく、読書体験そのものの豊かさを描く一冊。三宅香帆を知るうえでの入門書。 | 「次に読む本」を探している読書好き |
| 5位 | 『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版/2019) | 文芸的感性で「人を惹きつける文の秘密」を解説。SNS・ブログ・原稿づくりに効く構成術や比喩技法を、やさしい語り口で紹介。4万部超のベストセラー。 | SNSやブログで“伝わる文章”を書きたい人 |
| 6位 | 『〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(笠間書院/2020・文庫2023) | 「名作=退屈」と感じる人にこそ読んでほしい。夏目漱石や谷崎潤一郎など古典文学を現代感覚で読み解き、“難しい”を“面白い”に変える名案内。 | 名作を理解したいけど途中で挫折してしまう人 |
| 7位 | 『名場面でわかる 刺さる小説の技術』(中央公論新社/2023) | 有名小説の“名場面”を分析し、「なぜこの一文が心に残るのか」を解説。作家志望にも読者にも役立つ「物語の構造」入門。創作系イベントでも人気。 | 小説を書いてみたい・構成力を学びたい人 |
| 8位 | 『それを読むたび思い出す』(青土社/2022) | 自身の読書遍歴と人生を交差させた、エッセイ的評論集。幼少期からの読書体験、恋愛、仕事、そして言葉との関わりが瑞々しい筆致で綴られる。 | 人生と読書の“重なり”を感じたい人 |
| 9位 | 『副作用あります!? 人生おたすけ処方本』(幻冬舎/2019・新書版2024) | 気分や悩みに効く“読書の薬箱”。「恋に落ちた」「落ち込んでる」などテーマ別に本を紹介。読み終えた後、気持ちがふっと軽くなる癒やしの一冊。 | 読書で気分転換・心の処方を探したい人 |
| 10位 | 『妄想とツッコミでよむ万葉集』(だいわ文庫/2019) | 古典文学を“ガチ解説”ではなく“全力で楽しむ”文体で紹介。恋愛・嫉妬・ギャグ満載の人間ドラマとして万葉集を再発見できる。 | 古典をゆるく楽しく読みたい初心者 |

本ランキングは「受賞実績」「販売部数」「レビュー数」「話題性」で総合評価しました。『こんな人におすすめ』を追加することで、ランキングにとらわれず自分に合った一冊が選べるようになっています。

上位3作は社会・感情・思考の“現代を読む”テーマが中心、下位もエッセイ・創作論・古典解説まで幅広く、読書層を選ばないバランス構成になっているね!次にランキング順に著書を紹介していきます♬
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
1位『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
文芸評論家・三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書, 2024年)は、「働くこと」と「読むこと」の関係を見つめ直す一冊です。
多くの社会人が「忙しくて本を読めない」と感じるのは怠けではなく、社会の構造的な問題だと著者は指摘します。
明治以降の日本における労働と読書の歴史を辿り、自己啓発書の登場や教養主義の時代、サラリーマン文化、そして仕事がアイデンティティと化した現代まで、読書の意味がどのように変わってきたかを描き出します。
効率化と成果を重視する社会では、読書は「非効率な行為」や「ノイズ」とみなされがちですが、著者はそこにこそ人間的な成長があると強調します。
印象的なのは「全身全霊をやめませんか」という提案。仕事にすべてを注ぐのではなく、半身で働き、半身で生きるという姿勢が、読書や趣味の余白を取り戻す鍵だと説きます。

「読まないのは本人の選択では?」という批判もありますが、本書は明快な答えよりも「なぜ読めなくなるのか」を考えるきっかけを与えてくれる内容です。働く人が再び“読む喜び”を思い出すための、静かで力強い読書論です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
2位『「好き」を言語化する技術』
三宅香帆氏の著書『「好き」を言語化する技術―推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)は、SNS時代の“推し活”に新しい視点を与える一冊です。
32万部を超えるベストセラーとなった本書は、「推しを語りたいのに言葉が出てこない」というもどかしさを抱える人に向けて、熱意を“伝わる言葉”に変える技術を教えてくれます。
本書は「推しを語ることは自分の人生を語ること」から始まり、準備・発信・文章化というステップで構成。終章では実際の例文やQ&Aも収録され、理論だけでなく実践的な内容になっています。
読者からは「自分の感情を自分の言葉で表現することの大切さを再認識した」との声が多数。特に、他人のレビューに影響されて自分の感想を修正してしまう人にとって、 “自分の言葉で語る勇気”を与えてくれる内容です。

「推し活」にとどまらず、文章表現やSNS発信、さらには子どもの読書感想文にも応用できるという汎用性も魅力です。言葉で「好き」を伝える力を育てたいすべての人に、必読の一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
3位『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』
三宅香帆著『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書、2025年9月刊)は、「話が面白い人はどんな読み方をしているのか?」という問いを通して、読書と会話の関係を解き明かす一冊です。
本書は〈技術解説編〉と〈応用実践編〉の二部構成で、「比較」「抽象」「発見」「流行」「不易」という五つの鑑賞技術を提示。
例えば「他の作品と比べる」ことで新しい視点を得たり、「書かれていないことを発見する」ことで深い読解が可能になるといいます。
読書をただの情報収集で終わらせず、物語の背景や時代性を自分の言葉で語るための“知的レシピ”が紹介されています。
読者の感想は賛否両論。肯定的な声では、著者の分析力やインプット・アウトプットの具体的手法が参考になったという意見が多く、特に「話のネタを仕込む五つの技術」が実践的だと評価されています。
一方で、タイトルから想像される実用書的内容を期待した読者には、後半が書評中心である点に物足りなさを感じたという声も。

総じて本書は、「読書を通して人とつながる力」を磨く指南書であり、読書と会話を結びつけるユニークな視点が光る一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
4位『人生を狂わす名著50』
三宅香帆著『人生を狂わす名著50』は、読書好きにはたまらない“危険なブックガイド”です。本書は、京都大学大学院に在籍していた著者が、書店員として働きながら感じた「読書の中毒性」をユーモラスに綴ったもので、もとは天狼院書店の人気記事から生まれました。
テーマは、「社会の常識に流されず、自分を変えてしまう本」。タイトルの“人生を狂わす”は、破滅ではなく「新しい価値観に出会ってしまう喜び」を意味しています。
紹介されるのは『高慢と偏見』『グレート・ギャツビー』『図書館戦争』など文学色の濃い50冊。それぞれに「読むべき次の3冊」も添えられ、合計200冊が提示されるという贅沢な構成です。

語り口は軽やかで、まるで友人が喫茶店で「この本、ヤバいよ」と語るような親しみやすさ。読者はページをめくるたびに、次々と“積読”を増やしてしまう。単なる書評を超え、本が人をどう動かすのかを体感できる一冊。読書の快楽と危険を思い出させる、まさに“人生を狂わす”名著ガイドだと言えます♬
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
5位『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』
三宅香帆著『文芸オタクの私が教えるバズる文章教室』(サンクチュアリ出版)は、文章に「文才」がなくても人を惹きつける文を書くための“技術”を体系的に解説した一冊です。
著者は文筆家・書評家として数多くの名文を分析してきた経験をもとに、「バズる文章」を4つの切り口——“つかみ・文体・組み立て・言葉選び”——に分け、具体的な法則として紹介しています。
たとえば「星野源の未熟力」は、あえて完璧でない語り口で読者の共感を呼ぶ方法を示し、「村上春樹の音感力」はリズムで読み心地をつくる技を明らかにします。
その他にも、秋元康の“裏切力”、さくらももこの“配慮力”、俵万智の“合図力”など、文豪から現代作家まで50名の表現を独自の観点で言語化しており、まるで“名文の解体新書”のような面白さがあります。
読者からは「抽象的だった文才を、法則として整理した点が画期的」「具体例が豊富で、読むだけで文章力が上がる」と高く評価されています。
特に、綿矢りさの“簡潔力”や又吉直樹の“かぶせ力”など、身近な作家の分析がリアルに響く。文章を書く人はもちろん、読書好きにも「名文の構造を見抜く視点」が得られる実用書です。

今日のSNS時代において、 “バズる”とは単に拡散されることではなく、“心に残る”ことだと気づかせてくれる1冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
6位『〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』
書評家・三宅香帆氏による『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(KADOKAWA)は、名作文学を“読めるようになる”ための実践的読書ガイドです。
夏目漱石やドストエフスキー、三島由紀夫など「名前は知ってるけど挫折した」古典を、少しのコツでぐっと身近に感じさせてくれます。
たとえば「まずあらすじを読む」「翻訳者を変えてみる」「タイトルからモチーフを想像する」など、文学を“攻略”する視点が新鮮。
文庫版では書き下ろし2編も追加されており、構成も「小説の読み方基礎講座」と「名作を楽しく読む方法」に整理されています。

取り上げられる作品群も幅広く、『カラマーゾフの兄弟』『グレート・ギャツビー』『吾輩は猫である』『ペスト』『金閣寺』といった王道名作を、ユーモラスかつ的確な分析で解説されています。
たとえば『吾輩は猫である』では“照れ屋な漱石が猫に託した本音”という視点を示し、『金閣寺』では“三島が金閣寺をアイドルのように見ていた”と語るなど、文学を身近な感情で読み解く語りが光ります。
読者からは「読んだふりを卒業できた」「名作へのハードルが下がった」と好評。文学に構えず楽しむ姿勢や、著者の誠実なまなざしに共感の声が多いです。

一方でネタバレが多く、 “真面目な書評集”と捉える人も。ただ総じて、本書は“わからないまま読む勇気”を与えてくれる一冊です。名作を通じて「読むことは、自分を映すこと」と気づかせてくれます。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
7位『名場面でわかる 刺さる小説の技術』
三宅香帆著『名場面でわかる刺さる小説の技術』(中央公論新社、2023年5月刊)は、「小説は名場面ひとつで勝てる」という大胆な主張を軸に、小説を“読む”と“書く”両面からその極意を説く一冊です。
京都大学大学院修了の書評家であり作家でもある著者が、人気作家25人の作品を題材に、読者の心をつかむ「名場面」の構造を徹底解剖しています。
本書は「講義編」と「名場面編」の二部構成。「講義編」では、名場面が生まれる条件や避けるべき“NG場面”を具体例とともに分析し、物語を印象的に仕上げるための考え方を提示します。
続く「名場面編」では、25作の名シーンを「関係を書く」「変化を書く」「場面を書く」「イベントを書く」という四つのテーマに分類し、それぞれの技術を読み解きます。
恋愛や友情、家族愛などの関係性の描き方、物語の転換点となる出来事の配置、場面設定による感情の高まり方など、小説が読者の心に“刺さる”瞬間の裏にある構成的・感情的な技術が明快に解説されています。

もともとは2021年4月〜2022年2月にウェブ連載された内容に加筆・修正を加えたもので、読み手にとっては「小説の面白さの正体を知る」指南書として、書き手にとっては「名場面を生み出すための実践書」として、創作好きの読者に強く刺さる一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
8位『それを読むたび思い出す』
三宅香帆の『それを読むたび思い出す』は、書評家として知られる著者が、自らの人生を「本」とともにたどる初の自伝的エッセイ集です。
すべて書き下ろしで構成され、「地元」「京都」「読書」という三つの章立てで、幼少期の記憶から大学時代、そして作家として東京で生きる現在までの軌跡が書かれています。

高知の田舎で育ち、京都で文学に出会い、東京で書き続ける。そんな「読んで、書いて、生きる」彼女の姿勢が、静かな筆致で綴られています。
読者の共感を集めるのは、著者の言葉の瑞々しさと感性の鋭さだといえます。「退屈が自分の養分」「贅沢な時間とは必要のない余白を持て余すこと」といった一節には、日常の小さな幸福を掬い上げるような哲学が宿ります。

本を“そばにいてくれる他人”と表現する彼女のまなざしは、孤独な時間を抱える多くの人の心に寄り添うと言えます。
特に「京都」の章では、鴨川で友人と過ごした日々や祇園祭、古本市の思い出など、青春の光景が鮮やかに蘇ります。
読書という行為が単なる趣味ではなく、人生そのものを形づくる営みであることが、本書全体から静かに伝わってくる。読むたびに、自分の中の“本を読む理由”を思い出させてくれる一冊だといえます。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
9位『副作用あります!? 人生おたすけ処方本』
『副作用あります!?人生おたすけ処方本』(三宅香帆著、幻冬舎刊)は、落ち込んだり悩んだりしたときに“心に効く一冊”を処方してくれる、まるで本の薬局のようなエッセイ集です。
著者は書評家・文筆家として知られる三宅香帆氏。京都大学大学院出身で、数多くの名著紹介で知られる彼女が、「怒られた日」「仕事に行きたくない朝」「死にたい夜」など、人生のあらゆる場面に合わせて“本の薬”を差し出します。

構成は「対症療法編」「予防編」「変身編」「滋養強壮編」の4部から成り、豊島ミホ、さくらももこ、司馬遼太郎、よしながふみなど、多彩な作家の作品が登場。読者の心をやさしく癒します。
文体は軽やかで親しみやすく、難解な本の紹介もスッと読めるのが魅力。友人が「この本、効くよ」と語りかけてくるような距離感です。
読者からは「小説を通して異性や他世代の視点に立てる」「同じ本でも読む時期によって響き方が違う」など、 “読書の効能”を再発見したとの声が多く寄せられています。
一方で、「その状況でその本!?」と突っ込みたくなる選書もあり、著者の感性にクスリと笑える場面も。読書を薬にたとえるユーモアと、真摯に本と向き合う姿勢が同居した一冊で、「読むことで自分を取り戻せる」ことを改めて教えてくれます。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
10位『妄想とツッコミでよむ万葉集』
三宅香帆著『妄想とツッコミでよむ万葉集』(絵:相澤いくえ/大和書房・だいわ文庫)は、古典を「真面目に遊ぶ」一冊です。
1300年前の歌を題材に、著者が妄想を広げながら現代的なツッコミを入れるという独自の手法で、万葉集の世界を軽やかに再解釈しています。
登場するのは、わるい彼氏を心配する母親、権力者を翻弄する若い女性、繊細な男性歌人など、どこか現代人と重なる人物たち。古典文学の中に、人間の普遍的な恋や悩み、ユーモアが息づいていることを教えてくれます。

本書の魅力は、専門書的な難しさを排し、インターネット文体の親しみやすさで描かれること。関西弁風の軽快な意訳や、ラノベ的な比喩、さらには「おじさんLINE」などの現代語ネタが満載で、「古典=堅苦しい」というイメージを見事に裏切ります。
読者からは「笑いながら読める万葉集入門」「難しい古典をこんなにカジュアルに紹介できるのはすごい」と高評価。特に、柿本人麻呂や大伴旅人といった歌人をキャラクターとして描き出す手腕や、「キラキラネームの歴史性」にまで踏み込む独自の視点が新鮮だと評されています。
万葉集を「遠い古典」ではなく、「人間臭くて愛しい物語」として感じさせてくれる――そんな新しい古典の入り口となる一冊です。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
まずはどれから?テーマ別の“最初の1冊”
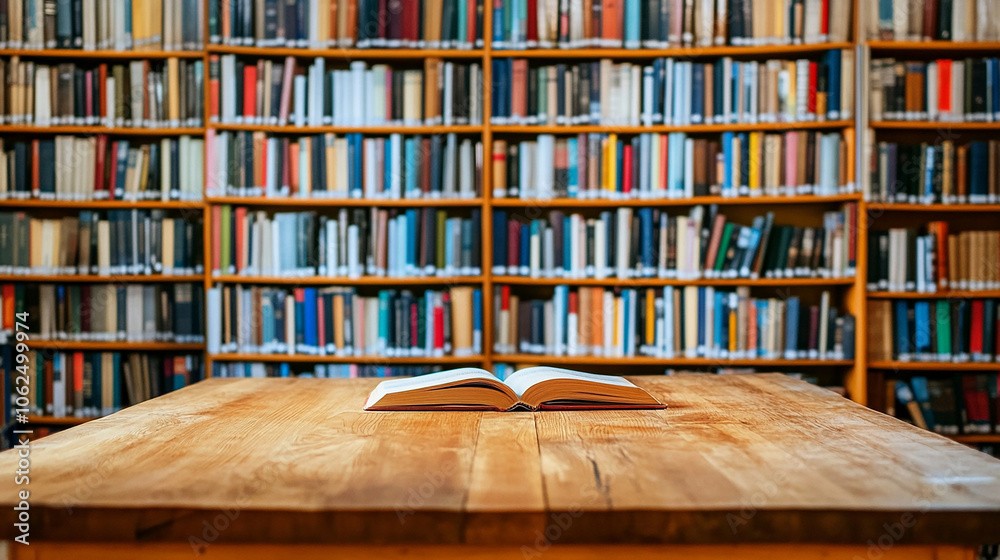
三宅香帆さんの著作は、読書論から文章術、推し文化、古典まで幅広くカバーしています。
どの一冊から手に取るか迷う人のために、テーマ別におすすめの“最初の1冊”を紹介します。
あなたの「今の気分」に合わせて、最適な入口を見つけてください。
📖 読み方のヒント
- 「★★☆☆☆」=新書・実用書として読みやすいレベル
- 「約2〜3時間」=1〜2夜で読了できるボリューム
- 気分別に選ぶなら、思考=1位/感情=2位/行動=3位 の順で読むと理解が深まります。
| 書名 | 主なテーマ | 難易度 | 読了時間(目安) | 読後の気分・印象 |
|---|---|---|---|---|
| なぜ働いていると本が読めなくなるのか(集英社新書) | 労働・読書・時間・資本主義 | ★★☆☆☆ | 約4時間 | 思考が整理され、読書意欲がよみがえる |
| 「好き」を言語化する技術(ディスカヴァー携書) | 推し活・感情・言葉・創作 | ★☆☆☆☆ | 約2.5時間 | 感情を伝える勇気が湧く、前向きな気分 |
| 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか(新潮新書) | 会話・知識・発想・思考術 | ★★☆☆☆ | 約3時間 | 話したくなる知識が増えてポジティブに |
| 人生を狂わす名著50(ライツ社) | 名著案内・思想・人生観 | ★★★☆☆ | 約5時間 | 読書リストが増え、知的好奇心が刺激される |
| 文芸オタクの私が教える バズる文章教室(サンクチュアリ出版) | 文章術・構成力・表現 | ★★☆☆☆ | 約3時間 | 書きたくなる衝動が湧く実践的読後感 |
| 〈読んだふりしたけど〉あの名作小説を面白く読む方法(笠間書院) | 古典文学・読解・教養 | ★★☆☆☆ | 約4時間 | 難解な作品が身近に感じられ楽しくなる |
| 名場面でわかる 刺さる小説の技術(中央公論新社) | 創作論・構成・心理描写 | ★★★☆☆ | 約4時間 | 物語を“分析的に楽しむ”目が育つ |
| それを読むたび思い出す(青土社) | 読書遍歴・人生・エッセイ | ★★☆☆☆ | 約3時間 | 静かな余韻が残り、自分の記憶をたどりたくなる |
| 副作用あります!? 人生おたすけ処方本(幻冬舎) | 心の癒やし・読書療法 | ★☆☆☆☆ | 約2時間 | 心が軽くなり、明日が少し楽しみになる |
| 妄想とツッコミでよむ万葉集(だいわ文庫) | 古典・ユーモア・恋愛・人間味 | ★☆☆☆☆ | 約2時間 | クスッと笑えて古典が好きになる軽快な読後感 |

三宅香帆さんの本は、どれも「自分と向き合う読書」をテーマにしています。
一気に読むより、気になる章だけ拾い読みするのがおすすめだよ。

朝の通勤時間に読むなら『好きと言語化する技術』、
休日にじっくり考えたいなら『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』。
感情を動かしたい日は『副作用あります!?』を開いてみてください。
その日の気分で選ぶことで、読書が“生活のリズム”になります。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
まとめ
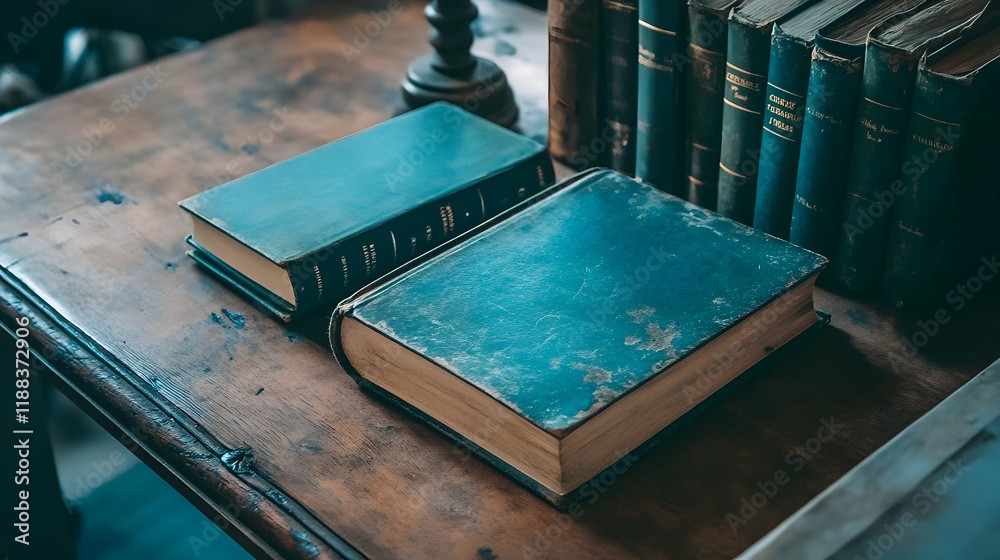
三宅香帆さんの本は、単なる「読書案内」ではありません。そこには、読むことを通じて自分と世界をつなぎ直すための“思考の灯”があります。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で社会の構造を見つめ、『「好き」を言語化する技術』で感情を言葉に変え、『話が面白い人は何をどう読んでいるのか』で知識を会話に転換する──どの一冊も、現代を生きる私たちの心をやわらかく刺激します。

読むことは、競争でも義務でもなく、「自分を取り戻す時間」。難しく考えず、気になるタイトルから手に取ってみてください。きっとそこには、忘れていた“読む喜び”が待っています。

電子書籍として、『紀伊国屋書店』さんでもダウンロード可能となっています。気にあるタイトルからチェックしてみてくださいね♬
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
【関連記事:チームリーダー・発信者必見!『好きを言語化する技術』+コミュニケーション検定で伝える力を高める】
【関連記事:「読書の効用とは?人生を変える効果とおすすめ本15選【保存版】」】
【関連記事:【最新版】「言語化力」を鍛えるおすすめ自己啓発本10選|思考を整理し、伝える力を磨く】
“PR:アフリエイト広告を利用しています”