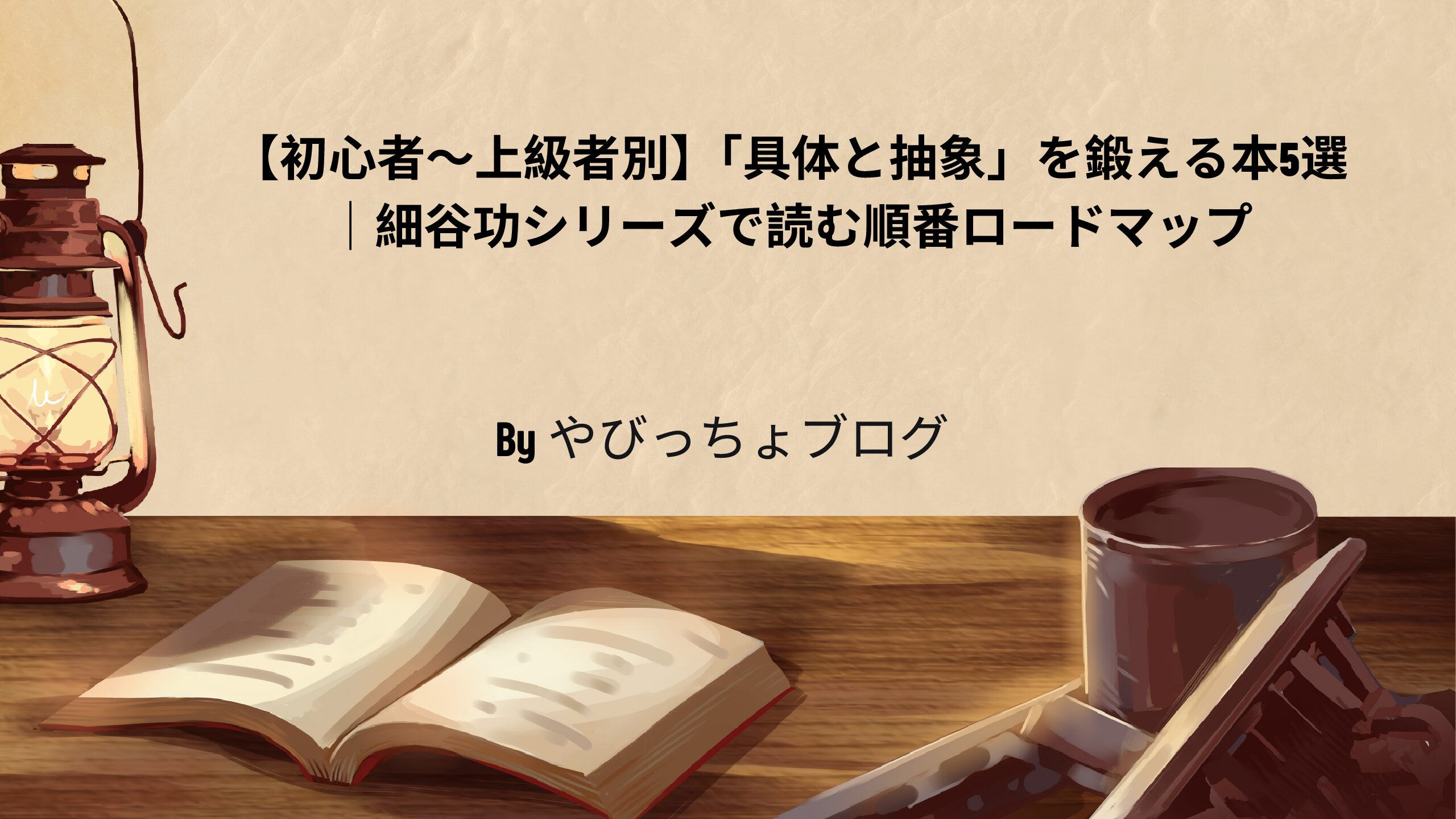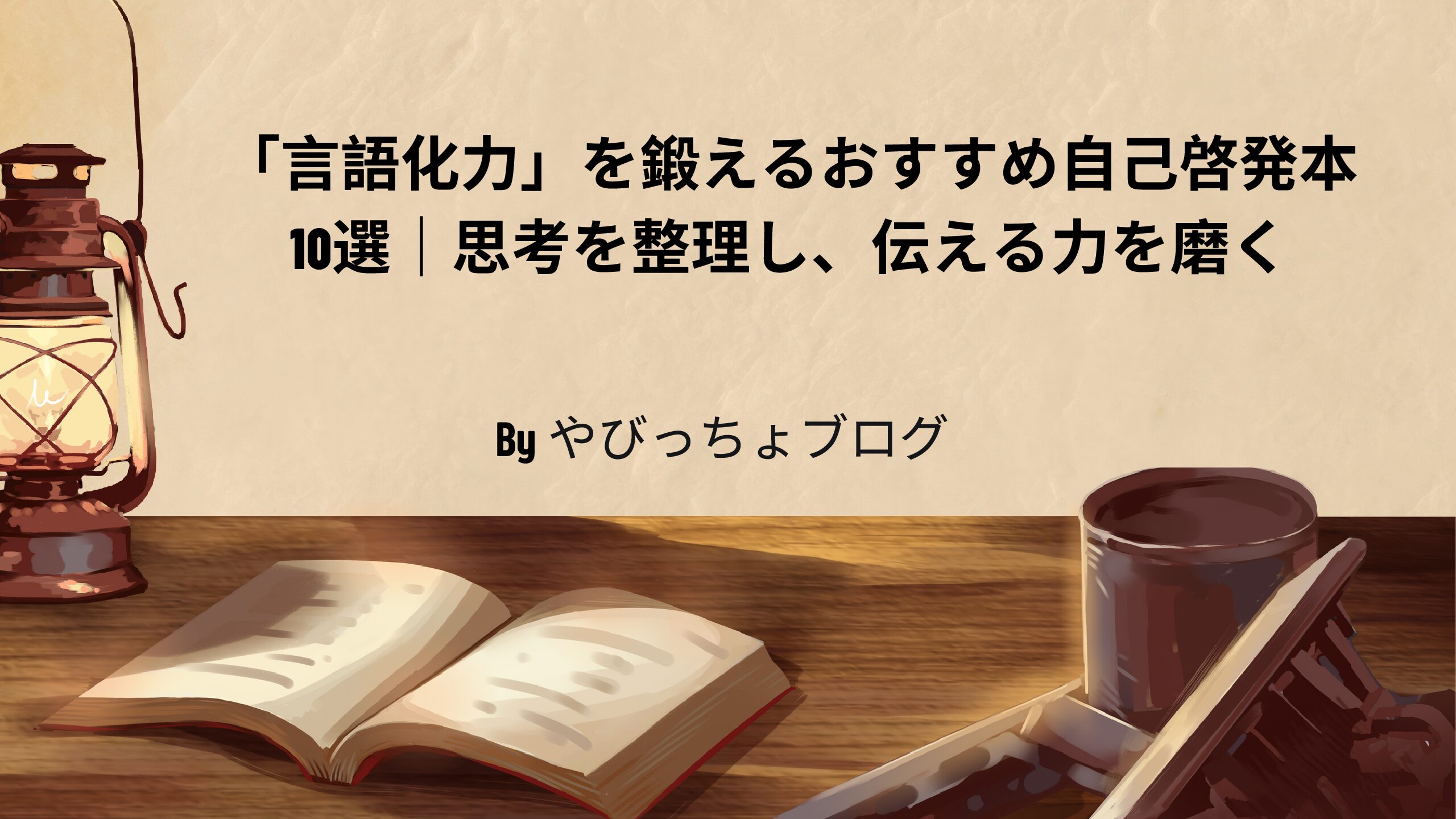「頭ではわかっているのに、うまく説明できない…」
「話が抽象的すぎて相手に伝わらない」
など、日常や仕事でのコミュニケーションで困ったことはありませんか?そんな悩みを解決するカギが “具体と抽象を行き来するスキル” です。
本記事では、ビジネス書で数多くのベストセラーを執筆している 細谷功さんの書籍を中心に、初心者→実践者→上級者の3段階で読むべき本を5冊に厳選。ロードマップ形式で紹介します。
この記事を読むことで、
- 具体と抽象の意味と重要性
- 本を読む順番と学び方
- 各ステージで得られるスキル
がわかります。

具体的に言わないと、相手にちゃんと伝わらないし、解釈がズレるし、結局どう動けばいいのかもわからなくなっちゃうんだ。逆に抽象的すぎると、話がわかりにくいし、実務で役立たないし、この人何を言いたいの?って信頼もされにくなるんだ。

ふーん!パパ?じゃあさ、どうやったら“具体と抽象”ってもっと上手にできるようになるの?
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
具体と抽象の関係とは?

私たちが物ごとを考えるときには、必ず「具体」と「抽象」という二つのレベルを行き来しています。
たとえば、日常のちょっとした体験や目に見える出来事は「具体」にあたります。そして、それらの出来事から共通点を見つけたり、法則や意味をまとめたりすると「抽象」にたどり着きます。
私たちは気づかないうちに「具体」と「抽象」を使い分けながら思考しています。たとえば「今日は雨が降っている」というのは具体的な事実ですが、そこから「秋は天気が変わりやすい」という一般化を導き出すと、それは抽象化された考えになります。
このように、具体と抽象は対立するものではなく、行き来しながら理解を深めるための“両輪”なのです。

「具体」は、事例や体験、目に見えるもの。「抽象」は、本質やルール、原理というように具体と抽象を使い分けることがだいじなんだ。

パパ?「具体」と「抽象」を使い分けることで、どんな力が伸びるの?
「具体」と「抽象」をバランスよく行き来することができると、さまざまな力が伸びます。具体的に以下の3点が挙げられます。
- 説明力が上がる
- 問題解決力が高まる
- 相手に伝わりやすくなる
物事を整理して伝える力が磨かれるため、説明力が高まります。また、表面的な出来事にとらわれず本質を見抜けるため、問題解決力が向上します。
相手の理解度に合わせて表現を調整できるので、伝わりやすさが格段に増します。具体と抽象を自在に使い分けることは、思考力とコミュニケーション力を育てる鍵となるのです。
『具体と抽象』を高めるため、細谷功さんの書籍を中心に、初心者→中級者→上級者の3段階で読むべき本を5冊紹介します。ロードマップ形式で紹介します。

細谷功さんって、思考法をテーマに本を書いたり講演したりしてるコンサルタントなんだ。『地頭力を鍛える』『具体と抽象』『メタ思考トレーニング』など著書も多くて、具体と抽象を行き来する力や問題発見力をわかりやすく解説していて、ビジネスパーソンに人気なんだ。

細谷功さんの本を読んで、具体と抽象を行き来する力を伸ばしてみたいな。
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
【初心者〜上級者別】「具体と抽象」を鍛える本5選
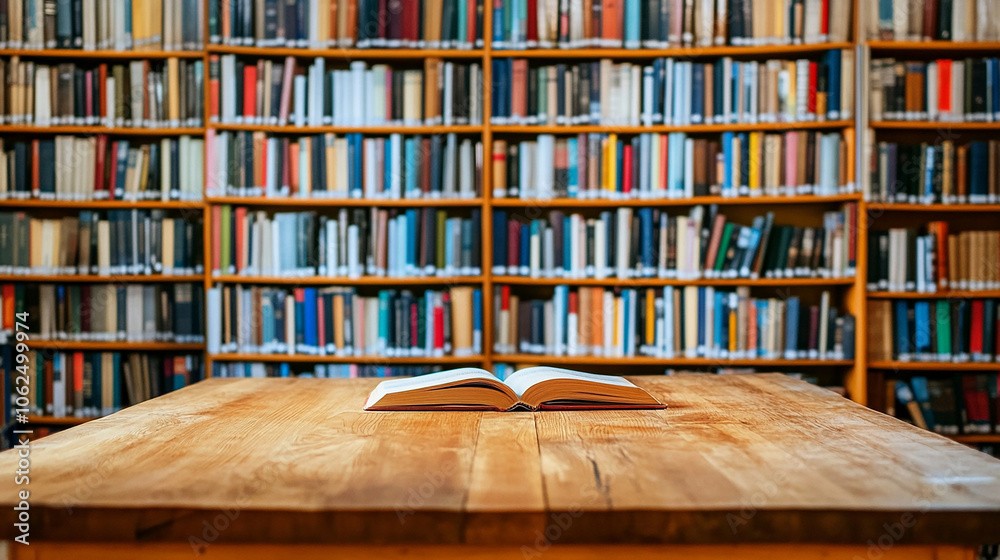
ここからは、具体と抽象のスキルを段階的に身につけられるように、「初心者 → 実践者 → 上級者」という三つのステージに分けておすすめの本を紹介していきます。
いきなり難しい内容に取り組もうとすると挫折してしまうことがありますが、レベルに合わせて順番に読むことで理解が自然に深まり、実際の仕事や日常生活でも応用しやすくなります。

まずは入門書から始めて、「具体と抽象って何なのか」をイメージしてみるところからいきましょう。そこで基本的な考え方をしっかり押さえておくのが大事なポイントです。
初心者編1冊目:『13歳から鍛える具体と抽象』
初心者編1冊目に取り上げる本は、細谷功さんの代表作『具体と抽象』を、より若い世代に向けてわかりやすく書き直したのが『13歳から鍛える具体と抽象』(東洋経済新報社、2023年9月刊)です。著者は累計100万部を超える人気ビジネス書作家であり、本書も発売直後から注目を集めています。
本書のテーマは、具体的な事例と抽象的な原理を行き来する「思考の往復運動」を鍛えること。日常の出来事を抽象化して法則を見抜いたり、逆に抽象的な原理を具体例に落とし込んだりする力を磨くことで、勉強や人間関係がスムーズになり、一生役立つ“頭の使い方”が身につくと説かれています。
読者が得られる効果は多岐にわたりますが以下の3点が挙げられます。
- 視点が広がり思考の解像度が高まること
- 複雑な情報をシンプルに整理できること
- AIに振り回されず使いこなす力を育てられること
こうしたスキルは現代を生き抜くうえで欠かせません。
また本書は「なぜ話がかみ合わないのか?」「数学でxやyを使う理由は?」「お金の目的は?」など、子どもにも身近な問いを切り口にして解説しているところも特徴です。
- 第1章では数や言葉、お金といった抽象概念の役割
- 第2章では読書による具体と抽象の繰り返し
- 第3章では勉強への応用
- 第4章ではコミュニケーションの改善
- 第5章では使い方の注意点をまとめています。

最終的にこの本で目指してるのは、「具体と抽象」を自由に使いこなして、自分の考えや行動の幅を広げられるようになることなんだ。大人にとっても入門書としてすごく読みやすいし、子どもから社会人まで幅広くおすすめできる一冊だよ。

パパ!とても難しそうな内容なのに、子どもでも読めるってすごいね~
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
初心者編2冊目:『具体と抽象―世界が変わって見える知性のしくみ』
初心者編2冊目は、『具体と抽象―世界が変わって見える知性のしくみ』(dZERO刊、2016年)です。本書は抽象と具体という人間特有の知的活動をテーマにした一冊です。
本書は、四コマ漫画を手がけた漫画家・一秒さんとの共著となっており、理論とユーモアが融合した構成になっています。
本書の核心は、私たちが日常的に陥る「議論のすれ違い」や「人間関係の衝突」の背景にある、具体と抽象の扱いのズレを明らかにすることです。
- 「具体」はわかりやすさを与えますが、ときに思考を狭める側面もあります。
- 「抽象」は知性の源泉ですが、曖昧すぎると相手に伝わらない危険もあります。
本書は、この二つを行き来する往復運動こそが知性を支え、問題解決や整理力を高めるカギであると強調しています。
内容は「抽象化なくして生きられない」「法則とパターン認識」「往復運動の意義」など多彩なテーマを扱い、抽象と具体の関係をピラミッド構造で示すなど視覚的にもわかりやすく解説。
さらに、会議や戦略立案でのコミュニケーションギャップを「抽象度を合わせる」という発想で解消する方法も提示されます。

読者さんの感想でもね、「具体と抽象を一緒に使えるようになるのが大事だった!」とか「時代が変わるときには抽象度を高めなきゃダメなんだな〜」って声がいっぱいあるんだよ。だからこの本読むと、世界を理解するためのメガネみたいに、具体と抽象を自由に使えることの大切さがわかるんだよね。

初級編で「具体と抽象ってこういうことか」って理解できたら、次はその力を実際に日常とか仕事で使えるように鍛えていきましょう。次に紹介する「中級編:おすすめ2冊」は、具体と抽象を行ったり来たりする感覚をトレーニングしながら、相手にもっとわかりやすく伝える技術まで学べる内容になってます!
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
中級者編1冊目:『「具体⇔抽象」トレーニング―思考力が飛躍的にアップする29問』
中級者編1冊目は、「具体と抽象」を実践的に鍛えられるよう構成した『「具体⇔抽象」トレーニング―思考力が飛躍的にアップする29問』(PHP研究所、2020年)です。
本書は新書判283ページのトレーニングブックで、理解だけにとどまらず「手を動かしながら考える」ことに重点を置いています。
最大の特徴は、抽象化と具体化を行き来する「具体⇔抽象」の思考回路を鍛えるために、29問の演習問題が収録されている点です。
読者は問題を解くプロセスを通じて、自然にこの思考パターンを身につけられるよう工夫されています。
具体と抽象を自在に往復する力を得ることで、思考力の飛躍的な向上、新しい発想力の育成、コミュニケーション・ギャップの解消、さらには「自分の頭で考える力」を磨くことができると説かれています。

この本ね、具体とか抽象の基本から、仕事や毎日のことにどう使うかまで教えてくれるんだよ!「ピラミッド」とかたとえ話の使い方もあって、ほんと頭のトレーニングジムみたい。本読んでるだけで自然に考えを整理する力がついちゃうんだよね〜。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
中級者編2冊目:『有と無―見え方の違いで対立する二つの世界観』
中級者編2冊に取り上げるのが、2024年6月に発表した『有と無―見え方の違いで対立する二つの世界観』(dZERO)です。
本書のテーマは、私たちの「ものの見方」に潜む二つの思考パターン――「ある型」と「ない型」に光を当てることにあります。
「ある型」思考とは、多くの人が自然に持つ「存在するもの」「目に見えるもの」に注目する考え方。一方、「ない型」思考は「存在しないもの」「まだ見えていないもの」にも意識を向ける少数派の思考法です。
著者は、この二つの思考が生み出すギャップや認知の歪みこそが、社会を動かす原動力になっていると説きます。
対立構造として、二つの思考が生み出すギャップや認知の歪みは以下の内容が挙げられます。
- 「答えがある/答えがない」
- 「問題解決/問題発見」
- 「カイゼン/イノベーション」
- 「レッドオーシャン/ブルーオーシャン」
対立する概念を「有と無」の軸で捉え直す構成。さらに「具体と抽象」「自分と他人」「部分と全体」といったテーマまで掘り下げ、普段意識しない思考の偏りを明らかにします。

レビューでは、「あるもの」ばかり見ないで「ないもの」にも目を向けると視野が広がって行き詰まりを突破できるって高く評価されているんだ。特に時代の変わり目には「ない型」の発想が大事で、無限の可能性を見抜く力は器の大きさにもつながるんだ。

正反対の考え方を、 “あるものとないもの”っていう見方で考え直してみるって難しいねぇ~。上級者はどんな本が飛び出してくるんだろう?
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
上級者編:『地頭力を鍛える―問題解決に活かす「フェルミ推定」』
上級者編として取り上げる1冊は、細谷功さんの代表作『地頭力を鍛える―問題解決に活かす「フェルミ推定」』(東洋経済新報社、2007年)です。コンサルティング業界で重視される“考える力”に光を当てた一冊です。
本書のテーマは、インターネットに依存しがちな現代社会で失われつつある「自分の頭で考える力」、すなわち地頭力の重要性を説くことです。
地頭力とは、膨大な情報の中から本質を見抜き、付加価値を生み出す力であり、PCやAIでは代替できない人間固有の能力と位置づけられています。
細谷氏は、地頭力を構成する三つの思考力を示します。
- 「結論から考える」仮説思考力
- 「全体から考える」フレームワーク思考力
- 「単純に考える」抽象化思考力
これらに論理思考力や直観力、知的好奇心が加わることで、地頭力は三層構造として理解できます。

この本の大きな特徴はね、地頭力を鍛える方法として「フェルミ推定」を取り上げてるところなんだ。たとえば「日本に電柱って何本あるんだろう?」みたいな、一見ムリそうな問いに対しても、常識とかロジックを使ってざっくり計算してみるの。やってみると具体と抽象を行ったり来たりする力とか、精度を見極める感覚、知識の幅まで広げられる効果があるんだよ。

パパ…ちょっとナニ言っているのかわからないんだけど。
章構成も「地頭力とは何か」から始まり、「フェルミ推定の定義」「鍛え方」「ビジネス応用」へと展開。仮説思考、フレームワーク思考、抽象化思考の個別解説に加え、さらに地頭力を伸ばす方法まで網羅的に解説しています。
知識を単に詰め込むのではなく、自分の頭で考える力を鍛えたい人にとって、本書は上級者として読んで欲しい一冊といえるでしょう。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
まとめ|「具体と抽象」を鍛えて思考力をレベルアップしよう

私たちの思考やコミュニケーションの土台には、常に「具体」と「抽象」があります。この二つを自在に行き来できるようになることで、説明力が高まり、思考力が深まり、そして問題解決力を飛躍的に伸ばすことができます。まさにビジネスでも日常生活でも役立つ“万能スキル”といえるでしょう。
今回ご紹介した細谷功さんのシリーズ5冊は、「初心者 → 中級者 → 上級者」という段階を踏むことで無理なく力を育てられるロードマップになっています。
入門では「具体と抽象とは何か」を理解し、次にトレーニングや対立する2つの概念を組み合わせる力を高めて実践力を磨き、最後により高度な思考法で上級レベルへとステップアップしていく構成になりました。
大切なのは、ただ読むだけで終わらせないこと。本の内容を自分の言葉で要約したり、具体例に落とし込んで説明したり、日常のアウトプットに活かすことが実力を伸ばす近道です。

まずは『13歳から鍛える具体と抽象』を読んでみよっと。そこから「具体と抽象」を自由に使える考える力を育てていけば、毎日の会話とか勉強にも新しい発見が出てくるはず。そしたらね、きっと世界の見え方がガラッと変わっちゃうんだろうな〜!

今回、紀伊国屋書店のサイト記事を参考に記事を書いてきました。紹介した書籍について、興味があれば一度、本を手に取って読まれることをお勧めします。紀伊國屋書店ウェブストアから電子書籍も購入可能ですのでチェックしてみて下さいね。
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
【関連記事:1日3分で頭のモヤモヤを整理する!荒木俊哉『こうやって頭のなかを言語化する。』レビュー】
【関連記事:【最新版】「言語化力」を鍛えるおすすめ自己啓発本10選|思考を整理し、伝える力を磨く】
【関連記事:【2025年最新版】思想家・内田樹のおすすめ本10選|名著・人気ランキングと読み方ガイド】
“PR:アフリエイト広告を利用しています”