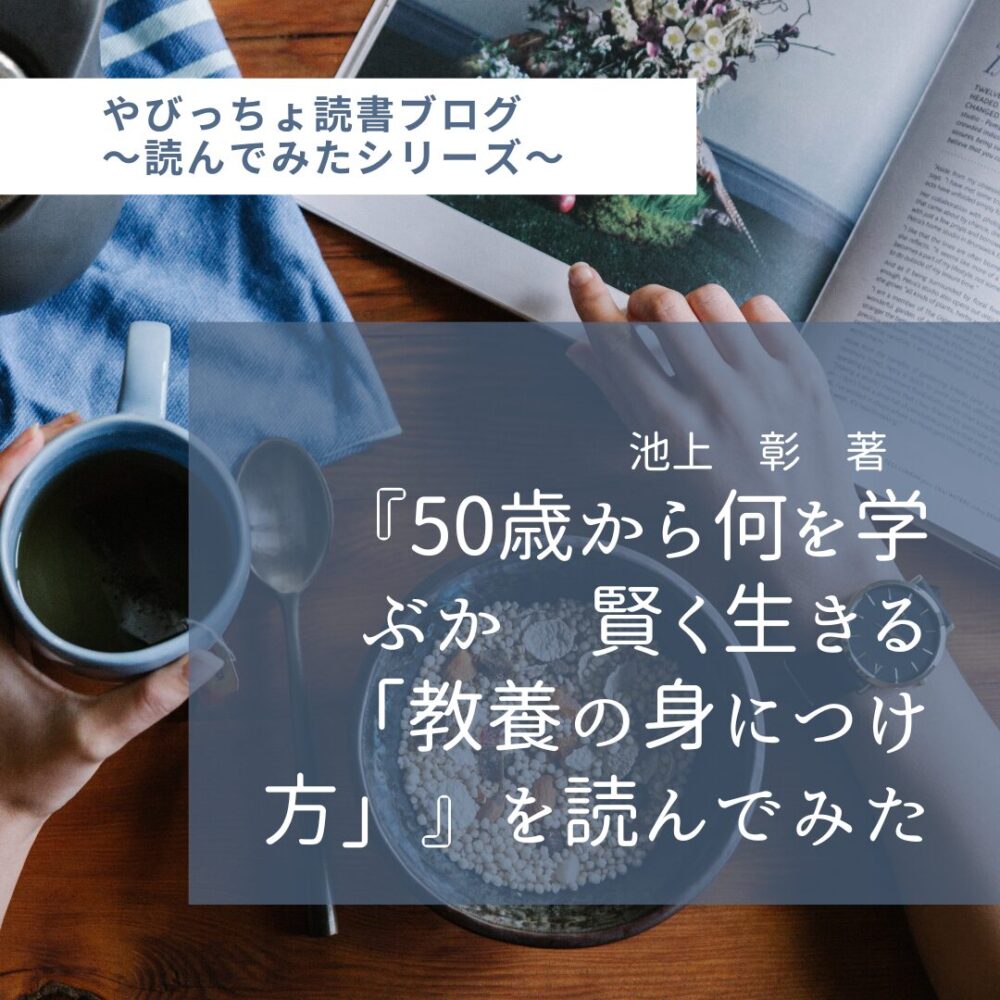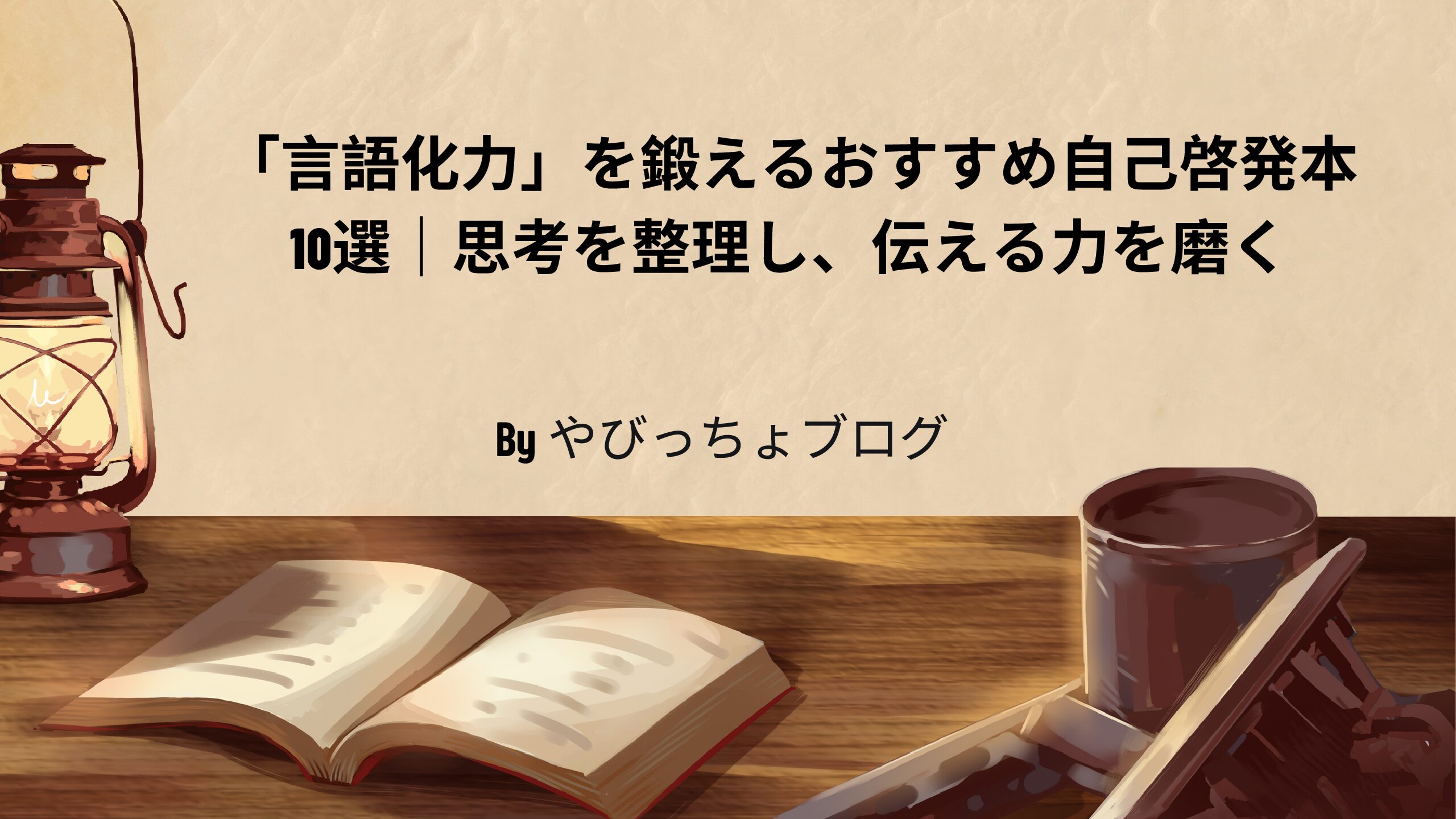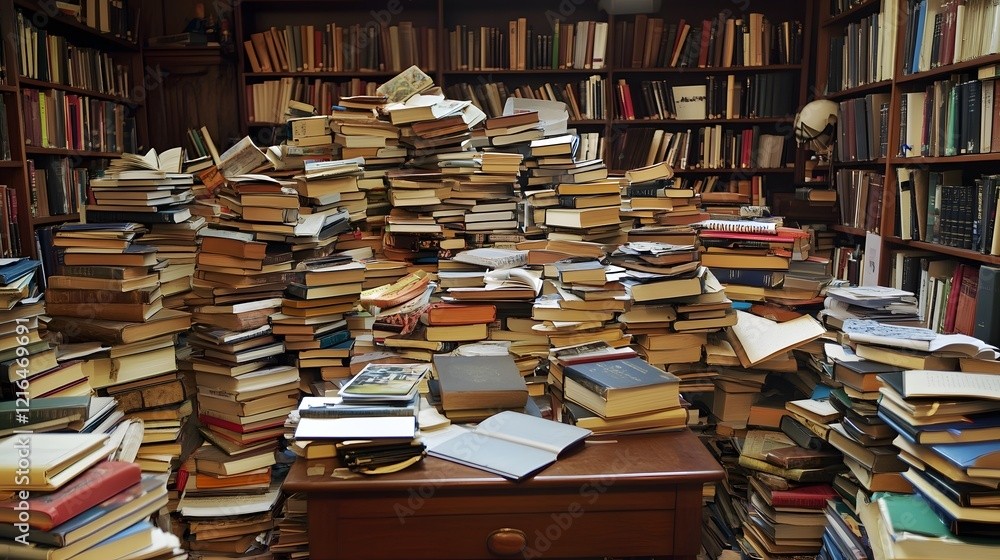
「もう50歳を過ぎたから、新しいことを学んでも遅いのでは?」――そんな気持ちを抱いたことはありませんか。
キャリアや家庭で大きな役割を果たしてきた私たち世代は、ふと立ち止まったときに「これからの時間をどう生きるか」という問いに直面します。
そんなときに出会いたいのが、ジャーナリスト池上彰さんの著書『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』です。
40年、50年と人生を歩んでくると、どうしても「自分なりの生き方のクセ」が表れてきます。そのクセの一つが、視野が狭くなり、偏見や思い込みにとらわれてしまう「視野狭窄」です。
若い頃は柔軟だった思考も、年齢を重ねるにつれて価値観が固定化し、とある思い込みから気づかぬうちに周囲との距離を生んでしまうことがあります。

本記事では、「中年期に学ぶ教養論」を一つの視点として取り上げたいと思うんだ。教養って、ただ知識を増やすってことじゃなくて、自分を客観的に見られる“鏡”みたいな役割を持つんだ。要するにさ、「老害」にならないための視点をちゃんと養って、人間ってものをもっと深く理解できる力になるってことなんだよ。

パパたちが、いっぱい体験してきたこととか知ってることを、そのままにするんじゃなくて、「教養」っていうふしぎなめがねをとおして見てみると、すごい宝物になるんだね~。大人になってからの毎日を、もっと楽しくてゆたかにするヒントになりそうだね♬
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
なぜ“今”教養を学ぶのか?中年期だからこそ考える理由
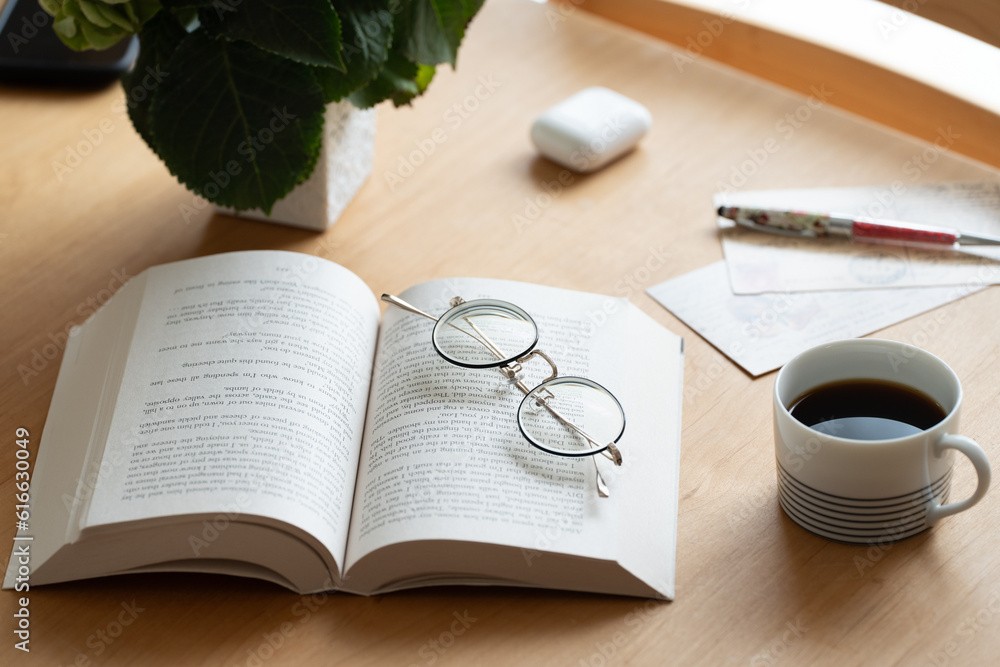
40代から50代にかけて多くの人が直面する「中年危機(ミッドライフ・クライシス)」という言葉も広く知られるようになりました。
「中年危機(ミッドライフ・クライシス)」とは、これまで積み重ねてきたキャリアや生活の基盤が一見安定していても、「自分の人生はこのままで良いのか」「残された時間で何をすべきか」というあせりや虚しさが押し寄せてくる心理的不安を表した言葉です。
若さの勢いに任せられた時代とは異なり、体力や気力の衰えを実感し、同時に社会的役割の変化に直面する中年期は、心の揺らぎが大きくなる時期でもあります。そんな時こそ必要なのが「教養」です。
歴史や哲学、古典に触れることで、人間存在の普遍性を学び、自分の悩みを相対化できる。それは、人生の後半を支える精神的な土台となり、不安を和らげる大切な支えとなるのです。

教養ってさ、ただ知識をいっぱい集めることじゃないんだよね。むしろ、自分を客観的に見つめ直したり、もっと広い視野で社会とか人間を理解するための力なんだ。池上彰さんの『50歳から何を学ぶか』って本は、その具体的な方法とか意義をすごくわかりやすく教えてくれてるんだよ。
教養が中年期の精神的な支えになる
著者の池上彰さんだけでなく、多くの教養書に共通して語られているのは、「教養はすぐに身につくものではない」という点です。いわば「コスパが悪い学び」の代表とも言えます。
本書『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』では、「なぜ、教養が必要なのか」と言う理由にしっかりと答えが示されています。
確かに教養はすぐには役に立たないものです。多くは無駄になるものです。身につけたものがすぐに出世や収入増につながることはまずありません。
一方で、教養は最強の武器でもあります。特に現在のように、技術や社会が凄まじいスピードで変化して行く時代、目先の情報を追うのではなく、教養を身につけることが結果的に現代社会における問いを見つける手助けになるからです。
つまり、実学や専門バカの限界を知ったからこそ、あらためて教養にスポットライトが当たっているのではないでしょうか。
引用:『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』18ページより
池上さんは、「すぐに役立つ実学の限界」を知ったからこそ、教養の重要性が見えてくるのだと語ります。言い換えれば、仕事や生活の中で実学を使い尽くした世代だからこそ、教養を深める資質を備えている、ということです。

たとえばコロナ禍のときのことを思い出してみてほしいんだ。テレビからは毎日のようにいろんなニュースが流れて、真偽の分からない情報もSNSに溢れてたよね。本当に意見がバラバラで混乱したと思うんだ。答えがハッキリ出ない問いに対して、「自分や家族の健康をどう守るか?」っていう答えは、実学からは絶対に教えてもらえないんだ。

みんな言ってることがちがってて、どれがほんとかわからなかったもん。だから自分でちゃんと考えなきゃいけないんだね。先生が教えてくれる勉強だけじゃなくて、 “じぶんのあたまで考える力”が大事なんだって思ったよ。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
ファスト教養の弊害とは
近年、「教養」を求めるあまり、手軽に身につけようとする動きが広がり、「ファスト教養」という言葉まで登場しました。
ファスト教養とは、端的に言えば「物ごとを手っ取り早く理解し、ビジネスの場で上手く立ち回ることで、成果や収入につなげる」という考え方です。
池上彰さんの本では、この「ファスト教養」には警鐘が鳴らされています。なぜなら、教養とは本来、即効性とは無縁のものだからです。
「人間とは何か?」「世界はどのように成り立っているのか?」「歴史から私たちは何を学ぶのか?」――こうした根源的な問いに向き合い、人類が積み重ねてきた英知を受け継ぐ作業こそが、教養の本質なのです。

社会に出たばっかりの若いおにいさんやおねえさんが、「早くおしごとで成果を出したい!」とか「少しでもおこづかいみたいにお金をふやしたい!」って思う気持ち、わたしもなんとなくわかるな。そのがんばりたい気持ちってすごくたいせつだよね♪
「リスキリング(学び直し)」と教養の違いについて
昨今、デジタル化やICTの活用が進む中で、「リスキニング」の必要性が盛んに語られています。リスキニングとは、直訳すると「学び直し」を指し、時代の変化に合わせて新しいスキルを習得する取り組みです。
仕事に直結するスキルを学び直すことはキャリアを維持・発展させるうえで欠かせません。しかし、これは「教養」とは異なります。
リスキニングは実務で成果を出すための手段であり、即効性を求める学びです。一方で、教養とは人間や社会を広く深く理解するための土台であり、すぐに役立つものではありません。つまり、リスキニングは重要ではあるものの、教養とは別物として捉える必要があるのです。
「リスキリング(Reskilling)」とは、職業能力の再開発、再教育のことを意味します。近年では、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略において、新たに必要となる業務・職種に順応できるように、従業員がスキルや知識を再習得するという意味で使われることが増えています。
引用記事:リスキリングとは――意味やリカレント教育との違い、DX実現に向けた導入時のポイントや事例を紹介 – 『日本の人事部』

特に中年にとってさ、デジタル化とかICTの活用ってほんと頭が痛い問題なんだよね。昔はアナログで普通にやってた仕事が、デジタル化のおかげで効率よく片づけられてるのを見ると、「あれ、もしかして私って必要ないんじゃないか?」って、思い知らされるんだよ。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
教養を“自分ごと”にする方法3選
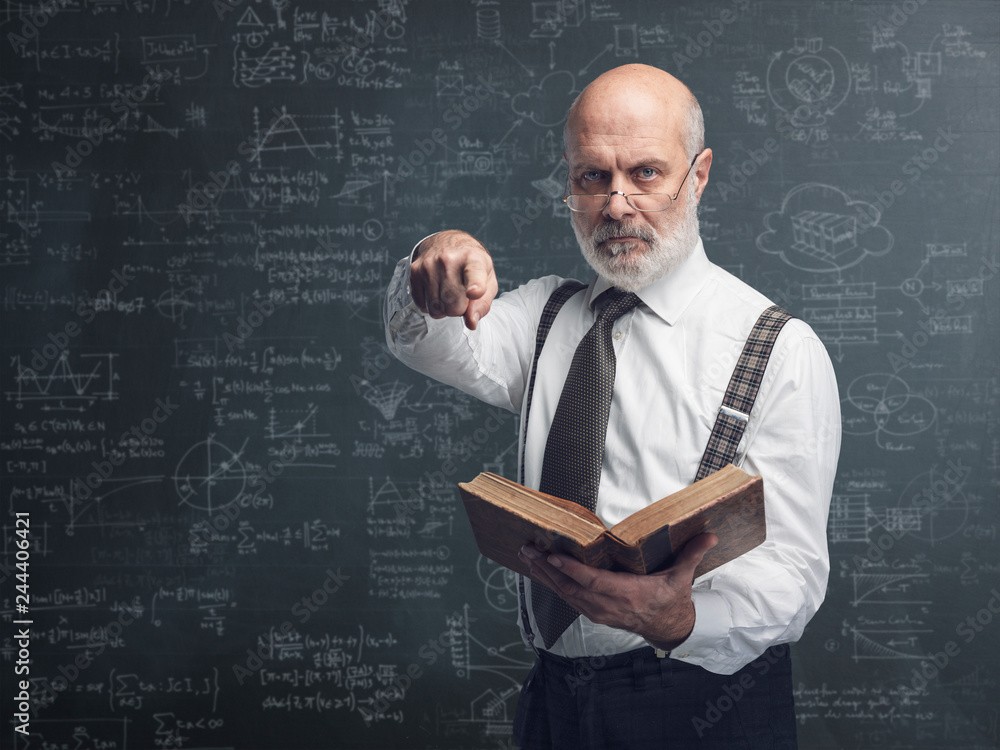
教養という言葉を聞くと、どうしても「難しい本を読むこと」や「特別な知識を持つこと」をイメージしがちです。
本来の教養とは、私たちの日常と切り離された遠い存在ではなく、むしろ“自分ごと”として考えることで初めて身につくものです。
気になるニュースを深掘りしてみる、本屋で手に取った一冊をきっかけに新しい分野へ関心を広げる、あるいは友人との会話から「なぜ?」と問いを立てて調べてみる。
こうした小さな習慣が、教養を知識の積み重ねに終わらせず、自分の考え方や生き方を形づくる力へと変えていきます。
次に、「教養を“自分ごと”にする方法」として3つ挙げてみたいと思います。

教養を身につける最初の一歩ってさ、やっぱり「読書」なんだよね。ネットでポチッと本を買うんじゃなくて、ちゃんと書店に行って本棚を眺めることから始まるんだと思うんだ。

最近は「みんな本をあんまり読まなくなった」って言われてるけど、わたしもYouTubeとかまとめみたいなのですぐに調べちゃうんだよね。一度は本屋さんにいってみて、ならんでる本をゆっくりながめて見るよ。
教養を“自分ごと”にする方法①:「ヤバい」で感情を表現するクセを止める
近年、若い人たちの間で流行している「ヤバい」という言葉。もともとネガティブな響きが強かったはずですが、いまや「すごく良い」という意味でも使われるようになりました。
「中年期を迎えた大人がそんな言葉を使うなんて」と説教するつもりはありません。気をつけたいのは「ヤバい」という便利な言葉に慣れてしまうことの怖さです。
本来なら「嬉しい」「驚いた」「感動した」といったさまざまな感情の表現を、すべて「ヤバい」で片づけてしまうと、心の機微が伝わらなくなってしまいます。
状況に応じて適切な言葉を選び、自分の思いを丁寧に表現することは、脳の活性化にもつながります。さらに、自分の感情を具体的に言葉にすることは、言い換えれば「自己認識を深めるための有効なトレーニング」です。
つまり語彙力は、相手に伝えるだけではなく、自分自身を理解するための大切な道具でもあるのです。
(前略)自分の感情を豊かな語彙を使って表現できる人は、自分の感情を明確に捉えられない人に比べ、言葉の暴力や腕力を振るうことが40%少ないとのこと。
表現豊かに自身の気持ちを言語化できる人ほど、感情的にならずにストレスを回避することができるというわけなのです。
***
感情のラベリングは、その場での感情の抑制だけではなくて、今後同じような状況になったときも衝動的な行動を起こさないための、ストレス体制の強化にもなります。感情に振り回されずに、冷静に自分の感情を見つめる習慣を身に付けていきましょう。
引用記事:ストレス対策はやっぱり「言語化」が最強だった。“自分のキモチ” を言葉にできますか? – STUDY HACKER(スタディーハッカー)|社会人の勉強法&英語学習
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
教養を“自分ごと”にする方法②:間違いを指摘してもらえないことを自覚する
上司や先輩と呼ばれる立場になる「中年期」には、もう一つ大きな難しさがあります。それは「間違いを指摘してもらえなくなる」ということです。
「えっ、ミスをしても怒られないならラッキーじゃないか」と思うかもしれませんが、それは大きな勘違い。「言われるうちが華」という言葉があるように、周囲がわざわざ指摘してくれるのは、まだ自分に期待を持ち、気にかけてくれている証拠です。
逆に「言っても聞いてくれない」「あの人に何を言っても無駄」と思われてしまったら要注意。その瞬間から一気に「老害」への道を歩み始めることになります。

「老害」って呼ばれるのは中年だけの問題じゃないんだよね。態度しだいじゃ、会社の若手だってアルバイトの先輩だって、あっという間に「老害認定」されちゃうんだ。結局のところ、周囲は年齢じゃなくて、ふだんの言動が自分の評価を決めるんだよ。
教養を“自分ごと”にする方法③:陰謀論に巻き込まれない
最近では、インターネットの普及で「何かを知りたい」と、思った時に本を参考にするのではなくてネットでググる(検索)する人が多くなったと池上さんは語ります。
ネット検索では、調べたい情報が玉成混合で画面上に出てくるため、一つ一つ情報を精査する能力が必要になると言います。
特に問題になっているのは、陰謀論や偏った情報を広める動画を信じ込んでしまうという傾向です。「誰も知らない○○」「テレビや新聞が報じない△△」といった触れ込みの動画を見て、「他の人が知らない情報を、自分は知ってしまった!」と刺激と優越感を得てしまうのです。しかも悪いことに、一度その手の動画をクリックすると、同じような動画が次々に再生されるので、導かれるように「その世界」に入り込んでしまうのです。
引用:池上彰著、『50歳から何を学ぶか~賢く生きる「教養の身につけ方」~』67ページより

パパも、YouTubeとかで陰謀論の動画をひと通り見たりしてるんだ。ああいうのって内容がけっこう面白いんだよね。今の世の中、社会や政治に鬱屈した気持ちがあったり、物価高でしんどかったりするから、全部を頭から否定する気にはならないんだ。ただやっぱり、「一回立ち止まって考えてみる」ってスタンスも大事だと思うんだよね。

わたしもね、YouTubeでいろんな「動画」を観るけれど、すべてが「ウソ!」ってきめつけられない気もするの。だからこそ、自分のあたまで考えることがだいじなんだねよね。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
さいごに|新たな学びや挑戦が人生に活力をもたらす

池上彰さんの著書『50歳から何を学ぶか 賢く生きる「教養の身につけ方」』をテキストに中年期からの教養の学びかたについて解説してきました。
年齢を重ねると、新しいことを始めるのが億劫になりがちです。しかし、「中年期からの教養」を得ることは、人生に深みと活力をもたらしてくれます。
「中年期からの教養」の醍醐味とは、これまで外に向かって積み重ねてきた「成功」や「役割」を一度手放し、「本当に自分が大切にしたいものは何か」「どんな人生が自分にとって意味があるのか」といった根本的な問いに向き合うこと。
これまでの生き方を否定するのではなく、蓄積された知恵と経験をもとに、より本質的な自分へと近づくプロセスなのです。

ここまで話してきたけど、やっぱり「教養」ってのはすぐに身につくもんじゃないし、コスパだけで語れるものでもないんだよね。でも、中年期に差しかかって不安になったり、立ち止まったりするタイミングだからこそ、じっくり向き合う価値があるんだと思うんだ。本記事を読んで、池上彰さんの著書が気になった方は、一度手に取って読まれることをお勧めします。

池上彰さんの本『50歳から何を学ぶか』は、hontoっていうお店で電子書籍でも買えるんだよ。ちゃんとhontoのページにあるから、ケータイやパソコンとかでも読めるの。しかもね、形式はEPUBってやつで、iPhoneでもAndroidでも、WindowsやMacでも読めちゃうんだ。お値段は950円(税込)だって!
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
【関連記事:─ 佐藤優とSARAスクール『40代でシフトする働き方の極意』に学ぶ人生後半戦の戦略 ─】