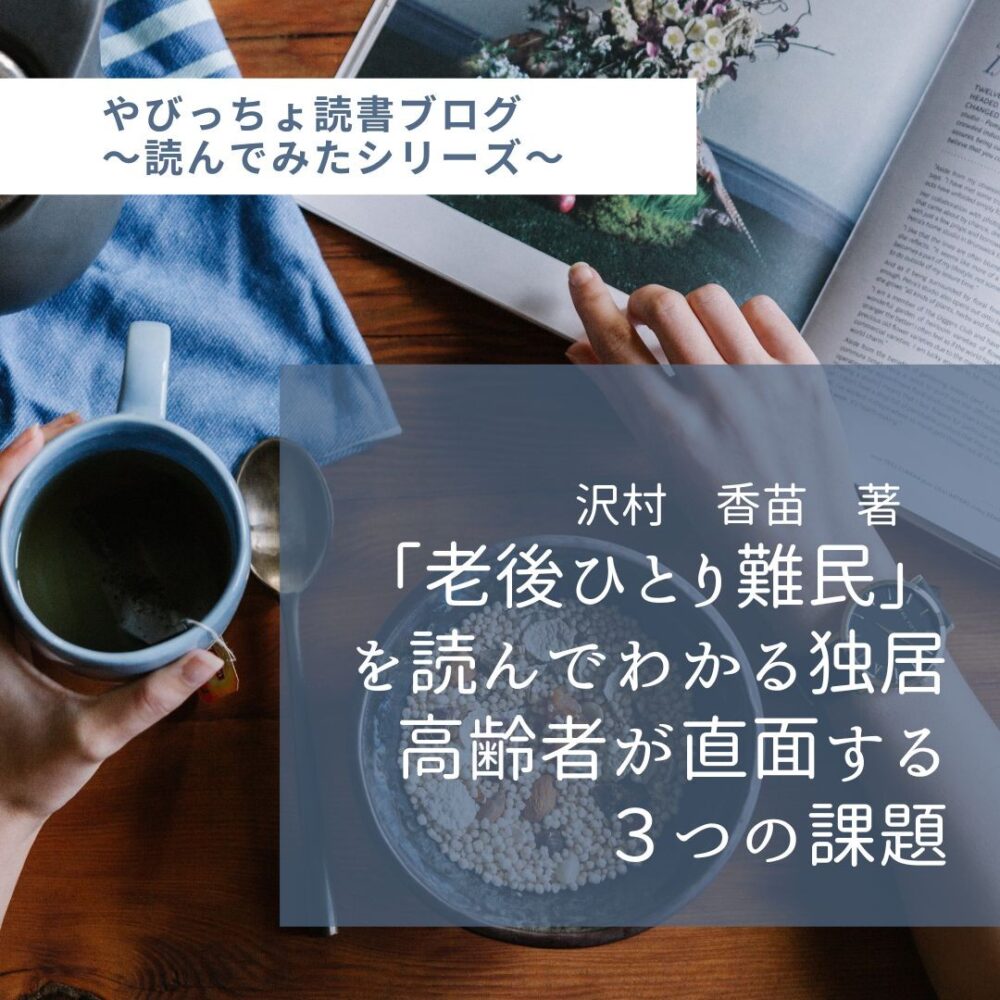近年、「老後ひとり難民」という言葉が注目を集めています。これは、親族に看取られることなく、死後の葬儀や手続きすら誰にも担ってもらえない高齢者の姿を指すものです。
結婚しない人や子どもを持たない人が増え、親との同居も減った現代では、家族や親族とのつながりが薄れています。その結果、いざという時に頼れる人がいない高齢者が急増しているのです。
背景には以下のような社会変化があります。
- 未婚率の上昇や子どもを持たない選択の増加
- 核家族化の進行による親族関係の希薄化
- 「元気なうちは人に迷惑をかけない」とする価値観の広がり
日本は世界でも有数の長寿国ですが、健康寿命を過ぎた後には転倒や病気をきっかけに生活が一変し、独りでの暮らしに限界を感じる瞬間が訪れます。
本来であれば家族が担っていた入院時の保証人や退院後の生活支援、死後の葬儀や事務手続きが宙に浮くことは、独居高齢者にとって切実な問題です。

私たちは、元気で健康に過ごせるうちに「老後」や「終活」について考え、準備しておくのが理想です。しかし現実には、「自分の死を考えたくない」「想像したこともない」という方に多く出会います。そんな現状を分かりやすく解説しているのが、沢村香苗氏の著書『老後ひとり難民』です。今回はこの本を紹介したいと思います。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
沢村香苗著書『老後ひとり難民』の概要について

沢村香苗さんの著書、『老後ひとり難民』は、日本の急速な高齢化社会における一人暮らしの高齢者たちが直面する困難や問題を描いたものです。

沢村香苗さんは、取材を通じて得た実際のケースをもとに、高齢者の生活の現実を詳しく記述しています。プロローグで『老後ひとり難民』を次のように定義します。
親族に看取ってもらえないどころか、死後の葬儀さえしてもらえないというケースは、今やまったくめずらしくなくなっています。背景には、結婚しない人、子どもを持たない人、親と同居しない人などが増え、「家族」「親族」のつながりが希薄化するなか、「いざというときに頼れる人がいない」人が増えているという現実があります。
引用:沢村香苗著、『老後ひとり難民』8~9ページより
本書『老後ひとり難民』では、社会的なサポート体制の不備や、家族との疎遠、人間関係の希薄化といった問題にも焦点を当てています。こうした問題に対する解決策や、地域社会が果たすべき役割についても論じられています。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
「老後ひとり難民」が直面する3つの課題とは

独りで老後を迎える「老後ひとり難民」は、元気なうちは実感がなくても、病気や入院をきっかけに深刻な課題に直面します。
まず一つ目は、退院後の生活や介護が「家族の支え」を前提とした制度設計の中で立ち行かなくなること。
二つ目は、入院・施設入居・賃貸契約など、あらゆる場面で必要となる「保証人」不在の問題です。
そして三つ目は、死後に残される葬儀や遺体の引き取り、賃貸解約などの手続きが宙に浮くこと。これらは誰にでも起こり得る現実であり、早めの備えと社会的な仕組みづくりが求められています。

人生をまっとうする上で「ピンピンコロリ」が理想だと言われます。高齢になっても元気で過ごし、最期には病気や介護なしに急に亡くなるという理想的な老後の生き方を指します。病気や介護なしにという想いは「人に迷惑をかけることなく」という意味が含まれていると思います。
「自分はピンピンコロリで逝きたい、死んだらそのあたりに骨をまいてくれたらいい」と潔さを強調する人もいます。ですが、「ピンピンコロリ」は選ぶことができないのです。まして、医療の発達した今の時代では、そう簡単に死ぬことはできません。
引用:沢村香苗著、『老後ひとり難民』97ページより
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
課題その①:入院~退院にかけて生活課題が浮き彫りになる

「老後ひとり難民」が直面する1つ目の課題が「入院をきっかけに生活に行きづまる」です。実際に私も、ケアマネジャーとして勤務をしていますが、入院をきっかけに介護保険を申請して欲しいと言う依頼を病院から受けることがあります。
介護保険を申請したあとに要介護(要支援)認定が降りると介護サービスが利用できます。その際にケアマネージャーが、利用者本人の困りごとや希望などを聞きながら退院に向けて一緒にケアプランを作成します。
ここで、ポイントとなるのが、「在宅に戻るにあたって介護保険サービスが必要になるような状況だ」ということがわかります。言い換えれば「周りの支援が必要になる」状況だと言えます。
ケアマネージャーが支援する上で直面する困難な条件(いわゆる困難事例)のひとつに「身寄りがいない独居高齢者(老後ひとり難民)」の支援があげられます。その理由を次に説明します。
介護保険制度の弱点とは
なぜ、「身寄りがいない独居高齢者」が困難事例になるのかポイントをあげると、一番の要因は「家族のサポート不足」があげられます。本著、「老後ひとり難民」でも、介護保険サービスについて詳しく解説されています。
押さえておきたいのは、介護保険制度スタートの際、理想の老後が「家族に看取られながら自宅で最期を迎える」ことだったという点です。
引用:沢村香苗著、『老後ひとり難民』45ページより

「介護保険サービス」を利用すれば、老後の生活は安心だと思う方もいらっしゃると思いますが、介護保険の申請を行うにも市役所の窓口で申請をしなければいけません。入院中の利用者に代わって対応する医療ソーシャルワーカーや地域包括支援センターの職員はボランティアで対応してくれているのが現状です。
※POINT:介護保険制度は家族がいると言う条件が前提として制度設計された
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
課題その②:「保証人」という重大な問題について
「老後ひとり難民」が、直面する課題2つ目のポイントが「身元保証人」の問題です。本書でも触れていますが、「身元保証人」には法的な裏付けや明確な定義はありません。
病院への入院、介護施設への入居、さらには賃貸契約に至るまで、人生のさまざまな場面で身元保証人を求められます。
身寄りのない独居高齢者にとって、頼れる家族がいないことは深刻な現実です。保証人がいなければ、治療方針の決定が難しくなったり、退院や生活再建が進まなかったりと、生活の根幹が揺らいでしまいます。

友人や知人に依頼する、行政や専門機関を活用するなど代替策はあるものの、精神的な支えを失う孤立感は解消できません。この「保証人」問題は、今後ますます高齢社会において大きな課題となっていくのです。
※POINT:身元保証人が必要になる場面について
- 病院への入院時
- 賃貸など不動産で契約をする転居時
- 施設入居時
- 介護保険サービスを始めとした契約時
上記に共通する点として、高齢期のライフステージに変化があった際に「身元保証人」が必要になります。
本著でも、「老後ひとり難民」が身元保証人を必要とする場面を述べています。今まで住み慣れていた居住スペースから移動しなければならない時に「身元保証人」が必要となるようです。
身元保証人がいないと、金銭面での未払いのリスクに直面しますし、入院先では意思疎通ができなくなった場合に治療計画が決められなかったり、死後の手続きができなくなったりします。
身体が不自由になったときに、身の回りの世話や退院時の手続きができないリスクもあります。
引用:沢村香苗著、『老後ひとり難民』85ページより
具体的な対策とは言えないのですが、入院になった時のことを考えての対策として以下のことが挙げられます。
その①:友人や同僚に保証人になって欲しいとお願いをしておく
周りの人間関係を大事にする。それに越したことはないですよね。「信頼が大きな財産」です。
その②:クレジットカード決済などで、支払方法を明確化しておく
クレジットカード決済が出来るだけでも、入院費の支払いができると信頼される担保の一つになると思います。できれば、若いうちにクレジットカードを作っておくことも対応方法のひとつです。
その③:生活費などの捻出が苦しいなら「生活保護」の受給を検討する
「生活保護」の受給要件に関しては、各地方自治体によってさまざま条件が異なります。「生活保護」を受給している場合、「医療扶助」が受けられ、自己負担が一部を除いて免除されます。

実際に、ケアマネージャーとして身寄りがいない利用者を支援しているときに病院からの求めに応じて身元保証人になったこともあります。賃貸の解約でアパートの片付けも一人で対応しました。もちろん、業務の範囲外なので無報酬で対応しなければなりませんでした。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

課題その③:「老後ひとり難民」が亡くなった後に起こる問題について
人生の最後でもある「老後ひとり難民」が亡くなった際にどのような問題が起こるのか?本書『老後ひとり難民』を参考にしながら、実体験(沖縄県の那覇市をモデルケース)を元にまとめていきます。
過去の事例で対応しましたが、独居高齢者が亡くなるときは「自宅で孤独死」が一番多いケースだと本著でもふれています。
介護事業所は、利用者の生活や健康管理に深く関わっているため、何かあった際の対応は多くの場合、介護事業所からケアマネジャーへ連絡を受けて利用者の対応にあたります。実際に連絡を受けて訪問すると、すでに利用者亡くなっている状況に立ち会うこともあります。
ケアマネージャーと利用者との契約は、ご本人が亡くなった時点で解約となります。しかし実際には、亡くなった後も事業所やケアマネージャーによる支援や手続きのサポートが続くことが少なくありません。この流れを理解しておくことで、介護現場の役割や仕組みをより正しく把握することができます。

あくまで、実体験としてお読みください。ケアマネージャーの業務の範囲を超えた対応でもありますので例外的な事例として参照ください。下記の説明に関しては、実際の自治体の対応に即してください。
※POINT:これ以降は、業務上の対応では無く、あくまでボランティアの延長としてお読みください(他のケアマネージャーに同様の対応を求めることはお控えください)。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
老後ひとり難民が亡くなったあとの流れについて

ここからは、身寄りがいない「老後ひとり難民」が亡くなられたあとの流れについて解説していきたいと思います。
- 死亡届の提出について
- 遺体の引き取りについて(火葬や埋葬まで)
- 公共料金や賃貸の解約手続き
- 病院や介護利用料などの未払いについて

利用者が亡くなったと報告を受けて訪問すると警察に通報します。ただし、突然死をのぞく、健康状態に不安を感じている利用者に対して、事前に訪問診療に繋いでいるケースが多いです。
訪問診療の先生に繋いでいるケースだと、診療所に連絡を受けて先生に訪問してもらい死亡診断書を書いてもらいます。
訪問診療と併せて訪問看護に繋いでいるケースがほとんどなので、訪問看護事業所に連絡を入れて「エンジェルケア(死後のケア)」を依頼します。
※POINT:ここでの注意点は「死亡診断書」も「エンジェルケア」も自己負担であることです。介護保険や医療保険は適用されません(生活保護の方も同様です)。
死亡届の提出について
身寄りのいない独居高齢者が自宅で亡くなった場合、死亡届を提出する義務があるのは、「賃貸の大家さん」になります。不動産に連絡を入れて死亡届の提出を大家さんに依頼します。
過去の事例で大家さんとトラブルになったこともありましたが、その方は生活保護を受給していたため、福祉事務所に相談して「福祉事務所長」名義で提出したこともあります。
遺体の引き取りについて(火葬や埋葬まで)
ご遺体を、そのままにはしておけません。遺体安置所からの留置先、ご自宅で看取られた場合には葬祭場へ移送が必要になります。

遺体の引き取りに関しては、市内にある葬祭業者に依頼しました。通夜や告別式も無く、遺体の引き取りから火葬まで平均15万円程度で対応してくれました。
埋葬の件ですが、利用者のお一人は、生前に市役所に同行して市の集合墓地に申し込みをしました。身元保証人で私(ケアマネージャー)の名義も必要でしたが、3万円程度で契約できました。
※POINT:「海に散骨してくれ」と、遺言された方もいました。散骨に関して調べてみると、那覇市では海上に限られており散骨するところも基本的に決まっているとのこと。利用者本人の想いの場所で散骨をすると法律に触れることもその時に知りました。散骨に関しても、実際には予算も船をチャーターするので30万円ほどかかると言われました(もちろん諦めました)。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
公共料金や賃貸の解約手続きについて
利用者が亡くなられたあと、労力を使う対応が「賃貸住宅の片付けと解約手続き」です。独り暮らしで生活をしていると訪問介護(ヘルパー)の介入があっても荷物が散乱していることが多く片づけに追われます。余談ですが、ゴミ屋敷の片付けは得意です。

正解を言えば、遺品整理に関してはケアマネージャーの業務ではありません。ただ、遺品整理をしていると、生前にはわからなかった利用者の姿がわかることもあります。
電気料金も抑えるためにブレーカーを落として作業するので、真夏の作業は地獄です。生活保護受給の方だとワンルームタイプの賃貸アパートなので片づける量も少ないとおもいきやゴミの分別やゴミ出しが苦労しました。
これを、家族が対応すると思うと大変な作業になると思います。終活ではありませんが、モノを捨てるタイミングは大切だと思います
結論(まとめとして)

沢村香苗さんの著書、『老後ひとり難民』をテキストにしながら「老後ひとり難民」が直面する3つの課題で記事を書いてきました。
「老後ひとり難民」が直面する課題の根底にあるのは、戦後日本社会がたどってきた「核家族」へといたる政治政策と経済成長のツケがいま顕(あらわ)れているといえます。
昭和末期と併せて失われた30年が日本に与えた恩恵とその副作用は、少子高齢化という形となって顕著になってきたと言えます。
おわりに
「老後ひとり難民」の問題には、シンプルでわかりやすい解決策がありません。また、新たな解決策が提示されるまでには、長い時間がかかりそうです。
引用:沢村香苗著、『老後ひとり難民』211ページより
長い年月をかけて、変わってきた時代の変化が、小手先の施策や努力で変わるとは思いません。これから、長い年月をかけて現実と向き合わなければならないと思います。

最後までこの記事を読んで、くださりありがとうございます。記事を読んで具体的に内容を知りたいという方にはぜひ、本書を手に取ってお読みになることをお勧めします。また、**沢村香苗著『老後ひとり難民』**は、ebookjapan(電子書籍サービス)で購入可能です。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
【関連記事:介護を成功させるための家族の役割3つのポイント】
【関連記事:「老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」を読んでわかった高齢者が直面する3つの課題】
【関連記事:理想のケアマネージャーを選ぶ3つのポイント】