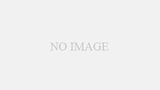2025年5月、ヴィジュアル系シーンに衝撃が走りました!─La’cryma Christiが12年ぶりに再結成するというニュースは、多くのファンにとって歓喜と驚きが入り混じる出来事となりました。
なぜなら、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、幻想的なメロディとテクニカルな演奏に加え、プログレッシブロックとも言える複雑な構成をもった楽曲のクオリティが、独自の地位を築きました。
La’cryma Christiは、LUNASEAや黒夢、GLAYといったV系黄金期に継ぐ、ポストヴィジュアル系を象徴する存在だと言えるからです。
再結成の舞台は、同世代のバンドが集結する音楽フェス「CROSS ROAD Fest 2025」。このタイミングでの復活には、2022年に他界したギタリスト・KOJIへの想いも込められており、単なる“懐かしの復活”にとどまらない深い意味が込められています。
公式ホームサイトによるコメントでは「時空を越えて、今この瞬間を共に生きてほしい」と綴られており、ファンと共に歩む新たな物語の始まりが強く示唆されている。現在では、あくまで期間限定の活動としながらも未来に向けての航路が示された瞬間だと言えます。

La’cryma Christiの再結成は、彼らの音楽が持つ普遍的な魅力を再確認する絶好の機会とも言えます。そして、その入口としてふさわしい一枚が、今回取り上げる名盤『Lhasa』です。
🎧 Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
〝PR〟
この記事を読んで欲しい人もしくは読んでわかること

本記事は、La’cryma Christiの音楽に初めてふれるかたや、再結成を機にもう一度、かれらの音楽を聴き直したいと思っているファンに向けて執筆しています。
代表作『Lhasa』を通じて、彼らの音楽性や魅力、バンドの歴史をわかりやすく理解できます。
- La’cryma Christiの再結成について解説します
- La’cryma Christiのキャリアについて知ることで再結成への理解が深まります
- 名盤2ndアルバム『Lhasa』の楽曲についてレヴューします
1990年代、ヴィジュアル系の火付け役となったX JAPANを先駆者として、LUNASEA、黒夢、L’Arc〜en〜Ciel、GLAYが黄金期を築き上げました。
その流れを引き継いで、90年代後半から、ポストヴィジュアル系と言われる「ビジュアル系四天王」がシーンに登場しました。
- SHAZNA、
- La’cryma Christi、
- MALICE MIZER、
- FANATIC◇CRISIS
の四組を指します。
今回は、La’cryma Christiを取り上げ再結成に併せて過去の作品を解説していきます。
🎧 Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
La’cryma Christiの再結成について

La’cryma Christiが12年ぶりに再結成し、2025年11月に「CROSS ROAD Fest」への出演が決定したことが大きな話題となっています。
ヴィジュアル系バンドとして90年代を代表する存在で、再始動を待ち望んでいたファンにとって、彼らの復活は歓喜の瞬間。

音楽シーンに再び光を放つLa’cryma Christiの今後に大きな期待が寄せられています。2025年5月8日にLa’cryma Christi公式ホームページ上で再結成を報告しました。その文章から引用します。
La’cryma Christiは12年振りに再始動します。
未来を夢見る青春時代に僕たちの音楽を聴いてくれたみんなも、今はすっかり大人になって、職場でも家庭でも忙しい毎日を過ごしている人も多いでしょう。
責任に押しつぶされそうになったり、頑張っていても無力感を感じたり、忙しさの中で日々に輝きを感じられなくなっている人も多いかもしれません。
みんなの人生に、今再び光が射しこむように。人生がもっともっと輝くように。
そんな願いをもって、僕たちは再始動することを決めました。
引用記事:La’cryma Christi OFFICIAL Web Site

2022年に、ギターKOJIさんのご逝去に伴い、再結成は難しいと思われていました。La’cryma Christiの音楽性を再現するにはオリジナルメンバーの存在が必要だからです。ですが、今回、バンドとして前に進む決断を下したことは、ファンとしても嬉しい限りです。
2025年11月にヘッドライナーとしての出演が決まっているLa’cryma Christiですが、「CROSS ROAD Fest」とは、どのようなフェスなのでしょうか?
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
「CROSS ROAD Fest」とは?
「CROSS ROAD Fest」は、1990年代から2000年代初頭にかけて活動し、ヴィジュアル系シーンを牽引した伝説的バンドが集結する音楽フェスティバルです。2025年11月15日(土)と16日(日)の2日間、千葉・幕張イベントホールで開催されました。
このフェスは、当時の音楽シーンを彩ったアーティストたちが一堂に会し、ファンと共に“あの頃”の熱狂を再現することを目的としています。
出演者には、
- La’cryma Christi、
- SHAZNA、
- Plastic Tree、
- Psycho le Cému、
- Waive、
- D’ESPAIRSRAY、
- PENICILLIN、
- LM.C、
- L’luvia、
- Wyse、
- FANTASTIC◇CIRCUS
など、名だたるバンドが名を連ねています 。
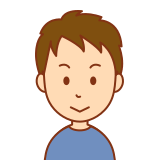
個人的にも、聞き続けているバンドとしては、Plastic Tree、PENICILLIN、FANTASTIC◇CIRCUSなどの名が挙がっており、とても興味深いイベントだと言えます。
🎧Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
La’cryma Christiが世代を越えて注目を集める理由
La’cryma Christiの再結成は、90年代のヴィジュアル系音楽シーンを象徴するバンドの復活として、世代を越えて大きな注目を集めています。
彼らの音楽は、メロディアスでドラマチックなサウンド、プログレッシブロックとも表現される壮大な構成力をもった楽曲が特徴です。
また、深い歌詞が特徴で、当時のファンにとっては懐かしさと共に、新たな世代にとっては新鮮な魅力を放っています。
特に、バンドの象徴的なアルバム『Lhasa』や代表曲「未来航路」などは、音楽的なクオリティと感情的な深さが、今もなお多くのリスナーに響き渡ります。
また、再結成という形で新たなステージを迎えることは、過去のファンにとってはもちろん、現代の若者たちにも新たな音楽的発見の場となり、ヴィジュアル系音楽の魅力が再評価されるきっかけとなっています。
La’cryma Christiが持つ独特の世界観と、世代を超えて共鳴する力強いメッセージが、今も多くの人々を惹きつけています。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
La’cryma Christiとは?バンドの基本プロフィール

La’cryma Christi(ラクリマ・クリスティ)は、1991年に東京で結成されたヴィジュアル系バンドであり、当初からそのユニークなサウンドとビジュアルで注目を浴びました。
バンドの名前「La’cryma Christi」はラテン語で「キリストの涙」を意味し、聖なるテーマを内包したその名前の通り、彼らの音楽も深い精神性とドラマ性を持っていました。
メンバーは、
- Taka(ボーカル)、
- KOJI(ギター)、
- HIRO(ギター)、
- Shuse(ベース)、
- LEVIN(ドラム)
の5人組で、メンバーの個性的なビジュアルと演奏技術の高さがバンドの特色となり、すぐにその存在感を示しました。
結成当初からインディーズシーンで活動を開始し、精力的にライブを行いながら、シングルやミニアルバムをリリースしていきました。

2022年にギタリストのKOJIが逝去されたため、オリジナルメンバーは4人。現在のライブではShinobu(ex. Creature Creatureなど)がサポートギターとして参加し、ツインギター体制を再現しています。ステージ上にはKOJIのギターも飾られ、彼の存在を感じさせる演出がされています。
🎧Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
初期の音楽性として
彼らの初期の音楽は、主にゴシックでダークな要素が色濃く、幻想的な雰囲気と重厚感のあるメロディが特徴でした。
インディーズ時代の作品には、後の音楽的方向性を予感させるような、メロディアスでありながらも、少しエクスペリメンタルなサウンドが多く見られました。
特に1994年に15000枚限定でリリースされた初のミニアルバム『Warm Snow』は、インディーズシーンでの注目を集め、La’cryma Christiというバンド名が広まるきっかけとなった作品です。

アルバム『Warm Snow』では、彼らが持つ美学と音楽性が見事に表現され、ヴィジュアル系バンドとしてのアイデンティティを確立しました。
1995年には、30000枚限定 『Warm Snow』の再レコーディング版「Dwellers of Sand Castle」が発売され、これがインディーズシーンでの代表曲となりました。
この曲は、ラクリマ・クリスティの特徴的なドラマチックなサウンドを更に深化させた作品であり、ヴィジュアル系の枠を超えて幅広いリスナー層に支持されることとなります。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
ライブパフォーマンスで独自の存在感を確立
インディーズ活動の中で、La’cryma Christiはライブパフォーマンスでも注目を集めました。エネルギッシュで情熱的なステージは、観客を魅了し、ファンの間で強い信頼を築き上げていきました。
この時期のライブでは、彼らの演奏力の高さと、歌詞に込められた深いメッセージ性がファンに強く響きました。
インディーズ時代の活動を通じて、La’cryma Christiはただのヴィジュアル系バンドにとどまらず、彼ら自身の音楽的アプローチを追求し続けました。
その後のメジャーデビューに繋がる準備期間として、彼らの音楽と演奏技術は確実に成熟し、バンドはメジャーシーンへのステップアップを果たします。
こうしたインディーズ活動の積み重ねが、La’cryma Christiをヴィジュアル系シーンの中でも独自の存在として位置づけ、後の大きな成功へと繋がる基盤を築いたのです。
黄金期のキャリアと代表作

La’cryma Christiは1997年、シングル「Ivory trees」でメジャーデビューを果たしました。カップリングの「偏西風」は、映像作品『Glass Castle』収録曲のリミックスヴァージョンが収められています。
このシングルは、カップリングと併せて、彼らの独自のサウンドを広く知らしめ、ヴィジュアル系バンドとしての地位を確立した重要な作品となります。
代表曲「With-you」がスマッシュヒット
飛躍へのきっかけとしては、4枚目のシングル曲『With-you』が挙げられます。メジャーデビュー1周年記念日にリリースされました。
初めてトップ10にランクインし、スマッシュヒットナンバーとなりました。登場回数は、La’cryma Christi史上最も多い作品となりました。
『With-you』は、今までの、暗くダークなLa’cryma Christiのイメージを払しょくする楽曲になっており、ポジティブな歌詞とポップな楽曲展開の中にラクリマらしさを込めた音楽性が見事にヒットした作品となっています。
【『With-you』のPVを観るなら:With You PV – YouTube】
未来航路が導いたバンドの進路
バンドの出世作となった「未来航路」。作曲はKOJIで家でギターを弾いていた時に「ふと浮かんだメロディー」がもとになったとされています。その後、思うように楽曲の構成が膨らまず、そのメロディーを3年間寝かせたとされています。
その後、再び作曲にとりかかったという逸話が残っています(Wikipediaより引用)。TAKAには「出会い」をテーマにした歌詞にしてくれ、と頼んでいたとされています。歌詞はTAKAの実体験とのこと。
曲のイメージとしては、清々しいアップテンポな曲調で、当時、インディーズ時代からのファンを戸惑わせたイメージが残っています。
鮮やかなギターパートと、TAKAさんのエモーショナルなボーカルが特徴的で、多くのリスナーに希望や夢を与えたと言われています。この曲を聴いて「新しい旅の始まり」を感じる方も多いと思います。
【『未来航路』のPVを観るなら:La’cryma Christi 《未来航路》】
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
🎧Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
『Lhasa』(1998)による音楽的完成と人気の頂点

2ndアルバム『Lhasa』は、彼らの音楽性が最も洗練された形で表現された作品として高く評価されています。
幻想的で耽美な世界観と、技巧的かつ叙情的なメロディが融合した本作は、ヴィジュアル系という枠を超えて幅広いリスナーに支持され、オリコンチャートでも上位にランクイン。
バンドにとって商業的にも音楽的にも頂点を極めたアルバムであり、再結成を機に改めて注目すべき代表作となっています。
『Lhasa』リリースの背景とタイミング
『Lhasa』は、La’cryma Christiがメジャーシーンで放った2作目のフルアルバムであり、1998年11月25日に発売されました。
前作『Dwellers of Sand Castle』で確立した世界観をさらに深化させ、音楽的完成度を大きく高めた本作は、ヴィジュアル系シーンの中でも異彩を放つ存在となります。
幻想性、メロディの美しさ、演奏の緻密さが一体となったアルバムは、発売当時から高い評価を受け、La’cryma Christiの代表作として現在も語り継がれています。
「yours」&「ours」
アルバムの構成は、全10曲からなります。大きく二部構成でまとめられており、前半5曲を「yours」と題し、シングル曲「未来航路」「With-you」「Lhasa」を含めた、聴きやすい明るくポップな曲がまとめられています。言ってみれば初心者向けへの楽曲が並びます。
後半5曲は「ours」と題し、前半とは一転してマニアックな曲をまとめてあります。元々、演奏に対して評判が高いバンドでしたが、曲の展開が複雑で変拍子を含んだ?プログレッシブロックの神髄が随所にちりばめられています。まさにコアなファン向けといった楽曲が並びます。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
『Lhasa』の楽曲について ~yours~
1曲目は5thシングル「未来航路」から幕を開けます。キャッチーなメロディラインと切なさを帯びた歌詞、そしてTakaの情感豊かなボーカルが見事に融合し、聴く者の心に強く残ります。
幻想的な世界観と現実を見据えた前向きなメッセージが共存し、La’cryma Christiらしい美学が凝縮された楽曲です。
続いて、2曲目「月の瞼」も疾走感あるロックンロールナンバーでテンションも上がります。ライブで盛り上げたい!っていう時に、この曲が充分に役割を果たしてくれそうです。ドライブにぴったりな楽曲ですが、個人的にL’Arc〜en〜Cielの「Driver’s High」と雰囲気が似ていて二曲とも良曲と言えます。
3曲目は、ヒットシングル「With-you」、La’cryma Christiを一気にメジャーに押し上げた楽曲です。クラシックの作曲家である、Johann Pachelbelが生涯に唯一作曲した有名曲「パッフェルベルのカノン(原題:Canon in D)」の旋律を盛り込んだと言われています。
サビのメロディーで感情を込めたボーカルが、印象的なミディアムナンバー。孤独や切なさをテーマに、淡く消えていく感情を描写しています。
4曲目は曲調がガラッと変わりオリエンタルでチャイナ風なアレンジ「SHY」、とてもかわいらしい楽曲でコミカルな演奏とボーカルを披露してくれます。
この曲を聴くとなぜかチャイナドレスのお姉さんが脳内で踊っている姿が見えるのは私だけ?
そして、アルバムタイトルでもある5曲目「Lhasa」アコースティックギターを導入に「さよなら/降り出した雨が/こころ濡らす」「さよなら/君の想い出が/僕に溶ける」と歌詞が切なく響き繊細なパートから一転、TAKAのエモーショナルなボーカリゼーションによって引き裂かれます。
まさに壮大で重厚、スケールの大きいサウンドと祈りのような歌詞が印象的でです。最後のさいごまで余韻を残すアコースティックギターとアウトロといい文句なしの楽曲構成となっています(まさに名曲!)。

「Lhasa」の歌詞の内容は大切な人を亡くした「僕」を謳っています。「喪失感」であったり、「虚無感」が襲ってくるような…絶望と、そこから何とか這い上がろうと必死に生きる想いに同調してしまいます。
【LhasaのPVを観るなら:La’cryma Christi – Lhasa PV [HD 1440p 60fps]】
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
『Lhasa』の楽曲について ~ours~
後半6曲目「Green」作詞はTAKA・作曲SHUSE、冒頭の不穏なイントロから「I can hear heartbeat from a thousand miles」の歌詞がお経に聞こえるのは全曲の余韻を引きずっているからでしょうか?不気味なワルツのテンポから一気に90年代のラウドロック調で開幕します。
Aメロ、BメロはさすがSHUSE節でサビは圧巻。初期のラクリマに通づる楽曲とも言えます。続く7曲目「PSYCHO STALKER」作詞はTAKA・作曲SHUSE、前奏からダークな疾走曲でまさにハードロック!一気に転がるような展開。
エフェクトが掛かったようなボーカルで「Hello!/何千万回ダイヤルしているのに」「Hello!/なんでこんな繋がらないの」と、怒りをのせたような歌詞が不思議な感覚へと誘います。
そして、意味深な「交差点の向こうで/ビー玉が散らばる」という歌詞。サビは美メロでまとめるところがLa’cryma Christiの醍醐味と言ったところでしょうか?
後半、8曲目は、複雑なアンサンブルと現実世界と幻想世界が交差する歌詞が印象的な「Frozen Spring」作詞はTAKA・作曲SHUSE、アンサンブルな余韻を断ち切るように、アップテンポなハードロックへと展開から…終幕へ(こんな楽曲が受け入れた時代がすごいと2025年の今、本当にすごいと思う)。
9曲目「鳥になる日」作詞はTAKA・作曲HIRO、前曲からさらにディープな世界へ誘うようなイントロから壮大な大陸サウンドをオーケストラへと昇華する。これぞ、ラクリマの十八番ともいえる楽曲。ラストに向けての期待感がいやでも高まります。
ラスト10曲目「Zambara」作詞はTAKA・作曲HIRO、7分越えの大曲。構成が複雑すぎて呆然と聴いているだけで曲が過ぎてしまう。…と思えるぐらいマニアック。
🎧Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
まとめ|追記:最近の動向(2025年12月31日現在)

という訳で、La’cryma Christiの再結成に併せて、最初に聴くべき1枚として『Lhasa』を取り上げました。
『Lhasa』を一言でいうなら、「新規のファンとコアなファン両方に向けた最大公約数的な作品」だと思います。聴きやすさと聴きごたえが同居する不思議な楽曲構成の数々。
今回、TAKAの歌詞を読み返して思ったことは「村上春樹の世界観」に通ずるものがあると感じました。
幻想と現実、確実なものと不確実なものが交差する世界観。10曲目「Zambara」には「古井戸」というキーワードが出てきます(村上春樹の作品でも古井戸は重要作品で登場するキーワードです)。
最近の動向(2025年12月31日現在)
La’cryma Christi(ボーカル:TAKA、ギター:HIRO、ベース:SHUSE、ドラム:LEVIN)は、2025年5月8日に12年ぶりの期間限定再始動を発表しました。
2022年にギタリストKOJIが逝去したため、残る4人で活動を再開。サポートギターとしてShinobu(元Creature Creatureなど)が参加しています。
KOJIの魂と遺した楽曲を継承する形で、ファンに「今この瞬間を楽しんでほしい」とのメッセージを発信しています。
主な活動ハイライト
- 2025年5月: 再始動発表。新オフィシャルサイト(lacrymachristi.jp)開設、ファンクラブ「La’cryma Christi OFFICIAL TEAM “LC GARDEN”」発足。YouTube公式チャンネル開設。
- 2025年10月: 過去音源のサブスクリプション配信解禁(ファン待望)。
- 2025年11月15-16日: 「CROSS ROAD Fest」(幕張イベントホール)両日ヘッドライナー出演。90年代〜2000年代V系バンド(SHAZNA、Plastic Tree、PENICILLINなど)が集結したイベントで、12年ぶりのステージが大盛況。KOJIのギターをステージに飾る演出で感動を呼ぶ。
- 2025年12月〜2026年: ワンマンツアー**「La’cryma Christi Live Tour 2025-2026 Night Flight 〜final call〜」**進行中。
- 12月24日(水):Zepp Namba(大阪)→ ツアー初日、クリスマスイヴ公演で大熱狂。ファンから「最高すぎる」「号泣」「KOJIのギターが目の前に…」などの感動レポート多数。
- 2026年1月3日(土):なんばHatch(大阪)
- 1月10日(土):さいたま市文化センター 大ホール
- 1月14日(水):LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公堂、東京)
追加公演「Night Flight 〜Last Finale〜」(チケット即完売を受けて決定)
- 2026年3月14-15日:LINE CUBE SHIBUYA(2days)
- 4月18日(土):柿落しシティホール(三重県桑名市民会館、TAKAゆかりの地)
- 5月9日(土):Zepp Namba(大阪、ツアーファイナル)
Xでの反響
- 再始動発表時からライブレポートまで、ファン投稿が活発。**「奇跡の復活」「涙が止まらない」「TAKAの歌声がブランクを感じさせない」「KOJIの想いがステージに」**などの感動の声が多数。
- ツアー初日(12/24 Zepp Namba)後には「前2列目で号泣」「メンバーのキラキラ顔が最高」「Your songも聴きたい!」など、セットリストや演出への興奮が広がる。
- 全体的にポジティブで熱狂的。コピーバンド活動の報告や「全通したい」「来年も続いてほしい」といった期待の投稿も目立つ。ネガティブな声はほとんどなし。

彼らのような稀有な才能を秘めたタレント(才能があるという本来の意味)は他に存在しないと思います。今後の活動にも注目していきたいと思います。
🎧Amazon Music Unlimited
1億曲以上が聴き放題。通勤・運動・読書のお供にも。
初回は無料で始められます。 🚀 無料体験してみる
※Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
【関連記事:「メタル脳」で判明!メタルを聴くメリット3選|中野信子の科学的解説とは?】