
『三国志』と聞いて、あなたはどんなイメージを思い浮かべますか?劉備、関羽、張飛が義兄弟の誓いを結ぶ「桃園の誓い」でしょうか?
それとも、三国志前半のクライマックスともいえる「赤壁の戦い」や、劉備亡きあと、病状を押して先君の意思を果たそうと「五丈原の戦い」で司馬懿と壮絶な知略戦を交わす諸葛亮の生きざまでしょうか。
三国志は様々なドラマチックな場面に彩られた歴史絵巻とも言えますが、この記事を読まれる方ならご存じだと思います。それらの多くは『三国志演義』という小説に基づいたフィクションに基づいています。
一方で、宮城谷昌光先生が描く『三国志』は、中国の正史『三国志』(陳寿著)を基にした、重厚かつ知的な歴史小説です。奇をてらったドラマや演出に基づく(フィクションの登場人物など)人間関係などではなく、「人間とは何か」「権力とは何か」「信とは何か」といった、国家と人間の在り方を説いた本質に迫る作品となっています。
今回、宮城谷昌光先生が書かれた「三国志入門」を元に、三国志の主要人物を紹介します。『三国志演義』と正史『三国志』の違いに視点を当てながら、彼らの思想と行動指針について深堀する、「現代的な教養小説」としての読み方を紹介していきます。
〝プロモーション:アフィリエイト広告を利用しています〟
この記事を読んで欲しい人もしくは読んでわかること
この記事は、宮城谷昌光著書、「三国志入門」をベースに、三国志の主要人物を紹介し、三国志の故事を紹介する「三国志初心者」にも理解が深まる構成となっています。
- 今、なぜ「三国志」を読むのか?その意味を追求します
- 作者、宮城谷昌光への理解が深まります
- 近年の「三国志」ブームの再燃について解説します
- 『三国志演義』と『正史三国志』違いを通して主要人物を多角的にとらえます
近年、ゲームや映画の影響もあり、三国志ファンは若年層から高齢者まで幅広く知れ渡っています。また、「教養ブーム」の流れもあり、歴史から学びを得ようと、ビジネスパーソンの必読書ともいえます。そんな、エンターテインメントや教養ブームを入り口に「三国志」の魅力を知って欲しいと思い、この記事を作成しました。

私も、高校時代に「横山光輝三国志」を漫画で読んだことで三国志の世界にはまりました。実際の歴史書も読みましたし、漫画「蒼天航路」は、宮城谷昌光先生の「三国志」と並んでバイブルになっています。また、「反三国志」といった、もし?蜀が天下を取っていたらという、いわゆる「ifモノ」まで、幅広く読んでいます。
〝プロモーション:Amazonアフィリエイト広告を利用しています〟
【関連記事:Amazonオーディブルで教養を身につける3つのポイント】
今、なぜ宮城谷昌光の「三国志」を読むのか?

三国志は、長らく日本人に親しまれてきた中国古典のひとつです。劉備・関羽・張飛の義兄弟の物語や、諸葛亮の奇策、赤壁の戦いなどは、吉川英治や横山光輝の作品を通して、多くの人にとって馴染みの深い英雄譚として定着しています。
しかし、宮城谷昌光が描く『三国志』は、それらの“演義”とは一線を画した、まったく異なる読みごたえを持つ作品です。彼が描くのは、陳寿の『正史三国志』に基づいた実像としての三国志。
そこにあるのは派手な戦闘や脚色された人間ドラマではなく、実在の人間たちが悩み、葛藤し、選択しながら生きた記録です。
登場人物を多面的に描くことで物語に深みが出る
宮城谷作品最大の特徴は、 “人物の内面”に焦点を当てている点です。たとえば、曹操は「残虐で冷徹な悪役」と言った一辺倒のキャラクターではなく、国家を守るために現実と格闘する合理主義者として描かれています。
また、合理主義者とは別の側面として、新たな時代を切り開く「破壊と創造」を行った文化人としても描かれていて人間像の幅が広く描かれています。
諸葛亮も、「超人的な天才」というよりも、「忠誠心と知性を併せ持った優秀な政治家」としての側面が強調されます。最初から天才的な才能を見せるような単純な物語構成ではありません。
幼い頃に故郷(徐州)を曹操に侵略された苦い経験がベースにあり、その基本戦略が魏とは組しないという、「隆中策」(りゅうちゅうさく)、日本では「天下三分の計」として、行動原理の元になるなど、行動の指針がこと細かに書かれています。
また、若い頃の諸葛亮は軍事が苦手で農政に秀でているなどの個性も描かれており、南蛮討伐と通して軍事のノウハウを学んだなど、人物の成長にもスポットを当てているところが魅力の一つです。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
歴史小説=娯楽にとどまらない「教養」の書
物語は単なる英雄譚にとどまらず、登場人物の失敗や成功、重要な決断に至った背景が、緻密な史料によって裏打ちされています。セリフや内省は控えめで、淡々と事実を積み重ねることで、かえって人物の信念や葛藤が際立ちます。
ドラマ性よりも、静かに燃える思想や倫理観を読み取る喜びがあるのです。その内容にふれていくうちに、読者が自分自身の仕事や人間関係に照らして考えられるような指針(思想ともいいます)を教えてくれる、「現代的な教養小説」に昇華されていると言えます。
さらに、歴史的背景や制度、官職の意味なども自然に織り込まれており、古代中国に対する知識も深まります。政治の機構や外交戦略、地理の構成まで把握して描かれているため、「読めば読むほど味が出る」タイプの作品といえるでしょう。
このような視点から描かれた三国志は、ビジネスパーソンや知的好奇心の強い読者層にとって、まさに“教養の宝庫”だと言えます。「なぜ人は戦うのか」「なぜ人は従うのか」「国家とは誰のためにあるのか」そんな普遍的な問いに対する答えを、登場人物の行動や言葉を通して静かに示してくれます。
もしあなたが、派手な戦闘や空想的な策略ではなく、本当の意味で“人間を描いた三国志”を求めているなら、宮城谷昌光の『三国志』はまさに教養を身につける上で最良の一冊になるでしょう。
演義ではなく“正史”だからこそ見えるリアルな人間像
宮城谷先生の筆は、その理念の崇高さを称える一方で、それがもたらす矛盾や苦悩も冷静に描きます。演義が英雄たちを理想化し、勧善懲悪や劇的な戦闘描写を通してドラマチックに描くのに対し、宮城谷の『三国志』は、陳寿の『三国志』という歴史書を土台に、人物の実像と時代背景を丁寧に掘り下げる点に特徴があります。
具体的に言うと、『三国志演義』の主人公、劉備は「仁義の英雄」として理想的に書かれます。退廃した後漢を立て直し、王朝を牛耳る曹操を打倒するため、逆境を苦ともせずに立ち向かう人徳者として書かれます。
一方、宮城谷『三国志』では、劉備の政治的計算高さや、「人徳者」というだけでは説明ができない行動原理を、「仏教的思想」という観点から読み解きます。後ほど、解説しますが、「人や国を棄てて逃げ続けたからこそ皇帝という座を手に入れた」と解説します。
同様に、『三国志演義』では、漢王朝の簒奪者として、悪役として書かれる曹操も、乱世の「奸雄」という一面だけではなく、革新的で理知的な統治者としての側面を強調されています。また、詩や書を愛し、新たな文化を築き上げるなど、その複雑な人格がリアルに描写されています。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
「儒教的価値観」が社会を支配していた後漢末期の時代背景を描く
当時の三国志の舞台が、儒教的価値観が社会を支配していたという価値観を描きます。「儒教的価値観」とは、忠義・孝行・礼儀・仁愛などを重んじる思想です。乱世の中で政治の混乱や官僚の腐敗が進むと、儒教は社会秩序を回復するための道徳的基盤として重視されました。
特に、皇帝への忠誠や家族・先祖への孝行といった価値観が、政治的正当性や支配者の徳を判断する基準とされる考えかたです。そういった「儒教的思想」が、後漢末期の時代背景を深く反映している点も見逃せません。
忠義や孝行、礼節といった儒教の価値が、登場人物たちの行動原理や政治判断に強い影響を与えていることが、史実に忠実な筆致から読み取れます。これは、現代においても倫理や人間関係の本質を考える手がかりとなり、読者に深い知的満足を与えてくれます。
こうした葛藤を、宮城谷昌光は淡々とした筆致で描きながら、読者に問いかけてきます。単純な善悪二元論や勧善懲悪といった、わかりやすい物語ではなく、時代背景や個人がもつ「思想」を根底に「理想と現実」について向き合う姿勢が読者を惹きつけます。
正史に基づくことでこそ描ける「リアルな人間像」を浮かび上がらせ、読者に新たな視点と深い感動を与える名作だと言えます。

本編に入る前に、著書の宮城谷昌光先生のプロフィールを紹介します
著者、宮城谷昌光のプロフィールについて
宮城谷昌光(みやぎたに まさみつ、1945年2月4日生まれ)は、日本の歴史小説家であり、特に古代中国を舞台とした作品で知られています。本名は宮城谷誠一。愛知県蒲郡市三谷町の出身で、早稲田大学第一文学部英文学科を卒業しました。大学卒業後は出版社に勤務しながら、作家の立原正秋に師事し、創作活動を開始しました。
当初は恋愛小説を執筆していましたが、次第に歴史に関心を持ち、特に古代中国の歴史に焦点を当てるようになりました。
『史記』をはじめとする漢籍を独学で学び、白川静の著書に影響を受けて甲骨文字や金文の研究にも取り組みました。このような深い学識に裏打ちされた作品は、史実に基づきながらも登場人物の人間性を丁寧に描写することで、多くの読者の支持を得ています。
代表作には『晏子』『楽毅』『孟嘗君』『太公望』『孔丘』『公孫龍』などが挙げられます。また、三国志のスピンオフ作品として『諸葛亮』などがあり、諸葛亮の幼少期から彼の人生を追いかけることができます。
特に、『三国志』は全12巻にわたる大作で、12年の歳月をかけて完成させました。これらの作品は、単なる歴史の再現にとどまらず、現代社会にも通じる人間の本質や倫理観を問いかける内容となっています。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
三国志の世界を知ることは、宝の山に踏み込むようなもの
週刊文春のインタビューで、宮城谷昌光先生は、三国志について「三国志の世界を知ることは、宝の山に踏み込むようなものかもしれません」と答えています。
その、インタビューで、「三国志のなかで、最高の名将は誰だったのか?いちばんの勇将は誰だったのか」と、考えるときがあると話されています。
その一人が、皇甫嵩(こうほすう)です。数十万人の信徒を擁する宗教団体が一斉に蜂起した「黄巾の乱」を、ほぼ一人で鎮めたとされています。
「そして皇帝の霊帝が亡くなった直後、董卓が朝廷を一気に制圧し、三国が分かれていくきっかけになりました。このとき皇甫嵩は、独立した勢力を持っていた陶謙から『一緒にやりませんか』と誘われたが、董卓の下に入った。その判断のまずさが、後に名将であることを知られない原因になったのです。歴史の転換期は難しいですね」
引用記事:「最高の名将は誰だったのか…」宮城谷昌光が『三国志』を縦横無尽に語りつくす特別講座 宮城谷昌光(作家)――クローズアップ | インタビュー・対談 – 本の話
そのほかにも、魏の武将「張遼」の名前を挙げて「三国志が本当に好きな人は張遼が好きだと思う」などと答えています。他にも、呉の武将「陸抗」を取り上げ「呉の国で爽やかで心に沁みた生き方をした最高の人物」と評価をされています。
また、宮城谷昌光三国志の主人公「曹操」を以下のように語られています。
「人の能力を見極めたり、組織で人を使ったり、率いたりするにはどうすればいいのか。人材発掘がうまい曹操から学ぶ必要があります。歴史書の原文は読みにくいでしょうから、歴史小説をもとに考える力を養うのがいいでしょう」
引用記事:「最高の名将は誰だったのか…」宮城谷昌光が『三国志』を縦横無尽に語りつくす特別講座 宮城谷昌光(作家)――クローズアップ | インタビュー・対談 – 本の話
宮城谷昌光三国志を読むことで、彼らの思想と行動指針についてしることが出来ます。まさに、曹操の生きかたや考えかたは、現代のリーダーとは?という考えかたで読み解くこともできます。そういう意味でも、三国志は「現代的な教養小説」としての役割を果たしていると言えます。
三国志人気の再燃について

〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
近年、エンターテインメントを中心に、三国志の人気が再燃しています。映画『レッドクリフ』やNetflixでのアニメ配信。さらには、アクションゲーム『真・三國無双8』や、シュミレーションゲーム『三國志14』、などのゲームシリーズが若い世代にも浸透しています。
併せて、SNSでも名言や武将ネタが話題です。例えば、「もし三国志武将が現代の会社にいたら?」というテーマで、曹操が「超合理的な経営者」、諸葛亮が「戦略コンサルタント」、関羽が「忠義に厚い営業部長」として描かれることもあります。
ビジネス界では、諸葛亮の戦略や曹操の人材登用術がマネジメント書で取り上げられるなど、三国志は「知略と人間力の宝庫」として注目を集めています。
三国志を題材にした漫画も…
また、三国志を題材にした漫画には、歴史を忠実に描いたものから、ユニークな解釈を加えたものまでさまざまあります。以下の作品が特に人気です。
- 横山光輝『三国志』
- 『蒼天航路』(原作:李學仁、作画:王欣太)
- 『覇-LORD-』(原作:武論尊、作画:池上遼一)
横山光輝の『三国志』は、日本の漫画界を代表する長編歴史作品で、全60巻(文庫版で30巻)という圧倒的なボリュームです。中国の古典「三国志演義」をもとにしながらも、横山氏独自の解釈が加えられた壮大な物語です。
『蒼天航路』は、英雄・曹操を主人公に据えた独自の三国志漫画です。三国志演義や正史に基づきながらも大胆なアレンジが加えられ、曹操を「最も人に興味を示した英雄」として描きます。従来の悪役イメージを覆し、合理主義と革新を追求する人物像が鮮やかに表現されています。
『覇-LORD-』は武論尊原作、池上遼一作画による歴史IF漫画で、中国の三国時代を舞台にしています。主人公は倭国の武将・燎宇。彼は倭統一を果たしながら後漢へ渡り、劉備らと出会います。しかし、劉備の非道さを見限り、その首を刎ね、自らが新たな劉備となる物語が展開されます。上記3作品の中では異色作とも言えます。
異色作『パリピ孔明』とは?
上記の作品だけでなく、三国志のオマージュ作として、映像化もされました『パリピ孔明』が挙げられます。『パリピ孔明』は、三国時代の天才軍師・諸葛亮孔明が現代の日本・渋谷に転生し、駆け出しのシンガーソングライター月見英子の夢を叶えるために軍師(マネージャー)として活躍する物語です。
孔明は五丈原の戦いで病死する際、「戦のない時代に生まれたい」と願い、気がつくとハロウィンで賑わう渋谷の街に若き日の姿で転生していたというところから始まります。そこで英子の歌声に感動し、彼女の成功を支えることを決意します。
孔明は三国志の知略を活かし、英子の音楽活動を戦略的にサポートしながら、彼女をトップアーティストへと導いていくというストーリーになっています。
映像化された『パリピ孔明』の主演俳優は、諸葛孔明役を向井理さんが務めています!そして、月見英子役には上白石萌歌さんが抜擢されています。映画『パリピ公明THE MOVIE』が、4月25日より公開されています。
【予告編を観るなら:映画『パリピ孔明 THE MOVIE』予告編【4月25日(金)公開】】
三国志の主要人物たち「演義」と「正史」から読み解く

三国志に登場する英雄たちは、単なる伝説上のキャラクターではなく、実在した歴史人物です。宮城谷昌光著『三国志入門』では、正史『三国志』に基づき、曹操・劉備・諸葛亮・孫権らの実像を冷静に描き出しています。
義や智、忠と野心といった複雑な人間性が浮き彫りになり、現代にも通じる「人間の本質」を学ぶことができます。本章では、演義では語られにくい彼らのリアルな姿を、正史をベースに解説していきます。
くりかえしますが、後漢末期は儒教的な価値観が依然として社会の基盤を形成していました。それは「仁」「礼」、「孝道」、そして「君臣の倫理」を重視するものでした。
この時期には、政治的混乱や社会的不安が拡大する中で、儒教的な道徳倫理が社会秩序維持の重要な役割を担っていました。
こうした価値観を知っているだけで宮城谷先生の三国志を面白く読むことが出来ます。それでは、革新者としての曹操の在りかたから解説していきます。
曹操:時代に要請された革新者
曹操(あざなを孟徳といいます)は、『三国志演義』においては、乱世の「奸雄」として描かれることが多く、狡猾で冷酷、目的のためには手段を選ばない野心家というイメージが強く定着しています。
しかし、宮城谷昌光著『三国志入門』では、そうした通俗的な見方を超え、曹操の本質を「革新者」として再評価しています。
宮城谷は、史実に忠実で簡潔な記録が特徴の正史『三国志』(陳寿著)に基づき、曹操を「漢王朝」簒奪をたくらむ悪役ではなく、乱世を立て直そうとした現実主義の改革者として描いています。
当時の常識としての「儒教」
漢王朝は、国を統治する思想として「儒教」という考えかたを採用してました。曹操が活躍する、三国志(後漢末期)の時代は、「儒教」的な考えかたが揺らぎ混乱していた時代ともいえます。
その、曹操の最大の特徴は、時代の混乱を正面から受け止め、従来の(儒教的な)常識や価値観を打ち破ることで、新たな秩序を築こうとした点にあります。彼は家柄や門閥にこだわらず、才能ある者を積極的に登用しました。
能力があるものを登用し適材適所に配置すると言えば、現代の価値観では当たり前なかんがえかたですが、当時の儒教的な価値観では、人材の基準は「仁」「礼」、「孝道」が中心であり、個人の「才能」は問いませんでした。
荀彧や郭嘉、程昱など、のちに魏の柱石となる優秀な人材を見出し、彼らの助言を取り入れて柔軟に政治・軍事の判断を下していきました。これは、儒教的な価値観や貴族中心の支配体制が常識だった当時としては画期的な発想でした。
※POINT:当時(後漢)の常識として「儒教」があたり前だったこの時代は、機能不全を起こしており停滞感に満ちていました。言うなれば、曹操は常識に囚われない革新者として「時代に要請された」英雄だったという見方もできます。『三国志演義』では、悪役(奸雄)として、あくまで脇役の立場で書かれますが、実際の歴史(正史)は曹操を中心に動いていたと言っても過言ではありません。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
時代を切り開く革新者
また、曹操は厳しい軍律を敷き、戦乱に苦しむ民衆を保護する政策を推し進めました。自ら耕作を奨励して屯田制を導入し、荒廃した土地の再建に力を注ぐなど、単なる戦上手ではなく、内政においても優れた実行力を持っていたことがわかります。
これは、戦乱を制するための武力と、社会を安定させるための制度改革の両立を図った姿勢にほかなりません。
さらに宮城谷先生は、曹操の文学的才能にも注目しています。彼の詩には、征戦の孤独、英雄の悲哀、そして理想と現実の狭間に揺れる心情が率直に表現されており、彼が単なる野望家ではなく、深い内省を持った人間であったことが読み取れます。
表面的な「奸雄」というレッテルの背後には、理想と現実に苦悩しながらも自らの信念を貫こうとした人物像が見えてくるのです。
劉備:義に生きた?不可解な野心家
劉備(あざなを玄徳といいます)は、『三国志演義』においては「義」の象徴として描かれ、関羽・張飛との桃園の誓いや、民を思いやる姿勢が強調された理想的な英雄像が広く知られています。
『三国志演義』の劉備は、「漢王朝」の退廃を憂う勤王主義でありながら、自身で何もすることが出来ない境遇に鬱勃としながら、母の孝行をしている…というキャラクター設定から舞台は始まります。
一方で、退廃しつつある王朝の中で出世を図り、ゆくゆくは漢を牛耳ることで、ゆくゆくは王朝簒奪をたくらむと言った若き日の曹操と、相対的に書かれています。「勧善懲悪」と言った視点で物語が書かれています。
しかし、宮城谷昌光著『三国志入門』では、こうした英雄的美化を一歩引いて見つめ、史実に基づいた劉備のもう一つの側面――「不可解な野心家」として注目しています。
曹操と何度、戦っても負け続け、逃げ続けていく劉備の元には、なぜか人材や国が集まるということが起こります。「人格者」という一面だけではとらえきれない人間像が書かれています。
正史『三国志』における劉備は、涿郡の出身で、初めは草履を売って生計を立てていたという極めて庶民的な立場から身を起こしました。血筋こそ漢王朝の末裔とされるものの、実際には権力基盤も軍事力もなく、まさに「ゼロからのスタート」でした。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
劉備の価値観としての「仏教思想」
そうした中で、彼の生涯には、いくつかの不可解さが散見すると言います。そのひとつに「まったく恩返しをしない」点が挙げられます。
自分を育ててくれた母に何をしたのか?若い頃に学資を出してくれた同郷の劉元起とのつきあいも書かれていません。宮城谷先生はこの点に着目し、劉備を「棄てていく人」であると解説します。
あえていえば、劉備は、
「棄てていく人」
です。旧来の倫理観では、それは薄情な人、恩知らず、となります。しかしながら、棄てつづけることは、保持しない、所持しないことであり、そのような信念と思想は、のちの仏教思想に通じていて、きわめて特異です。
引用:宮城谷昌光著、「三国志入門」~109ページ~
逃げの劉備
その後、袁紹と曹操が官渡でぶつかります。その後、袁紹が曹操に敗れたことを知ると、劉備は「恃むべきは劉表か」と思い、荊州の劉表を説いて、最上の賓客の礼をもって待遇されます。さらに、劉表は自身の兵を与えて、新野県に駐屯させました。
すでに、この時点で、曹操の元にいた関羽は劉備の元にはせ参じます。戦乱の混乱ではぐれた張飛や公孫瓚の下にいた俊英の趙雲も劉備のもとに集合します。ここでも、劉備の不思議な魅力について解説します。
(前略)それにしても劉備は不思議な人です。さきに曹操を裏切って小沛にもどり、曹操の攻撃をうけたとき、配下の安否を気にかけもせず、身ひとつで逃げたのです。見棄てられた者たちは、それでも劉備を慕ってあとを追ってきたのです。また、官渡の戦いのあとに群雄をながめてみると、いまだに生きている大物は、曹操と孫権、それに劉表しかいません。敗戦の多い劉備がなおも生きていることは、奇蹟に比(ちか)いといえましょう。
「逃げの劉備」
それもひとつの劉備像でしょう。すべてを棄ててゆくことによって、いのちを拾う。生きかたとしては、放れ業といえましょう。
引用:宮城谷昌光著、「三国志入門」~121・122ページ~
明確な思想をもたず、配下をおもいやる心ももたない劉備に、随従しつづける者たちの心情と考えとはどのようなものか?と、宮城谷先生の困惑の顔が思い浮かびます(ほほえましい場面だと思います)。安易に「人徳」や「人格者」と決めつけない宮城谷先生の歴史に対する解釈に頭が下がります。
〝プロモーション:Amazonアフィリエイト広告を利用しています〟
諸葛亮に遭って展望をもつ
劉表が治めていた頃の荊州は、内政の充実をこころがけ、教育にも熱心でした。州内に好学の風土を作り上げた見事な統治だと言えます。それゆえ、戦乱を嫌い、学問をしたいと多くの人材が、劉表の本拠地とした襄陽とその周辺に集まります。
このことが、劉備にさいわいすることになります。至宝というべき人物を得たのです。当時、襄陽の西の隆中に住んでいた諸葛亮を三度訪ねて、臣従させたのです。
自立したいがために逃げまわってきた劉備は、諸葛亮に遭って、はじめて展望をもちました。いわゆる「天下三分の計」です。
諸葛亮:天才軍師の光と影
諸葛亮(孔明というあざなは有名ですね)は、「天才軍師」として三国志の中でもひときわ強い人気を誇る人物です。『三国志演義』では、劉備の「三顧の礼」に応じて仕官したことで広く知られますが、天をも動かす知略と忠誠心を持ち、劉備の死後も蜀のために生涯を捧げた名軍師として理想化されています。
しかし、宮城谷昌光著『三国志入門』では、そうした英雄像の一方で、諸葛亮の人間としての「影」の部分――限界や苦悩にも光を当て、より立体的な人物像を浮き彫りにしています。
宰相として史上まれに見る諸葛亮
諸葛亮の本領は、戦場よりも政務にありました。蜀における内政の安定、法制度の整備、経済再建など、多くの功績は諸葛亮の手によるものです。
宮城谷先生はこの点を重視し、「彼の最大の才能は軍略ではなく、国家運営にあった」と述べています。実際、諸葛亮が丞相として政務を執った時代、蜀は乱れた政情の中でも秩序を保ち、清廉な政治が行われたと伝えられています。
ところが、諸葛亮の国家戦略は思いがけない頓挫をきたすことになります。荊州を治めていた関羽が、孫権と呂蒙の謀略によって殺されてしまいます。
それを怒った劉備が呉を攻撃します。「真の敵は魏であって呉ではありません」と、諸葛亮の献言をすべて容れてきた劉備ですが、この一事に対してはまったく諮問もせず、出陣し翌年に敗退します。
そのうえ、帰還した劉備は罹病し重体に陥ります「自分の子が補佐する価値がなければ、なんじが皇帝となれ」と、劉備は諸葛亮に言い遺こして崩じます。
(前略)このとき、劉備の子劉禅は十七歳で、諸葛亮は四十三歳です。劉禅は凡庸そのものの皇太子で、実際のところ、補佐するに価しないあとつぎでした。諸葛亮はそれがわかっていながら、
「わたしは股肱となって力を尽くし、忠節を死ぬまでささげます」
と、誓って、劉備を安心させ、そのことば通りに、劉禅の政治を暗くみせないような治世を出現して補佐しぬくのです。
引用:宮城谷昌光著、「三国志入門」~165ページ~
諸葛亮は、史上まれにみる清心の宰相であったと宮城谷先生も評価されています。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
戦略の評価としてはいまいちな諸葛亮
一方で、諸葛亮の軍事面に関しては、現実の評価はやや複雑です。北伐では魏に対して幾度となく攻勢を仕掛けましたが、最終的な勝利には至らず、蜀の国力を消耗した側面も否めません。
宮城谷先生はここに、理想と現実のギャップに苦しむ諸葛亮の姿を見出しています。忠義ゆえに出兵を繰り返しながらも、それが長期的に国家にとって最善であったかどうかは、読み手に問いを投げかける構成になっています。
また、劉備亡きあとの戦略への影響に対しては、部下の馬謖の意思が反映されたのでは?と疑問を呈しています。そのことが、のちの北伐で魏延との確執を生む結果となってしまいます。
一方で、諸葛亮は極めて規律を重んじる人物でもありました。自らに厳しく、他人にも同様の規範を求めたため、時に部下たちの自由な発想を抑制したとも言われます。
「泣いて馬謖を斬る」という逸話に象徴されるように、個人の感情ではなく組織の秩序を優先した判断を下す姿は、冷徹にも映る一方で、リーダーとしての苦悩を物語っています。
宮城谷先生はこのエピソードを通して、諸葛亮が理想を守るために、いかに多くの「痛み」を引き受けていたかを描いています。
孫権:竜頭蛇尾な皇帝
孫権(あざなは仲謀といいます)は、『三国志演義』における孫権のイメージは、冷静沈着で現実主義的な若き指導者として描かれています。兄、孫策の急逝後に若くして江東を継ぎ、周瑜や魯粛といった優れた家臣の補佐を受けながら、曹操の侵攻を『赤壁の戦い」で破り、蜀や魏との複雑な関係の中で巧みに勢力を維持していきます。
劉備や曹操のようなカリスマ性や突出した個性こそ控えめですが、安定した統治を志向し、時に強硬な決断も下せる堅実なリーダーとして描かれています。
その姿は、英雄たちが激しく争う三国時代にあって、理想と現実の狭間で生き抜いた、もう一つの賢者像とも言えるでしょう。
宮城谷昌光著『三国志入門』では、孫権のことを「竜頭蛇尾」として厳しく評価されています。その評価の裏には、偉大な父「孫堅」と、若くして横死しましたが英雄とも言える、兄「孫策」の影響もあったと思います。
孫権の晩年について、冷静で現実主義的な若き日の姿とは異なる、迷いや老い、そして残虐性が顔をのぞかせる側面に注目しています。若くして兄・孫策の後を継ぎ、柔軟かつ慎重な政略で呉を半世紀近く維持した孫権でしたが、晩年にはその明晰さを失い、猜疑心と権力欲に囚われた暴君的な行動が目立つようになります。そのことから「竜頭蛇尾」と評価されてしまいます。
孫権、十九歳にして起つ
兄の孫策が横死したとき、孫権は十九歳でした。食客(暗殺者)が放った矢に斃されました。兄の死をまぢかでみた孫権は「単行先行には災いがある」と、肝に銘じました。
なぜなら、父「孫堅」も兄「孫策」も単騎(1人で馬に乗っている)で、先に行ったことで災いに遭い命を失ったからです。
孫権は、生涯の中で従者から離れるといった単独行動を取りませんでした。そのことにより、兵略から大胆さを失わせることになりました。
そのことは、「自身の用兵には天下をあっといわせるものはなく、拙劣と言ってよいものになった」と、厳しい評価をしています。
父、孫堅と兄、孫策の徳に扶けられる
孫権は政治と軍事の手腕がはっきりとはせず、それでいながら「呉」という広大な広さを治めていかなければならない不安定な立場にありました。
そのような立場にありながら、悪臣がでずに皆で力をあわせて孫権を盛り立てていく状況ができたことは、「孫堅と孫策の徳の力」に支えられたと宮城谷先生は言います。
後年、呉の皇帝となった孫権は若き日の姿とは違い、猜疑心と権力欲に囚われ残虐な行為を行います。あげくには、悪臣がでて国を乱し滅亡への道をたどります。孫権の晩年の行動が「孫堅と孫策の徳の力を喪わせた」とも言えます。
曹操の侵攻に孫権おおいに悩む
荊州を下した勢いに乗って、曹操は呉への侵攻を開始しようと江水に大船団を浮かべて臨戦態勢に入ります。宮城谷先生は、「孫権の生涯をみわたしても、最大の危機とはこれであった」と書いています。
張昭をはじめ群臣は「曹操に従うべきだ」と、孫権に訴えます。群臣らは、曹操の兵力が強大であることに恐れをなしたと見なされています。
その中で、張昭は儒教を信奉する学者であるといってよく、「孫権が曹操に帰順すれば、戦乱がやみ、天下の民は安心して暮らせる」と、個人の欲望を棄てたかたちで言ったのでは?と、「三国志入門」では考察されています。
呉軍、赤壁にて果敢に闘う
しかし、大半の服従派の中で、魯粛と周瑜だけが抗戦を主張します。孫権に従う群臣の中で、おそらく魯粛だけが、呉が天下を制するにはどうしたらよいのか?というグランドデザインを描いていた戦略家だったと評価しています。
とにかく、孫権は、「曹操と戦う」と、決断し、周瑜を提督に任命し程普と共に水軍を率いて赤壁に臨みます。いわゆる「赤壁の戦い」が幕を切って落とされます。
周瑜は火攻をもって曹操の大船団を大破し、曹操を敗走させます。戦勝を聴いた孫権は、みずから軍を率いて合肥(がっぴ)を攻めますが下すことはできませんでした。以後、孫権の用兵のまずさはがあきらかになります。一方で、荊州の南部を劉備が平定してしまいます。
翌年、江夏太守の劉琦(劉表の息子)が病没します。劉琦に仕えていた臣下や官吏がこぞって劉備に帰順することになり、その勢力は大きなものへとなっていきました。
周瑜や呂範などは、劉備を警戒し嫌悪するあまり、抹殺したいと策を講じようとします。その中で、魯粛だけが劉備との融和を考えるように孫権に献策します。こころならずとも、魯粛の進言を容れた孫権は、妹を劉備に嫁がせます。
関羽、呂蒙の計略にはまる
勢力が拡大した劉備軍は、諸葛亮の策に乗って、蜀へと軍を進めます。苦々しい思いでいた孫権は、荊州に常駐する関羽を殺し、荊州を取ろうと呂蒙の謀計を採用して関羽を捕斬します。その首を曹操に送りつける話があるのですが、『三国志演義』と、『正史三国志』の記述が違っていて面白いので紹介します。
正史『三国志』(陳寿著)では
関羽は荊州を守っていましたが、夷陵の戦い以前、魏との戦いで樊城を包囲していた際、背後の拠点を孫権軍(呂蒙ら)に突かれ、孤立無援の状態で敗走します。
呂蒙の部下・陸遜や潘璋の軍によって捕らえられ、処刑されました。その後、孫権は関羽の首を曹操に送りました。
その意図は、関羽を殺した責任を回避するためと言われています。関羽は曹操政権下の魏とも因縁があったため、「彼を処刑したのは魏への配慮」という形を取り、劉備との対立の正当性を主張したとも考えられています。
また、当時、孫権は魏との宥和政策を取っており、関羽の首を贈ることで魏との関係強化を図ろうとしたとされています。
『三国志演義』での描写では
関羽は荊州を軽視し、呂蒙の計略(白衣渡江)により油断していたところを突かれ、部下の裏切りにもあって捕らえられます。
孫権は関羽の英雄ぶりに恐れを抱き、魏との関係強化と劉備への牽制のために曹操へ首を送りつけました。曹操は関羽を敬愛していたため、首を手厚く葬り、廟を建てて祀ったとされています(これは後世の脚色とも言われます)。
※POINT:関羽の処刑と首が曹操に送られたこと自体は事実(正史にも記載あり)です。孫権の意図は、主に 政治的立場の調整と劉備・蜀との対立の緩和を図るための外交的配慮と見るのが妥当です。ただし、演義ではこれに英雄譚的な要素(曹操の敬意など)が加わり、ドラマティックに描かれています。関羽の死は、三国鼎立前夜の緊張と駆け引きの象徴ともいえる場面です。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
陸遜、蜀を大敗し天下に名をとどろかせる
卑劣な策を講じて、関羽を殺した孫権を劉備は許すことができません。諸葛亮の進言を以てしても、怒りを斂(おさ)めることができず、劉備はみずから軍を率いて、呉に進攻しました。
先の提督、周瑜は病床に沈み、呂蒙や魯粛と言った呉の重臣は鬼籍に入りています。孫権は、いまだ用兵の実力が定かではない、陸遜を適用し、提督として蜀軍にあたります。
結果、陸遜は蜀軍の五つの駐屯地を攻めて大破し、勢いに勝って大勝を納めます。この戦いは「夷陵の戦い」と歴史に名を残します。陸遜が、この戦いで名が天下に知れ渡りました。
陸遜、孫権の逆鱗に触れ憤死する
夷陵の戦いから、二十三年後に陸遜は不幸の死を遂げます。孫権の愚劣な後継者選びに巻き込まれる形でそれはおとずれました。
後継者争いに対して、陸遜は長幼(ちょうよう)の序を明確にすべきであると、孫権を諫めました。ところが、そのことが孫権の逆鱗に触れ、陸遜を流罪に堕とし、さらに詰問で責められた陸遜は憤死しました。宮城谷先生も「孫権は国家の支柱たる名臣を自身の手で葬った」と、批判します。
結果、孫権は七十一歳で崩じ、大皇帝という諡名(しごう)がおくられますが、曹操と戦っていた頃のはつはつさは晩年にはありません。
徐々に政治が暗くなり、判断力が衰えそのことによって国を混乱させることになりました。長生きしすぎた結果だとも言えます。
そんな、孫権の美点を「読書家であった」とふれています。さらに「仏教を保護した文化人」の一面もあることを覚えておくと良いかもしれません。
まとめとして~「正史」と「演義」の書かれ方の違いについて~
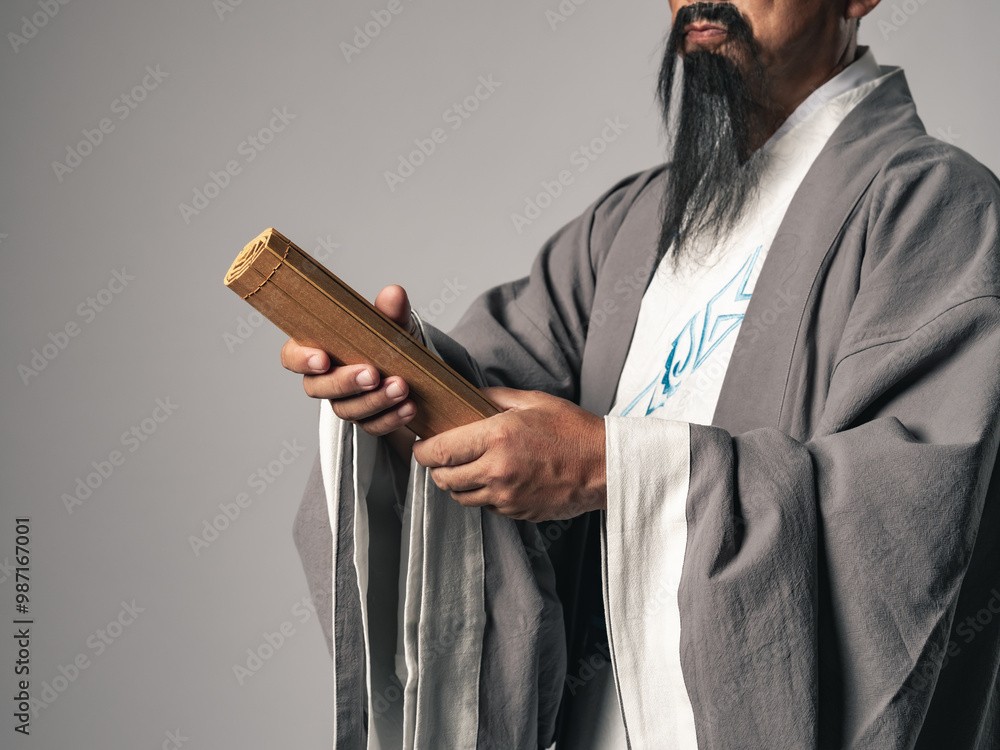
という訳で、『三国志演義』と『正史 三国志』の主要人物を紹介してきました。「演義」と「正史」の書かれかたを知ることで、登場人物の魅力を色んな角度から考察ができたと思います。
ここでは、なぜ、三国志の書かれかたが、「演義」と「正史」では違うのか?記事を振り返りながら要点をまとめてさいごにしたいと思います。
「正史」三国志は三国時代(魏・呉・蜀)の歴史書である
正史三国志の特徴は、中国の三国時代(魏・蜀・呉)の歴史を記録した歴史書であり、西晋時代の歴史家・陳寿によって編纂されました。その最大の特徴は、正史としての立場を貫き、事実の記録に重点を置いた点にあります。
もう一つのポイントとして、「晋」という国は、「魏」という国の後継であるという視点も重要です。三国志は3つの国が鼎立した、特異な時代だったのです。
ですが、「漢(後漢)」→「魏」→「晋」と、時代の継承がなされたとされており、歴史の中心はあくまで「魏」であり、主人公は曹操であったという見方ができます(また、晋にとって都合の悪い歴史は消されたもしくは修正されたという見方も大事です)。
これは晋の政治体制を支持し、晋の前身である魏を正統とする「魏晋史観」に沿った判断であり、当時の政治的背景を反映しています。
また、正史三国志の全体構成は「紀伝体」という形式をとり、人物を中心に歴史を記述しています。『三国志』は本来、「魏書」30巻、「蜀書」15巻、「呉書」20巻の全65巻から成り立っており、魏を正統王朝と位置づけたうえで、魏・蜀・呉の重要人物や出来事を記録したことも読み取れます。
著者の陳寿の生きざまが反映されている
正史三国志の著者である陳寿は、はじめ蜀漢に仕え、著名な政治家・費禕や姜維の下で記録係や文官として働いていました。蜀が滅亡すると、しばらく職を失いますが、その後、魏に仕え、最終的には晋の朝廷に仕官します。
晋の学者・張華に見いだされて、史書の編纂に従事し、『三国志』を完成させたとされています。
陳寿は、史書の記録において客観性・簡潔性を重んじたと評価されています。彼の筆致は冷静で、装飾を排し、事実を淡々と記録する姿勢が特徴です。
とはいえ、彼自身は蜀の出身でありながら、魏を正統と認める立場をとって『三国志』を編纂しました。
一方で、諸葛亮に対しては非常に高い評価を与えるなど、個人的な尊敬や出身地の影響がにじむ記述も見られ、完全に中立というわけではありません。
このため、後世の学者たちは彼の記述に対して賛否を分けています。言ってみれば、三国志は作者である陳寿の「生きざま」も描かれていると言えます。
〝プロモーション:Amazonアフィリエイト広告を利用しています〟
「三国志演義」は長編歴史小説である
『三国志演義』は、明の時代に羅貫中によって書かれた長編歴史小説であり、陳寿の『三国志』をもとに、さまざまな伝承や講談、民間説話などを取り入れて再構成された文学作品です。
『三国志演義』は全120回(章)から成り、後漢末から魏・呉・蜀の三国鼎立、そして晋による天下統一までの約100年にわたる歴史を描いています。
最大の特徴の一つは、人物の「善悪」が明確に描かれている点です。「正義」と「悪」の二元論で語ることによって、「物語をわかりやすく」する効果があり、読者に感情移入させやすくするためのテクニックを使っていると思えば、理解しやすいと思います。
また、『三国志演義』は数多くの有名なエピソードを通して知られています。たとえば「桃園の誓い」「三顧の礼」「赤壁の戦い」「空城の計」など、どれも創作・誇張が加えられているものの、読者の印象に強く残る場面です。
盛り上がる「場面設定」を意図的に創ることで、物語のハイライトを展開できるというテクニックを使っていると思えば、理解しやすいと思います(下世話な表現ですいません)。
「小説」とは「大説」に対する対義語である
『三国志演義』とは、歴史書をもとに書かれた「歴史小説」であると説明しました。知っておくと面白い知識として「小説」とは「大説」に対する対義語であるということです。「大説」という言葉はあまり使われませんが、「歴史書」のことを指します。
言うなれば、「歴史書」に対する「読み物」としての扱いであり、「小説」という言葉じたいが、「大説(歴史書)」に対する差別用語だともとれます。
その要因として、「儒教(正確には朱子学)」の影響がここでも挙げられます。朱子学について、ここではふれませんが、演劇や読み物といった娯楽は庶民が観るものであると言った偏見が「小説」という言葉に名残として残っているということです。
さいごに

ここまでお読みいただきありがとうございました。『三国志入門』では、陳寿の『三国志』を土台に、曹操や劉備、孫権といった英雄たちの実像とその時代背景を平易に解説されています。
演義で描かれる英雄像に疑問を持った読者にこそ、正史を知る最初の一歩としてふさわしい一冊です。
また、三国志という壮大な物語りを語りきるには、ページがいくつあっても足りないと思います。今回は、主要人物にスポットをあてて紹介しました。今後も三国志の色んな作品や人物を紹介できればと思います。次の記事もよろしくお願いいたします。
〝PR:アフィリエイト広告を利用しています〟
【関連記事:【2025年版】世界史のおすすめ本10選|教養として楽しく学べる入門書を厳選!】
【関連記事:宮城谷昌光が描く「秦末~楚漢戦争」の世界|おすすめ歴史小説5選と読み方ガイド】
【関連記事:宮城谷昌光『三国志名臣列伝〈魏篇〉』から見る魏の名臣を紹介【程昱篇】】







