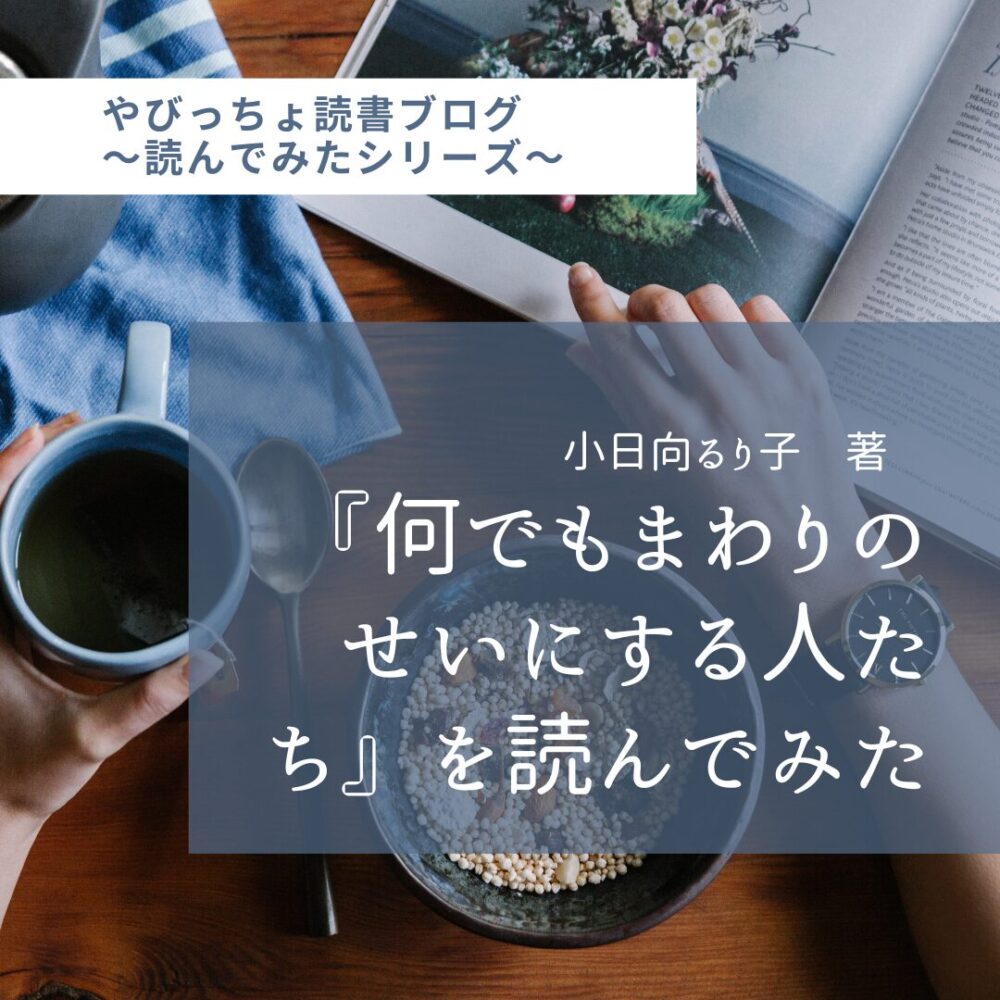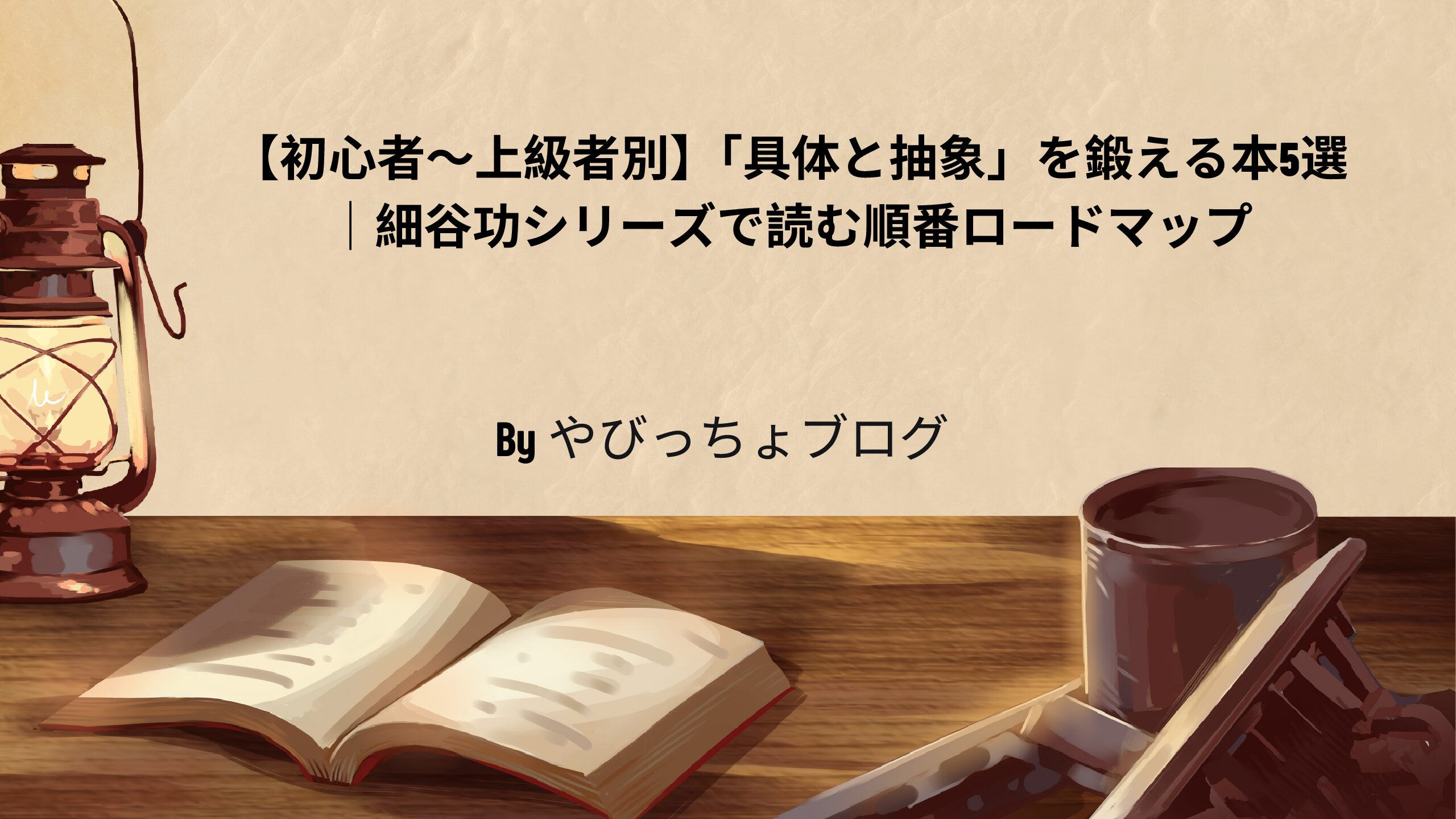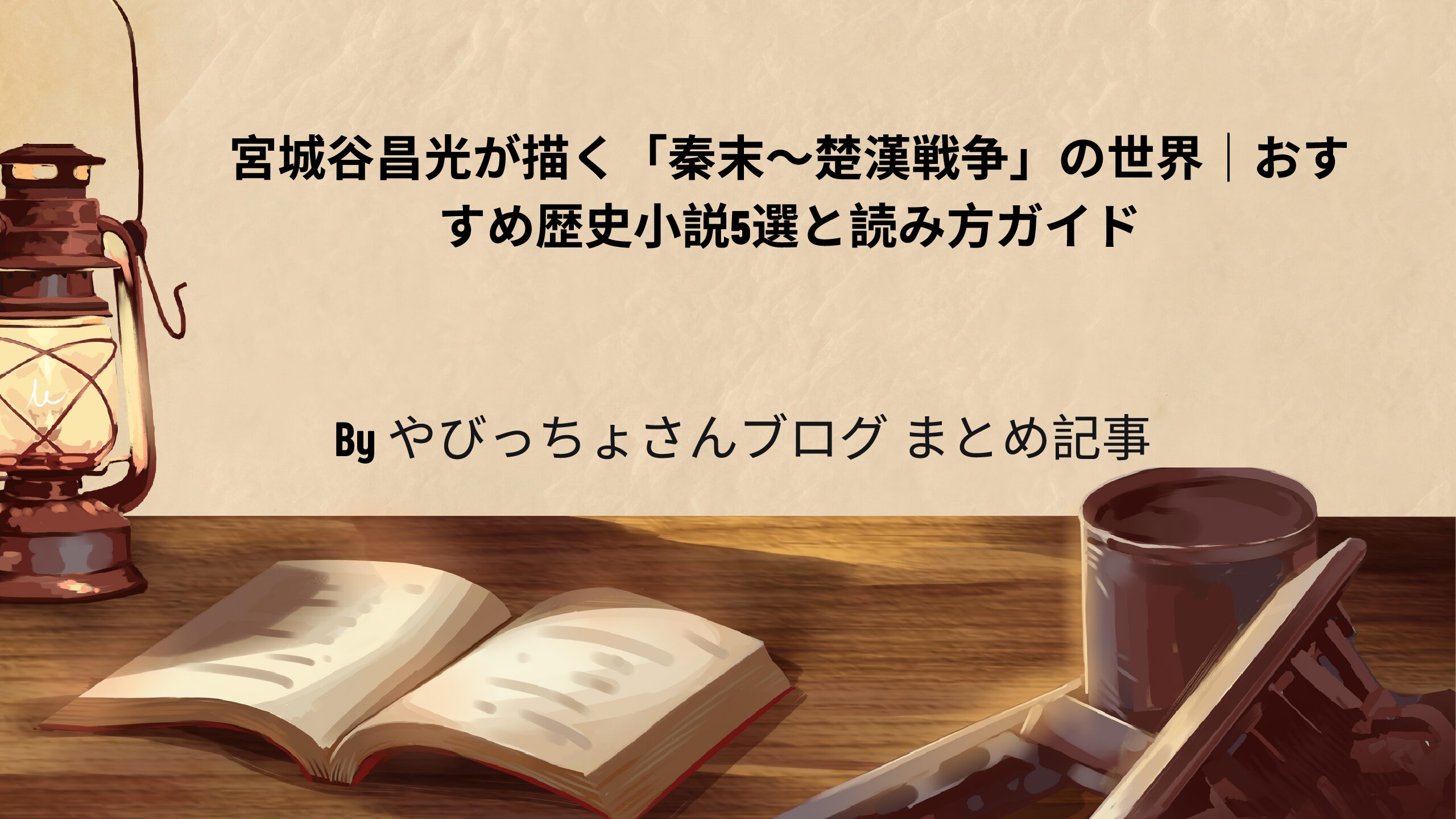職場や家庭で「何でもまわりのせいにする人」に出会ったことはありませんか。「あの人が悪い」「親のせいだ」「会社が悪い」といった発言は、心理学的に「他責思考」と呼ばれる思考パターンの表れです。
産業カウンセラーとして20年以上、6500件を超える心のサポートを行ってきた小日向るり子さんは、著書『何でもまわりのせいにする人たち』でこの他責思考の心理メカニズムについて改善法を解説しています。
他責思考とは、トラブルや失敗の原因を自分ではなく外部に求める姿勢であり、「自己責任を回避し失敗から自分を守る防御機制」の一つと位置づけられます。

「他責思考」は誰にでも多少はある考え方だけど、それが強くなると、自分の非を認めずに人のせいにしたり、問題解決に自分から動かなくなったり、言い訳や被害者意識が増えたり…っていう行動が目立つようになるんだ。

パパ!そのせいで、自分が成長できるチャンスを逃しちゃったり、学校とかおうちの人間関係が悪くなっちゃったり、ストレスとか孤独感がどんどん増えちゃったり…って、自分にとってすごく大きなデメリットになっちゃうんだよね。
本書『何でもまわりのせいにする人たち』はこうした背景や特徴を整理し、「ほどよく自責・ほどよく他責」というバランスのとれた思考法へのシフトを提案しています。
本記事ではその内容をもとに、他責思考の定義・心理的メカニズム・改善のヒントを詳しく見ていきます。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
他責思考の特徴と問題点

「失敗したのはあの人のせい」「会社が悪いからうまくいかない」──そんなふうに物事の原因を周囲に求める“他責思考”は、誰にでも少しはある思考パターンです。
“他責思考”の傾向が強くなると、自分の非を認めずに責任転嫁したり、問題解決に主体的に動けなかったり、言い訳や被害者意識が増えたりといった行動が目立つようになります。
結果として、自己成長の機会を逃し、職場や家庭での人間関係を悪化させ、ストレスや孤独感が増えるなど、本人にも周囲にも大きなデメリットをもたらします。
本章では、こうした他責思考の特徴や問題点を整理し、その背景や影響について詳しく見ていきます。
他責思考が強い人の行動例
他責思考が強い人には、いくつかの共通した行動パターンが見られます。まず典型的なのが、失敗やトラブルの原因を自分ではなく常に周囲に求める姿勢です。
- 「このミスは自分じゃなくてあの人のせい」
- 「このミスは自分じゃなくてあの人のせい」
- 「今の不幸は親のせい」
- 「給料が安いのは会社のせい」
など、身近な例に事欠きません。
こうした他責思考が強い人は、自分の非を認めようとせず責任を転嫁しがちで、問題が起きても主体的に解決に取り組まず「誰かが何とかしてくれる」と受け身になりやすい傾向があります。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
他責思考が強くなると起こる問題
他責思考が強い人は言い訳が多く、被害者意識を抱えやすいのも特徴です。自分の行動や選択に目を向けず、環境や他人に不満を募らせるため、怒りや苛立ちといった感情に支配されることも少なくありません。

それにね、謝るのがすごく苦手で『謝ったら負け』って思い込んでる人も多いの。最近よく言われる“謝ったら死ぬ病”って、その延長線上にある感じなんだよね。
こうした行動が積み重なると、周囲からの信頼を失い、チームの雰囲気や人間関係を悪化させるだけでなく、本人自身が自己成長の機会を逃し、ストレスや孤立感を深めるという悪循環に陥りやすくなります。
他責思考がもたらすデメリット
他責思考は一見「自分を守る」ための思考のように見えますが、実は本人にも周囲にも多くのマイナスの影響をもたらします。
特に「自分を守る」という思考が強い傾向になると、自分の非を認めず責任を外に押し付けることで問題解決が遅れ、成長のチャンスを逃してしまう危険があります。
また、被害者意識が強まり、怒りや苛立ちといったネガティブな感情に支配されやすくなり、結果として職場や家庭の雰囲気を悪化させることにもつながります。

他責思考がもたらすデメリットは以下の通りです。
- 自己成長の機会を失う(原因究明や改善策の模索を放棄してしまう)
- 人間関係・チームワークが悪化する(信頼を失いやすく孤立する)
- ストレスや不満が増大する(怒り・苛立ちなどの感情に支配される)
- 攻撃的な言動が増える(周囲から敬遠されやすくなる)
- 変化への対応が遅れる(柔軟な思考力・行動力が低下する)
- メンタルヘルスが悪化する(思考力の低下や心身の不調につながる)
こうした悪循環に陥らないためにも、自分の思考パターンを見直し「ほどよく自責・ほどよく他責」というバランスを意識することが大切です。

自分のせいじゃないって思ってばかりいると、なんで失敗したのかとか、どうしたらよくなるのかを考えなくなっちゃって、せっかく成長できるチャンスを自分で逃しちゃうんだよね。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
なぜ他責思考の人が増えているのか
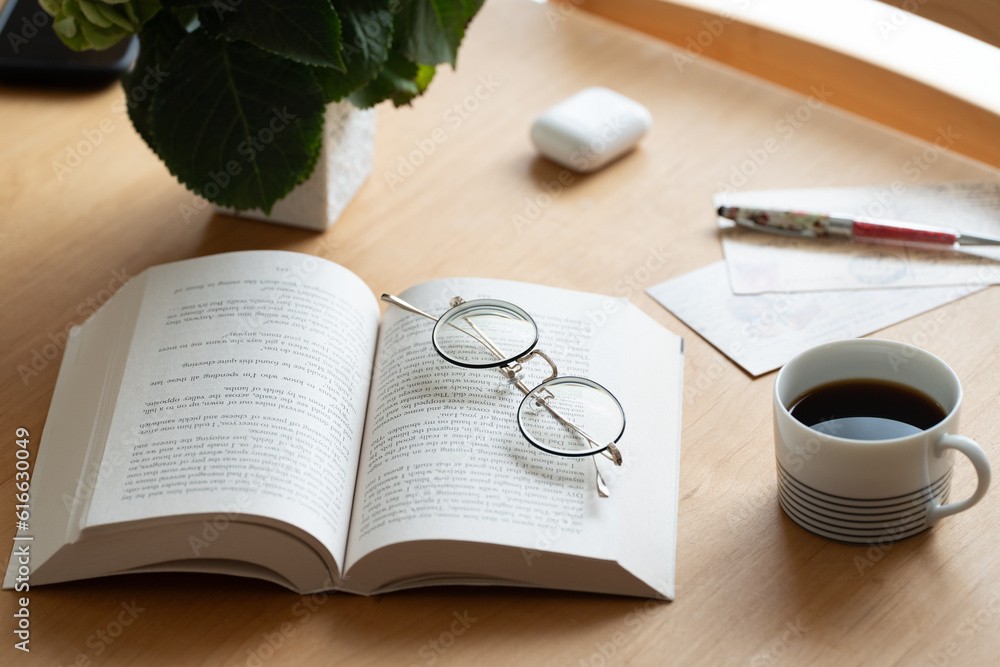
近年、「何でもまわりのせいにする」いわゆる他責思考の人が増えていると指摘されています。その背景には、現代社会特有の複合的な要因が絡み合っています。その一つに「核家族化」が挙げられます。
昭和の時代までは、ひとつ屋根の下に祖父母、父母、何人かの兄弟と住む生活が当たり前にありました。お盆や正月といった時期になれば、年齢が違う親戚が集まり、遊んだり話したりする中で、私たちはいろいろな世代や立場の人との距離感を自然と学んでいくことができたのです。
しかし、戦後、地方の若者たちが進学や就職で都会に出て行き、そのままそこで家庭を持つようになって、次第に核家族化が進んでいきます。このような住環境の変化によって、私たちは成長過程で他人との距離感を学ぶ機会が減ってしまいました。
引用:『何でもまわりのせいにする人たち』86ページより
時代の変化に加えて、現代は良くも悪くも人権意識が強くなりました。人との距離感や関係性を間違えると「ハラスメント」と糾弾されて社会的な立場を失うリスクも増えました。

多くの人が、他人とどうやって“ちょうどいい距離感”でつき合えばいいのか分からなくなって、その結果“ハラスメントって言われるかも…”って不安に思う人が増えているんだ。

相手に何を言われても、言い返さないで黙っていた方がトラブルにならずに済むって考えちゃうよね。
相手とのトラブルを避けて対人関係のトラブルを少なくする、という考えが広まった結果、「他責の発言を繰り返していても、誰も批判や訂正をしてくれない」という環境が出来てしまいました。
それゆえ、自分の他責思考に気づけずに他責がクセとなって定着し、どんどん先鋭化していく現象が行っていると言います。
SNSやインターネットの台頭
SNSなどインターネットの普及も大きな影響を与えています。匿名性の高い環境では、不満や批判を気軽に吐き出せるため、「自分は正しい、悪いのは他人」という構図が強化されやすくなります。
本書『何でもまわりのせいにする人たち』では、ネットの情報の伝達の速さと拡散力は、他責思考を強固にする要因となっている可能性が高いと解説しています。

ネットで同じような不満や批判に共感してくれる人が集まると、『世の中は自分の味方だ』って気持ちが大きくなって、結果的に『自分が言ってることは正義だ』って感じるようになって、他責思考がますます固定されちゃう傾向があるんだ。

「自分の意見は正しい、自分は正義だ」って思いこみをつくるSNSって不思議だね。同じ意見の人たちが集まって褒めあったりするから、他の意見に耳を貸さなくなるんだね。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
「年功序列」という価値観の弊害
今の高齢者が現役として働いていた時代は、「年功序列」という価値観が前提として社会に根付いていました。
年功序列という考え方を簡単に説明すると、「年上の人は、年上であるというだけで偉い。年長者は尊重されるべき」であるという価値観です。
高度成長期を支えてきたという強いプライドを持つ今の高齢者ほど、長年築いてきた経験や実績が評価されにくくなる現状に不満や孤立感を抱きやすく、それが被害者意識を強める要因になっています。

そこに“年功序列が当たり前”っていう価値観がくっつくと、『全部若者が悪いんだ』『自分たちの時代はこうだったのに』って気持ちが出てきて、自己責任より外のせいにする考えが定着しやすくなるんだよね。
こうした失望や不満、世代間ギャップが積み重なることで、結果として他責思考が固定化していくプロセスにつながっていくのです。
他責思考の人との上手な付き合い方

他責思考の人とかかわると、こちらが疲弊したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりしがちです。だからこそ、感情的に反応せず、冷静な距離感を保つことが大切です。
本書でも紹介されているように、他責思考の人は自分の癖に気づきにくいため、押し付けるような指摘ではなく、穏やかに気づきを促す声かけや、行動の結果を一緒に確認するなどの工夫が有効です。
相手を変えることよりも、自分が疲れない関わり方・環境づくりに意識を向けることが、長く健全な関係を保つコツといえます。

相手の言い分を頭ごなしに否定しないで、事実と気持ちを分けて受け止めるところから始めると良いかもしれないね。共感できるところは『そうだね』って短く共感を見せつつ、『じゃあ次はどうしようか?』『自分にできることって何かな?』っていう感じで解決の方向に話を切り替えると、相手が自分で考えるきっかけになるかもしれないんだ。

上から目線で相手に言ってしまったり、感情的にならないこともポイントだね。
“PR:アフリエイト広告を利用しています”
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
まとめ
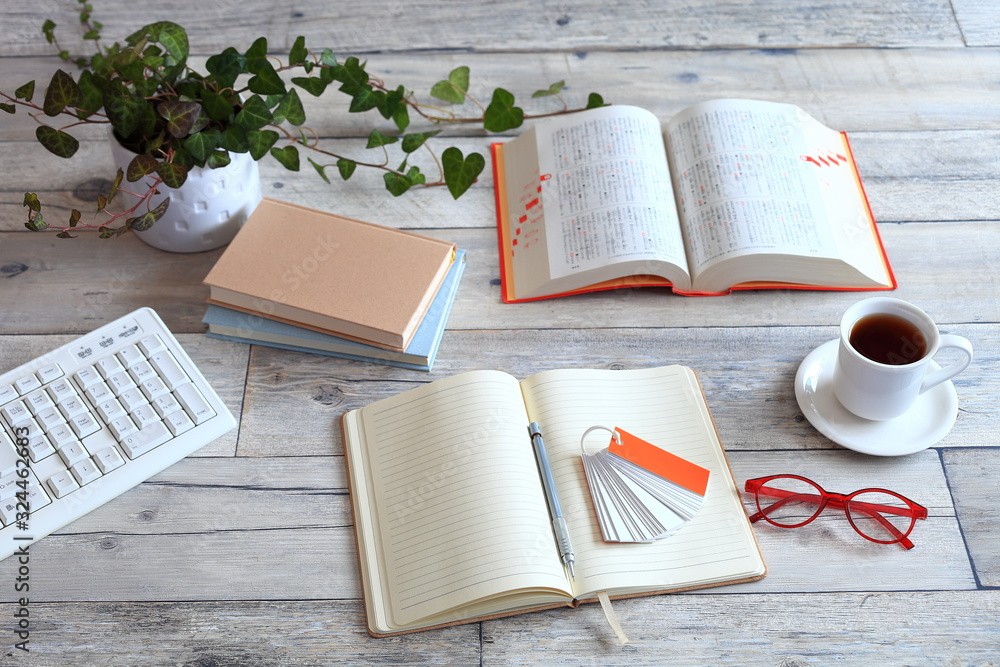
「他責思考」は、誰にでも少しは備わっている防御的な思考パターンですが、強くなり過ぎると自己成長の機会を失い、人間関係やメンタルにも悪影響を与えます。
本書『何でもまわりのせいにする人たち』(小日向るり子著)は、その心理的メカニズムや特徴、そして改善のヒントや周囲との上手な付き合い方までを丁寧に解説してくれる一冊です。
この記事では、他責思考の定義や背景、行動例、デメリット、増えている理由、そして付き合い方のポイントまでを整理しました。
大切なのは、相手を一方的に批判することでも、自分を過剰に責めることでもなく、「ほどよく自責・ほどよく他責」というバランスを意識することです。
こうした視点を持つことで、自分自身も他人との関係も、より健全でラクなものにしていくことができます。

本記事を読んで「他責思考」について気になったかたは、一度、本を手に取って読んでみることをお勧めします。本書では具体的な例や対処法も紹介されています。ぜひ、チェックしてみて下さい。

hontoの電子書籍ストアでも 『何でもまわりのせいにする人たち』 を購入可能です。気になった方はチェックしてみて下さいね♬
🎧 通勤中に“耳読書”で哲学を学ぶならAudible
👉 Audible無料体験はこちら
※Amazonのアソシエイトとして、当メディアは適格販売により収入を得ています。
【関連記事:メンターが老害化しないために|信頼される上司になるコミュニケーション術3選】
【関連記事:【最新版】「言語化力」を鍛えるおすすめ自己啓発本10選|思考を整理し、伝える力を磨く】
【関連記事:【初心者〜上級者別】「具体と抽象」を鍛える本5選|細谷功シリーズで読む順番ロードマップ】
“PR:アフリエイト広告を利用しています”