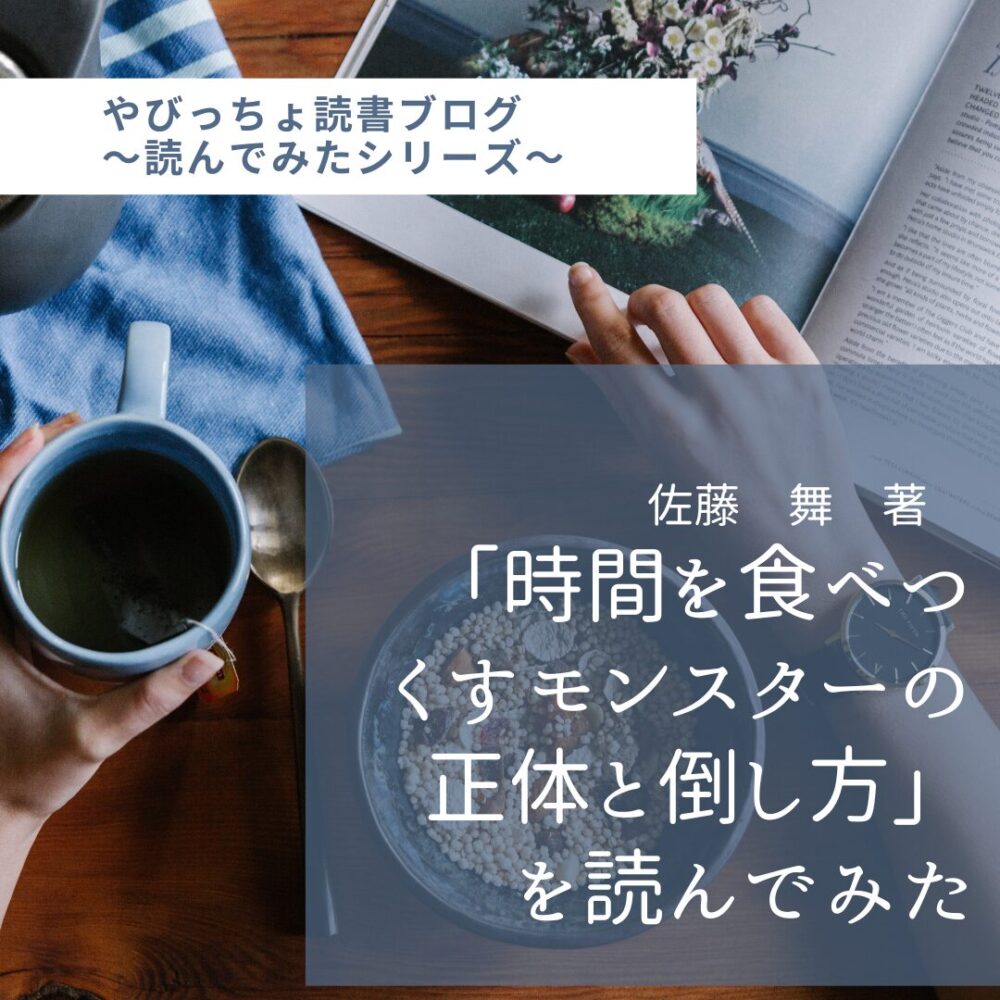休日の夕方、ふと時計を見て「あれ?今日はスマホを眺めていただけで終わってしまった…」と焦った経験はありませんか?
気づけば時間だけが過ぎ、やりたかったことに手をつけられないまま一日が終わってしまう。そんな後悔を抱いたことのある方は少なくないでしょう。
便利さの裏で、私たちの時間は少しずつ奪われています。佐藤舞さんの著書『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』は、この“時間を奪うモンスター”とどう向き合い、自分らしい人生を歩んでいくかを示してくれる一冊です。

「時間を奪うものからちょっと距離を置いて、もっと自分らしく、充実した毎日を過ごしたい!」──そんなふうに感じているキミに向けて、この本の大事なポイントを分かりやすくお話ししていくね。

パパ!それめっちゃ知りたい!スマホばっかり見ちゃって後で後悔すること多いから、この本のポイント聞けるの楽しみ♪
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
「死と太陽は直視できない」──人生の終わりを考えることから逃げていないか?

佐藤舞さんの著書 『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』 でも紹介されていますが、フランスの文学者フランソワ・ド・ロシュフコーは「死と太陽は直視できない」と語りました。
私たちは日々の生活に追われる中で、「人生の終わり」を意識することはほとんどありません。特に現代では、終末期を迎えた高齢者の多くが病院や老人ホームといった施設で過ごすようになり、身近で「死」と向き合う機会が減ってしまいました。
そのことが、私たちが人生の有限さを直視しづらくしている要因のひとつだと考えられます。
多くの人は、死と太陽という本質を見ることを避け、代替案として選んだ選択肢を正当化することに時間を使っているのではないでしょうか?
私たちが直視できないものとはなんでしょうか。
私はそれを、「人生の3つの理(ことわり)」だと考えました。
人生の3つの理
①死 ②孤独 ③責任
引用:『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』57ページ
本書では、人は「人生の3つの理」を直視したくないあまり、無意識のうちに自分に嘘をつき、行動をごまかしてしまうと説かれています。
この“ごまかしの行動”こそが、私たちの時間を奪うモンスターの正体だと指摘しているのです。

たとえば「人生の3つの理」をGPS機能にたとえると、イメージしやすいと思うんだ。目的地と地図、それにコンパスが揃っていても、もしGPSがバグっていたらどうする?今自分がどこにいるのか、どこに向かえばいいのか分からなくなって、同じところをグルグル回って時間ばかり無駄にしちゃうよね。

だからこそ、しっかりと、「人生の3つの理」を理解する必要があるんだね!
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

不安から逃れるために人がとる行動とは?
本書では、人が「人生の3つの理」から目を背けるときに、どんな行動をとるのかが具体的に示されています。
①死の不安:何かに没頭したり熱中して悩まないようにする
⇒ ワーカホリックになる
②孤独の不安:友人やパートナーを探して寂しさを紛らわせる
⇒ 浮気を疑って何度もスマホをチェックする
③責任の不安:他人に決めてもらうことで責任を回避する
⇒ 周囲に同調して自分の意見を言わない
引用:『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』64ページより一部編集
本著『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』では、これらの行動を「不安を消す」と言う意図以外にも、「正当な理由付け(ウソ・いいわけ)」ができるということにも言及しています。
ワーカホリックになる = 仕事をしないと家族を養えないから
浮気を疑って何度もスマホをチェックする = 疑われるようなことをする相手が悪いから
周囲に同調して自分の意見を言わない = 自分の判断に自身がないから
引用:『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』65ページより一部編集
自らの偏見や信じていることを肯定するような証拠を見つけ、自己正当化し「他責思考」に陥ることを「自己欺瞞」といいます。

自分では『これが正しい!』とか『これが私のポリシー!』って思ってても、実はごまかしてばっかりで…気づいたら人生ムダにしちゃってることってあるんだよね〜。

そして死を前にしたときに、「ああ…あれをやっておけばよかったな…」って後悔するって、この本では書かれているんだ。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
なぜ人は「自己正当化」に逃げてしまうのか?
なぜ人は自分の本心や本当に望む行動ではなく、代替の行動に逃げて「自己正当化」してしまうのでしょうか。
その理由を一言で言えば、「傷つきたくない」から、あるいは「失敗が怖い」からです。
そして、その根底に流れているのは「責任を取りたくない」という思い。
「もし責任を負うくらいなら、今の不自由な暮らしのままで構わない」──そう無意識に考え(あるいは考えないようにして)、現状にとどまってしまうのです。

ベストセラー作家で世界にも読者が多い村上春樹さんは、「日本人はそれほど、自由を求めてはいない、または自由が制限された生活に不愉快さを感じていないということ」に気がついたそうです。「むしろ安心感のために、彼らは自分で自分の自由を制限している」と、話されています。
「責任 → 孤独 → 死」という順番で突きつけられる現実
こうして人は、「責任を取りたくない」という思いから自己正当化に逃げ、現状にとどまります。
けれども、人生の中ではいずれ、そのツケを払わされる瞬間がやってきます。
本書では、それが 「責任 → 孤独 → 死」 の順番で突きつけられると解説されています。
たとえば──
- 自分の意見を言わず、周囲に合わせてばかりいた結果、家庭や職場で大きな問題が起こり、避けてきた「責任」を突きつけられる。
- その結果、人が離れていき、「孤独」に直面する。
- そして最後には、望んでいた終活や人生の幕引きができないまま、「死」と向き合わざるを得なくなる。

私たちってさ、『傷つきたくないな』とか『失敗するの怖いな』って逃げちゃうけど…結局それって、あとで大きなしっぺ返しになって返ってくるんだね…
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

モンスターに立ち向かう3つの武器

ここまで『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』を読み解きながら、「時間を奪う正体」について解説してきました。時間を食べつくすモンスターと戦うためには3つの武器が必要だと説きます。
第一の武器は自己覚知。自分の感情や価値観に気づき、受け止めることで、自分を客観的に理解できるようになります。
第二の武器は価値観の明確化。人生の軸となる価値観を知ることで、迷わず選択できるようになるのです。
そして第三の武器は諦める(あきらかにきわめる)力。困難に直面したときに、できない理由や限界を認め、本質を見極めて次の一歩を選ぶ思考です。

モンスターと戦うための3つの武器かぁ~!なんだか、むずかしいなぁ。

ここでは、3つの武器について具体的に解説していこうね。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

モンスターに立ち向かう3つの武器その①:自己覚知を行う
本書『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』の中では「自己覚知」という言葉そのものは使われていませんが、それに近い概念が紹介されています。
自己覚知とは、「自分自身を深く理解し、内面や性格、感情、価値観、欲望について気づきを持つこと」を指します。
これはまさに自分自身と向き合う行為であり、成長や変化への第一歩といえるでしょう。
自己覚知が進むことで、自分の強みや弱みを一歩引いた視点から見つめ直せるようになります。
その結果、日々の生活や仕事、人間関係にも良い変化をもたらすことができるのです。
本書では、その具体的な方法として以下の3つが挙げられています。
- 気づく(マインドフルネス)
- 受けれいれる(アクセプタンス)
- 重要なことに取り組む(コミットメント)
①「気づく」(マインドフルネス)では、今、起こっている出来事、自分の感情、認知、行動、身体反応に気付く(これを『自己覚知』と言います)。
②「受け入れる」では、気づいたことを「良いこと」・「悪いこと」とジャッジするのではなく、ありのままを受けれる。
③:重要なことに取り組む(コミットメント)については、人によって対応が違ってきますが、自分にとって価値あることに意識的に時間やエネルギーを注ぐことを指します。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》

モンスターに立ち向かう3つの武器その②:価値観を明確にする
少し抽象的な言い方になりますが、自分の人生を歩むうえで、「価値観」ほど大切な指針はないと思います。
人それぞれの価値観は、生まれ育った家庭環境や、人生の中で経験したさまざまな出来事から形づくられていきます。特に「困難」と呼ばれる出来事にどう向き合ったのか、どのように捉え、どんな感情を抱いたのか──そのプロセスこそが、その人の価値観を大きく左右します。
つまり、価値観とは単なる考え方の違いではなく、その人がどのように人生を受け止め、進んでいくのかを示すコンパスのような役割を果たしているのです。
例えば、「信じる」という価値観ひとつとっても、芦田愛菜さんのエピソードが本書に書かれているので引用します。
(中略)女優の芦田愛菜さんが、主演映画の完成告知イベントで「信じる」ということについて、大変示唆に富むコメントをされていました。
「『その人のことを信じようと思います』っていう言葉ってけっこう使うと思うんですけど、『それがどういう意味なんだろう』って考えた時に、その人自身を信じているのではなくて、『自分が理想とする、その人の人物像みたいなものに期待してしまっていることなのかな』と感じて」
「だからこそ人は『裏切られた』とか、『期待していたのに』とか言うけれど、別にそれは、『その人が裏切った』とかいうわけではなくて、『その人の見えなかった部分が見えただけ』であって、その見えなかった部分が見えた時に『それもその人なんだ』と受け止められる、『揺るがない自分がいる』というのが『信じられることなのかな』っておもったんですけど」
「でも、その揺るがない自分の軸を持つのはすごく難しいんじゃないですか。だからこそ人は『信じる』って口に出して、不安な自分がいるからこそ、成功した自分だったりとか、理想の人物像だったりにすがりたいんじゃないかと思いました」
引用:『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』214ページより
彼女の言葉を読み解くと、「信じる」とは単に相手を理想化することではなく、「覚悟を決めること」だと言えるのではないでしょうか。
つまり──
「この人を信じると決めたのだから、その人がどんな答えを出そうと受け止める。たとえ自分が思っていた結果と違っても、それは“信じた人の新しい一面を見られた”というだけのこと。」
そう捉える姿勢が「信じる」という行為の本質なのです。

それにね、芦田さんが言ってた『だから人は“裏切られた”とか“期待してたのに”って言うけど』ってところからもわかるように、彼女って起こったことを“良い”とか“悪い”とかで決めつけてないんだよね。

むしろね、起こったことをそのまま受け止める姿勢を持ってて、これって本にも出てくる“受け入れる(アクセプタンス)”の実践そのものなんだよね。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
モンスターに立ち向かう3つの武器その③:諦める(あきらかにきわめる)
本書『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』では、「あきらめる(諦める)」という言葉を「何ならできるのかを見極める(あきらかにきわめる)」という意味で解説しています。これは本来の言葉の背景とも深くつながっています。
そもそも「あきらめる」とは、仏教用語の「諦観(たいかん)」が由来で、**「物事の本質をしっかりと見極めたうえで、受け入れること」**を意味します。

ただ投げ出すんじゃなくてさ、『なんでできないのか』『原因はどこにあるのか』っていうのをちゃんと認める姿勢のことなんだよね。

人生を歩いてるとさ、自分の価値観に向かって頑張ってても、どうしても困難にぶつかって『あ、これできないな』って直面する瞬間って絶対あるんだよね。
そのときに大切なのは、ただ諦めるのではなく、「諦観」=物事の本質を理解したうえでの選択です。
この「諦観」という姿勢は、少し堅い表現ではありますが、人生をより生きやすくするための大事な考え方であり、本書が説く「ブレイクスルー思考」にも通じています。
【あきらめるの意味を知る:「諦観」「諦念」「達観」の意味の違いと使い分け – WURK[ワーク]】
まとめ:人生という旅を進むために

ここまで『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』を読み解きながら、「時間を奪う正体」について解説してきました。
私たちの人生を旅にたとえるなら、必要なのは「地図」「目的地」「コンパス」、そして「GPS機能」です。
地図は世の中の仕組み、目的地は自分の夢や目標、コンパスは価値観、GPSは「人生の3つの理(死・孤独・責任)」を正しく直視する力です。
これらがそろえば、自分の現在地を見失わず、迷うことなく歩みを進めることができます。
本書『時間を食べつくすモンスターの正体と倒しかた』が伝えるのは、時間を奪う存在に流されるのではなく、自分の価値観を軸に選択を重ねていくことの大切さです。
不安から逃げるのではなく、受け入れ、見極め、覚悟をもって進むこと。そうして初めて、自分らしく充実した人生という旅を歩むことができるのです。

具体的な対処法については本書により詳しく書かれています。気になる方はぜひ手に取って、自分自身の人生に重ねながら読んでみてほしいと思います。

『あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方』は honto の電子書籍(e-book) で購入できます!気になったかたは一度、チェックしてみて下さいね♬
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
【関連記事:【初心者〜上級者別】「具体と抽象」を鍛える本5選|細谷功シリーズで読む順番ロードマップ】
【関連記事:『読んだら勉強したくなる東大生の学び方』で学ぶ!人生をより良く生きる論理的思考法】
【関連記事:【最新版】「言語化力」を鍛えるおすすめ自己啓発本10選|思考を整理し、伝える力を磨く】