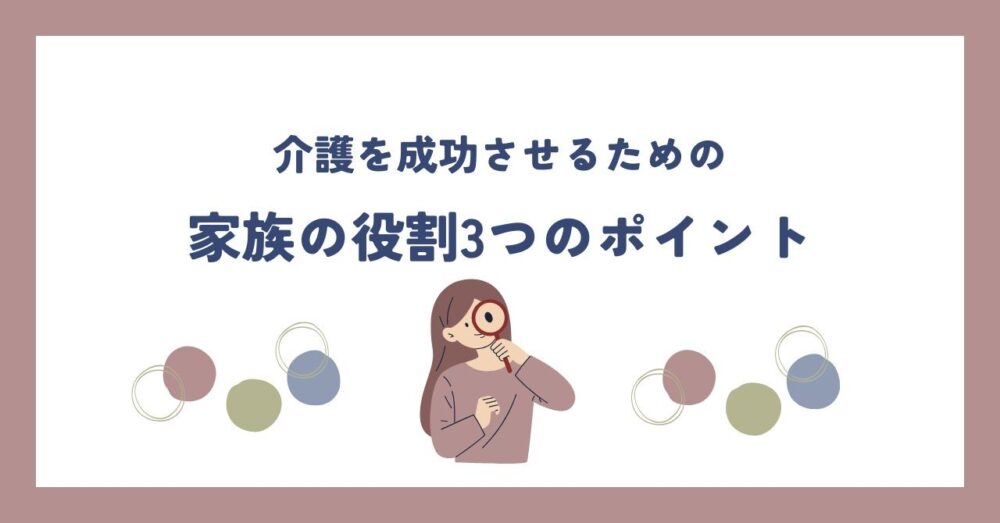ご両親の入院や病気・けがをきっかけに介護が始まることになったと、慌てるかたもいらっしゃると思います。「自分の親はまだまだ元気で介護なんて遠い先の未来のことだと思っていた」、「いきなり介護と言われても、家族として何をしたら良いのかわからない」などと、悩むことはありませんか?

今度、体調を崩して入院していましたが、リハビリを終えて親が退院して自宅に帰ってくることになりました。この前、ケアマネージャーさんと初めてお会いしましたが、これからどうしたら良いのかよくわかりません。
介護をするうえで家族の役割はとても重要です。今回は、「両親の介護が始まった」など、とつぜんの環境の変化にとまどう…そんなあなたに向けて、「介護を成功させるための家族の役割3つのポイント」について記事を書きました。
【関連記事:理想のケアマネージャーの探し方について】
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
この記事を読んでわかること

本記事は、「親御さんの介護が始まる」というかたに向けて書かれた構成内容となっています。一番初めに伝えたいことは「ケアマネジャーは、親御さんである利用者そして支える家族の味方」であることを覚えていてください。
介護の負担は人によってそれぞれですが、介護で困ったときや負担が重たい時にケアマネジャーと信頼関係を作ることで負担を少しでも軽減できると思います。その点を踏まえて、「この記事を読んで解ることは下記の3つ」です。
- 介護をするうえで家族の役割3つのポイントについてわかります
- ケアマネージャーとのかかわり方について理解が深まります
- ケアマネジャーが信頼できない、相談ができない!そんな時の対処法がわかります

沖縄県で独立型の居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが働く事務所)を運営しながら、ケアマネージャーとしても勤務しています。実際に私も現場で働いていて、家族(キーパーソン)との連携の取り方しだいでケアの質も変わってくると実感しています。
本記事で紹介する内容を読めば、「これから介護を始める」という方でも、家族の役割としての理解が深まる構成となっています。
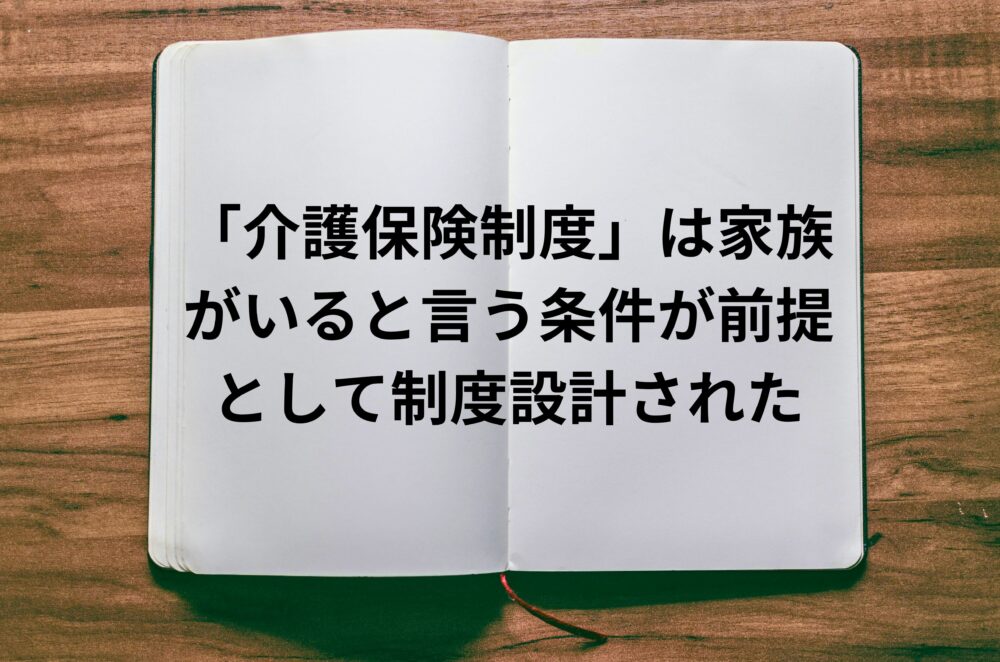
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟

介護を成功させるための家族の役割3つのポイントとは?
介護をするうえで「介護保険サービス」を利用することは、利用者の生活を維持することと併せて、家族の介護負担を軽減する上では必要な制度だと言えます。
ここで、知っておきたいことは「介護保険制度は家族がいると言う条件が前提として制度設計された」と言うことです。

子どもはまだ小さいです。親の介護もしてあげたいのですが、どうしたら良いのかわかりません。

いきなり、親の介護が必要だと言われても困るよ!ウチで引き取るにも色々考えなければいけないこともあるし…
介護をするうえで、家族の役割がなぜ重要なのか?と言うところから解説していきます。介護における知識や、介護への負担を軽減する上で、家族の役割は多岐にわたります。ここでは、家族の役割を大きく3つに分けて解説します。家族の役割とは下記の3つになります。
- 情緒的なサポート
- 医療面のサポート
- 契約、金銭管理のサポート
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
その①:情緒的なサポートが大事
介護保険では、ヘルパーによる生活援助や身体介護、リハビリを兼ねた外出支援のサポートに対して、訪問介護やデイケアなど専門的な介護者によるケアを行います。
ですが、利用者に対して話し相手になったり、心の支えになるといった精神的なサポートに対して介護保険では限界があります。そこで、情緒的な面においては家族のサポートが必要になります。
注意しなければならない点として、「介護をするうえで、親と同居すべきだ」などと決めつけや強制する訳ではないということです。
今は、電話だけでなくlineやオンラインでコミュニケーションを取ることが出来る様になりました。「自分のできる範囲」で構いません。電話やちょっとした時間で親御さんとのコミュニケーションを大切にされると介護への負担も軽減できると思います。

不安なときや、寂しいときに子供たちの電話や顔を見せに来てくれるのはありがたいねぇ~
その②:医療面のサポートについて
病院への通院付き添いや主治医と治療についての相談。お薬の管理や検査時の対応など、歳をとると一人では対応が難しくなります。
日々の状態観察も含めて利用者の健康管理をサポートする上で家族の協力が必要になります。どうしても親御さんと距離的に離れていてサポートが難しいなどの場合には、ケアマネジャーやお住いの地域包括支援センター、または自費サービスなども検討されても良いと思います。

よく聞かれる質問で「病院受診の付き添いを介護保険で利用したい」と、問い合わせを受けますが、介護保険で病院からの送迎や院内の付き添いまですべてを対応してくれるサービスはありません。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟

その③:契約・金銭管理などの社会的サポートについて
施設への入居や介護事業所との契約や利用料の支払い。また、入院の際の手続きや準備など、利用者を法的に守る意味からも契約や身元保証人として家族のサポートが必要になります。
金銭管理に関しては、デリケートな問題でもあるため、ご家族としてサポートが難しいなら、早めに担当ケアマネジャーやお住いの地域包括支援センターへ相談されることをお勧めします。

子供たちが近くにいないので、民間の身元保証人サービスに問い合わせたら高額な値段を請求されて困りました。子供たちが近くにいてくれたらこんな心配はしなくても良いのにのぅ
【関連記事:地域包括支援センターとは|役割や相談事例、利用方法を紹介【介護のほんね】】
※POINT:病院受診の付き添いサポートや身元保証人サポートに関しては、自治体の独自のサービスや、自費対応(介護保険外サービス)を実施している地域もあります。お住いの地域包括支援センターへ一度ご確認ください。
ケアマネージャーとの連携3つのポイントについて

家族が介護をするうえで、利用者だけでなく家族の介護負担軽減を図る上ではケアマネージャーとの円滑なコミュニケーションは不可欠です。

ここでは、ケアマネージャーとのコミュニケーションの取り方について解説していきますね
- 定期的にケアマネージャーとコミュニケーションを図ろう
- 家族の役割分担を明確化しよう
- ケアマネージャーにとって家族に対する感情的なサポートは大事なお仕事です
その①:定期的にケアマネージャーとコミュニケーションを図ろう
ケアマネージャーはケアプランを作成するにあたって利用者や家族と一緒にケアプランを策定していきます。家族は、利用者が伝えきれない思いや日常の詳細な情報を、ケアマネージャーに伝えることで計画づくりに一緒に参加していく役割があります。

ケアプランってケアマネージャーの意向だけで立てると思っていました。家族の要望を伝えても良いのですね。

足腰が弱っていたので、リハビリを頑張りたいと思っていました。私の要望を聞いてくれて助かりました。

離れた親のところへ通うくらいなら、ウチへ呼んで介護をしようかと考えました。リハビリを続けたことで自分の住み慣れた家で生活を続けられそうです。
介護サービスが始まると、定期的にケアマネージャーとの面談が始まります。専門用語でモニタリングと言います。利用者や家族が定期的にケアマネージャーと顔をあわせることで信頼関係づくりと正確な状況を把握する機会にもなります。
※POINT:ご家族は、ケアマネージャーへ利用者の日々の状態や日常の変化を伝えましょう。介護サービス事業所や病院などの連携のかなめであるケアマネージャーに情報を提供することで各事業所との連携が図れます。そのことで、より良いサービスの提案や、質の高いケアが提供されます。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
その②:家族の役割分担を明確化しよう
家族が介護をするにあたってどのような役割を担うかを明確にすることは大切なプロセスです。今まで何気なく行っていたことも重要な役割だったりすることもあります。
例えば・・・

仕事帰りに自宅によって両親の顔を見に行っているんだけど、こんなことも家族の役割になるのかなぁ?

もちろん!大切な役目です。利用者の立場からすると、精神的な支柱になっていたりすることもあります。ご自身の役割の明確化と責任を理解することが重要です。
※POINT:ケアマネージャーは家族に対して専門的なアドバイスやサポートを提供する役割があります。わからないことは積極的にケアマネージャーに質問することで信頼関係が構築されます。遠慮なく質問してくださいね!
その③:ケアマネージャーにとって家族に対する感情的なサポートは大事なお仕事です
介護は家族にとって、大きなストレスや負担になることが多いです。ストレスや負担をケアマネージャー話すことで感情的なサポートをしてもらうことも大事な作業です。
たとえ、介護負担を軽減できる介護サービスやサポートが無かったとしても、誰かに話を聞いてもらうだけでストレスや負担は軽減できることが多いです。

ケアマネージャーさんには、誰にも言えない介護への愚痴も親身に聞いてくれるので、ついつい話し込んじゃいました。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
※POINT:家族が介護をするうえで、ケアマネージャーとの円滑なコミュニケーションは不可欠です。気軽に相談できる関係性を作れることが介護へのストレスや負担軽減になると言えます。
さいごに

今回、介護保険発足の歴史から、介護をするうえで家族の役割について話してきました。また、家族がケアマネージャーとのコミュニケーションを上手く取ることで介護の質も変わってくると説明しました。ケアマネジャーの中には経験が浅く知識も不足しているかたもいると思います。
知っていてほしいことは「ケアマネジャーは変更ができる」ということです。知識や経験だけではなく、ケアマネジャーと利用者及びご家族の相性もあります。変更を申し出ることも介護の質をあげる上で一つポイントになると思います。
一方で、ケアマネジャーというお仕事は、目に見えない裏方の仕事も多く抱えています。利用者のケアを調整するため、医療機関や事業所などとの連絡調整は業務の中でかなりの比重を締めます。
その中で、ケアマネジャーは利用者や介護をされるご家族が「少しでも良いケアができる」ように裏で表で努力していることも知っていて下さると、とてもありがたいです。

ケアマネージャーは、利用者はもちろん介護をされるご家族の味方です。信頼関係を築くことで少しでもより良い介護が出来ることを願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。また、次の機会によろしくお願いします。
〝PR:アフリエイト広告を利用しています〟
【関連記事:『尾石晴著、「40歳の壁」を越える人生戦略』を読んで考える~一生モノのキャリアを構成する3つのポイント~】
【関連記事:「ミッドライフ・クライシス」教養論~50歳から何を学ぶか?~】
【関連記事:「老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」を読んでわかった高齢者が直面する3つの課題】
【関連記事:「老後ひとり難民」を読んでわかる独居高齢者が直面する3つの課題】