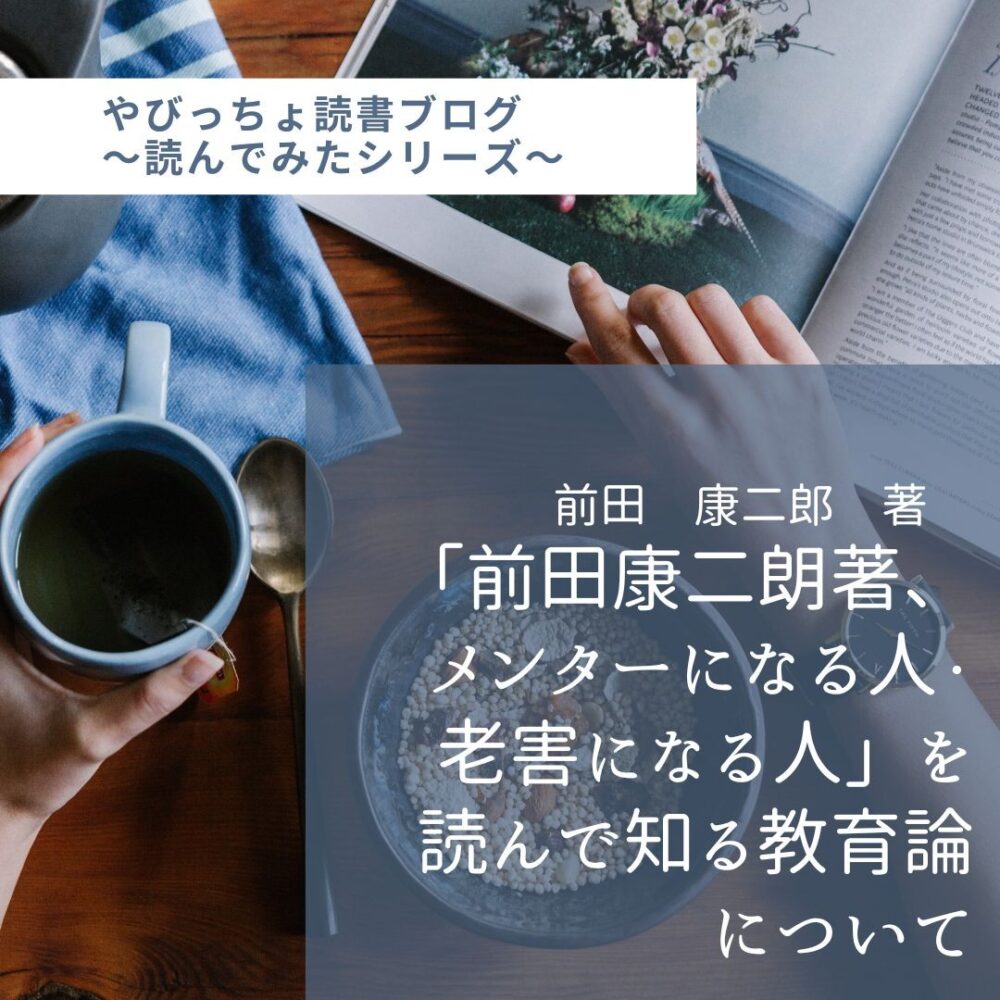40歳を過ぎたビジネスパーソンにとって、
「良き上司」や「良き先輩」であり続けることは簡単ではありません。
「気づいたら若手から距離を置かれている気がする…」
「昔は通じていた話し方が、今はなぜかうまくいかない」
「指導したつもりが“老害”と言われていたらどうしよう…」
40代・50代が仕事で必ず直面するテーマ、それが**“老害化”の問題**です。
しかし、誤解しないでください。
老害とは「歳をとったら自然とそうなる」わけではありません。
そして実は、20代でも30代でも老害になりうると言われています。
つまり老害化は“年齢の問題”ではなく、
「コミュニケーションのズレ」から起きる現象なのです。
前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』は、
自分の言動が「老害」とならないように
セルフチェックしつつ、メンターとして信頼される存在になるための教育論を示す一冊です。
この記事では、
- 老害とは何か
- 老害と呼ばれないための3つの話し方
- 若手から信頼されるメンターに共通する行動
- 性格統計学に基づく、タイプ別の伝え方
- 伝える力を伸ばせる資格「伝え方コミュニケーション検定」
これらを体系的にまとめ、
今日から使える“老害回避のコミュニケーション術”として解説します。

この記事では『メンターになる人、老害になる人』の概要とポイントを整理したうえで、「信頼される上司になるコミュニケーション術」3選を紹介します。

パパ!伝える力を伸ばせる資格「コミュニケーション検定」も気になる♪しっかり学んで話し上手になりたいな~。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
1|なぜ今「老害問題」が深刻になっているのか?

前田康二朗著、『メンターになる人、老害になる人』は、
ビジネスパーソンにとっての理想像を描いた一冊です。
著者はまず、「成果や実績を出すことが求められる」と解説します。
そのうえで、部下や後輩から信頼される「メンター」を目指し、
逆に「老害」と呼ばれる存在に転じないようにすることが重要だと説いています。
「老害」という言葉が急増した背景には、
価値観の多様化とコミュニケーション距離の変化があります。

今と昔では、価値観やコミュニケーションが
どのように多様化したのか?見ていこうか。

昔と今では職場の立場や
コミュニケーションの取り方も違っているんだね~
昔:上下関係が強く、指示型のコミュニケーションが主流
昔、(昭和~平成)の職場と言えば、上司の立場は絶対的でした。
「郷に入っては郷に従え」という言葉通り
部下は上司の背中を見て学ぶというスタイルが主流でした。
- 上司の言うことは絶対
- “正しいやり方”は上司が決める
- 若手は質問よりも「背中を見て学ぶ」文化

最近『老害』が増えた背景には、
終身雇用とか年功序列が崩れて、
中途採用が増えたことも関係してるんだよね。
そういうのも一因って言えると思うんだ。

昔みたいに、同じ会社でずっと働く人って減ってるって
学校の先生も言っていた。
いろんな世代や価値観の人が入り混じるから、
ぶつかることも増えるのかもしれないね。
今:価値観が複雑化し、 “対等性”が求められる
近年の社会では、
「年上の部下」「年下の上司」
という立場が珍しくなくなってきました。
価値観が複雑化したことによって、
“対等性”が求められることも重要なポイントとなりました。
- 若手は「納得」できない指示には動かない
- SNSで情報が開かれ、誰でも学べる
- 多様性(ダイバーシティ)を重視
- 効率より心理的安全性が優先される場面も多い
つまり、
かつて普通だった指導方法が、今は老害と捉えられやすいのです。
そしてもうひとつ重要なポイントがあります。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
2|老害とは“年齢”ではなく“態度”の問題である

本書『メンターになる人、老害になる人』では、
老害が生み出されるメカニズムとして、
『老害の構成軸』として、詳しく解説されているので引用します。
老害の構成軸
- 生きてきた年数(年齢)
- 特定の組織に所属してきた在籍年数(会社、団体、地域コミュニティなど)
- 特定の専門分野の実務経験年数(営業歴、製作歴、編集歴、人事歴、経理歴、教師歴、作家歴、野球歴、など)
- 組織のポジションの経験年数(社長、部下、理事長、編集長、など)
これらの年数が長いほど、その人が周囲から「メンター」となる要素もあれば反対に「老害」となる危険性もあるわけです。
引用:「メンターになる人、老害になる人」17ページより
老害を構成する要因として、年齢や組織に属した年数がかさむごとに
「メンター」になる要素と共に「老害」となる危険性もあると解説します。
老害の特徴
具体的に、老害とされる人の特徴には、共通項があります。
- 過去の成功に固執する
- 正解を押しつける
- 相手を「下」に置く話し方
- 否定スタート
- 価値観の違いを理解しようとしない
- 「俺の若い頃は」を多用する
- 時代の変化を軽視する
実はこれ、何歳でも当てはまるのです。
いわゆる“逆老害”(20〜30代の老害化)も指摘されており、
「若いのに老害」になっている人もいます。

正直さ、『老害』って言われる人こそ、仲間外れにされたり疎外感を持っちゃうと、逆に周りに悪影響ばっかりまき散らして、余計に面倒なことになっちゃうんじゃないかなって思うんだよね。

人って認めてもらえないと拗ねちゃったり意地張っちゃったりするよね。だからこそ、ちゃんと関わり方を工夫するのって大事なんだと思うな。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
3|老害の対義語は“メンター”である
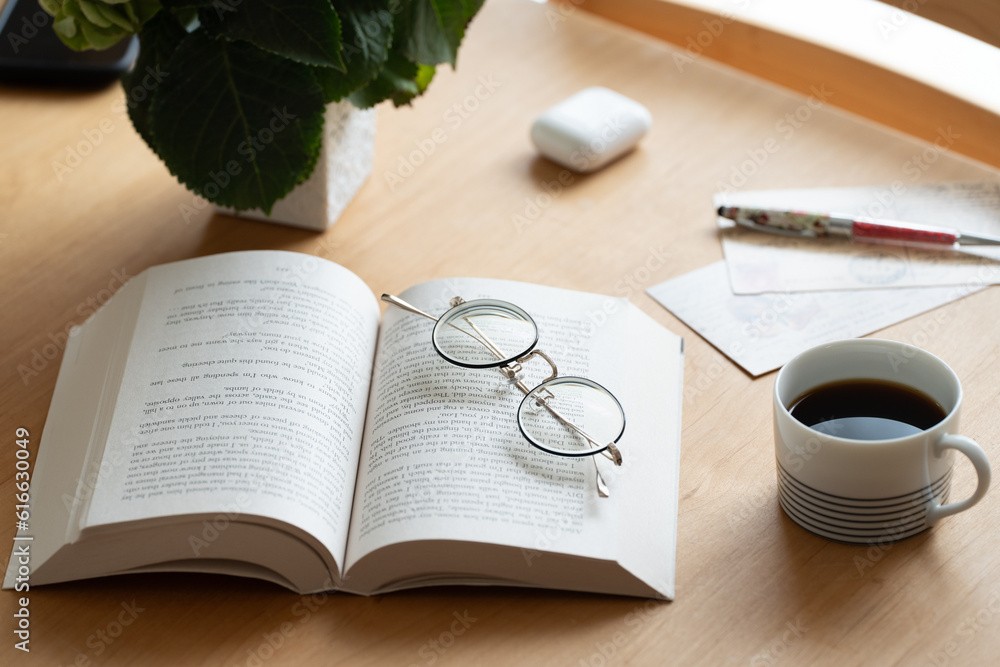
ここで改めて、「メンター」という言葉の定義を確認してみましょう。
辞書によると、メンターとは
「良き指導者。優れた助言者。恩師」 を意味します。
つまりメンターとは、単に知識や経験を教える存在ではなく、
相手に寄り添い、前向きな成長を後押しする人のことを指すのです。
メンターのイメージ象
ビジネスの現場では、部下や後輩に安心感を与えつつ、
信頼されるリーダー像として「メンター」の役割がますます求められています。
「日本メンター協会」ではメンターのイメージを次の様に挙げています。
メンターのイメージは、それぞれ、人によって、組織によって違うと思われます。訳語としては、「支援者」「助言者」とされることが多いです。 メンターに特定なスキルや知識を求めるのであれば、その領域に知識・スキルを持ち、その実績があり、いろいろと経験している人をイメージするかもしれません。しかし、多くの人のイメージは、「いろいろなことを安心して相談できて、前向きな気持ちにさせてくれる人」というイメージでないでしょうか。以下に、メンターのイメージを具体的に、6つ挙げてみます。
① 仕事の面でも、プライベートの面でも安心して相談できる人。
② どのような相談でも、共に悩み、考え、支え、称えてくれる人。
③ できる範囲で、有形無形問わず、力になってくれる人。
④ 特別に振る舞うことはせず、ありのままの態度で接してくれる人。
⑤ 同じ目線で、フラット(対等)な立場で対話してくれる人。
⑥ メンティーと共に、成長する人
※ メンターに支援してもらう立場の人を、メンティー(プロテジェ)と呼びます。
引用:メンターとは?メンター像には、目的別に2つの類型がある – 日本メンター協会

個人的にはね、メンターのイメージで出てきた
⑥の『同じ目線で、フラットな立場で対話してくれる人』
ってところに、すごく感銘を受けたんだ。

先生もそうだよね!
叱るように話すんじゃなくて、
ちゃんと同じ立場で話してくれる先生って
とても安心感があるし、素直に話せるんだよね。
老害とメンターは同一人物の中に共存しうる
メンターの定義として、要点をまとめると以下の点が挙げられます。
- 相手の成長を後押しする
- 同じ目線で対等に対話する
- 押しつけず、気づきを促す
- 心の安全基地になる
- 感情的に否定しない
- 相手に寄り添いながらも、必要な助言は明確に伝える
ここで重要なのは、
老害とメンターは同一人物の中に共存しうるということ。
本書『メンターになる人、老害になる人』では、
面白い気付きが書かれています。
そこで私は気付きました。「老害」の対義語は「メンター」(仕事、キャリア、ライフプランなどについて助言をしてくれる、信頼のおける相談相手)なのだということにです。
「老害」と言われてしまう人と、「メンター」と呼ばれるような人、これを別々にイメージすると、前者と後者は全く似ても似つかない別人格の人物を想像することでしょう。しかしそうではなく、老害を引き起こす人とメンターとして尊敬される人は実は「同一人物」の場合もあるのです。
引用:「メンターになる人、老害になる人」3ページより
人は誰もが、
調子の悪い日は老害化し、
余裕がある日はメンターになれます。
だから必要なのは、
自分自身のセリフを常にセルフチェックする習慣です。
そして、そのチェックポイントとして最も使えるのが、
これから紹介する**“老害と呼ばれないためのコミュニケーション術3選”**です。

本来はメンターとメンティーって“対等”であるべきなのに、
気づいたら一方的にメンターが上から目線になっちゃって、
結果的に『老害』っぽくなっちゃうこともあるんだ。

“良かれと思って”のアドバイスでも、
受け取る側からすると押しつけに感じちゃうことってあるもんね。
対等な関係を意識するのが大事なんだね。
※POINT:人は老害にもメンターにもなりえる可能性があることを理解する
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
4|老害と呼ばれないためのコミュニケーション術3選

ここでは、メンターであっても注意しなければ陥りやすい
「老害」と言われないためのコミュニケーション術について解説していきます。
前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』によれば、
老害と指摘されやすい人の話し方には、
一定の「くせ」や型(フォーマット)があるとされています。
その典型例が以下の2つです。
- 利己的な決めつけや断定をする
- 「Aは優れているがBは劣っている」という対比で優劣をつけたがる
この2つを組み合わせたような話し方をすると、
周囲から「老害的だ」と受け取られてしまうリスクが一気に高まります。

「そんなつもりで言ったのではない」と後から弁明しても後の祭りです。
以下に解説する要点に気を付けながら
「老害」に陥らないためのコミュニケーション術を学んでいきましょう。
その①:正しいか、正しくないかで論じない
前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』では、
客観的に正誤が証明できるものは指摘しても問題ないと説明しています。
たとえば…
- 「計算結果が間違っていた」
- 「禁止事項に触れてしまった」
といったケースは、
事実に基づくため指摘してもトラブルにはなりにくいのです。
一方で注意すべきなのは、
正解が一つに定まらない話題や、解決方法が複数存在する問題に対して
「正しいか/正しくないか」で論じてしまうこと。
これは非常に危険で、思わぬ摩擦や誤解を生む原因となります。
つまり、正誤を断定するのではなく
「多様な考え方がある」と受け止める姿勢が、
円滑な人間関係を築くために欠かせないポイントなのです。

このフレーズは、人と会話をする時にトラブルを避けるための教えとしてよく使われるんだ「宗教と政治と野球の話はするな」って

わかる気がする!
その人の価値観とか立場が強く出ちゃう話題だからだよね。
※POINT:正しい、正しくないではなく「どっちとも言えない(グレー)」な状態があることも理解する。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
その②:優れているか、優れていないかで論じない
前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』の中で、
Amazonをはじめとしたレビューサイトに見られる特徴的な傾向についても触れられています。
辛口な意見の多くは、冒頭にこんな自己紹介から始まることが少なくありません。
- 「私は海外の○○大学に留学していましたが…」
- 「私は上場企業の○○の管理者ですが…」
こうした書き出しには、
「私は著者より優れている」というアピールが込められているのです。
著者によれば、これらの発言の裏には
「優れた学歴や職歴を持つ自分の意見は、他の人よりも価値がある」
という思い込みがあるとのこと。
結果、自分の意見=正しい意見と信じ込み、
感情的かつ断定的な暴言がネット上で散見されるようになるのだと指摘されています。
つまり、背景にどれほど立派な経歴があったとしても、
相手を見下すような態度や断定的な言葉遣いは、
建設的な議論を妨げる要因になりかねません。

これはオンラインのレビューだけじゃなくて、
SNSとか普段のコミュニケーションにも当てはまる教訓だよね。

その③:会話の冒頭を「否定」から入ってはいけない
「会話の冒頭を「否定」から入ってはいけない」
を具体的に解説をするため、本著から引用したいと思います。
コロナ禍に在宅勤務制度を導入していた会社で社員の方達にアンケートを取ったところ、「在宅勤務下で不快だった出来事」の断トツの一位が、オンライン会議の冒頭で、上司から「ちゃんと仕事してる?」「さぼってたんじゃないの?」とからかわれたことでした。
引用:「メンターになる人、老害になる人」95ページより

上司の立場からするとさ、
親しみを込めた軽い冗談のつもりで
『君こそ、ちゃんと仕事してるの?』
って声かけることもあるんだよね。

多分ね、部下から『上司こそどうなんです?』って
軽くツッコんでもらうのを期待して言ってるんだと思うよ。
前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』でも指摘されているように、
今の若い世代からすると
「ちゃんと仕事してる?」「さぼってたんじゃないの?」
その一言はまったく違う意味に受け取られます。
彼らにとっては 「いきなり否定された」と感じる行為であり、
「なぜ初めから否定されなきゃいけないのか」「意味がわからない」
と不快に感じてしまうのです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
5|性格統計学で“伝わる伝え方”を理解する

人は誰もが違う価値観、違う考え方を持っています。
その違いを統計データに基づき整理したのが
**性格統計学(12万人のデータ)**です。
データの中から、性格別のタイプを大きく3つに分けられると言います。
- ビジョンタイプ(未来・イメージ)
- ピースタイプ(安心・共感)
- ロジカルタイプ(データ・理屈)
このタイプごとに、
響く言葉・刺さる言葉・NGワードが違うのです。

次に、タイプ別に「響く伝え方」や「ほめ方」「NGワード」
を解説していきます。
① ビジョンタイプ(未来志向|ワクワク・自由重視)
ビジョンタイプの方の特徴として、
未来志向でイメージや自由な雰囲気を好み、
新しいことや変化が好きなことが挙げられます。
主に、ワクワク感が原動力になるタイプです。
※響く話しかた(モチベーションUP)
- 「一緒に面白いことしよう」
- 「もっと良くなる案がある」
- 「自由にやってみて」
※褒めかた(承認が刺さる)
- 「発想がいいね」
- 「新しい視点だね」
※NGワード(やる気が急落)
- 「根拠は?」
- 「計画性がないよね」
② ピースタイプ(安心感重視|調和・優しさタイプ)
ピースタイプの特徴として、
「安心感や穏やかな関係性」を大事にすることが挙げられます。
「気持ちの変化に敏感」で「人の役に立つことで力が出る」
タイプとして挙げられます。
※響く話しかた(心が開く)
- 「大丈夫、あなたならできる」
- 「いつも助かってるよ」
- 「困ってることない?」
※褒めかた(努力が報われる)
- 「丁寧だね」
- 「気配りが素晴らしい」
※NGワード(深く傷つきやすい)
- 「そんなの気にするな」
- 「早くして」
③ ロジカルタイプ(合理性重視|分析・結論タイプ)
ロジカルタイプの特徴として、
データや根拠を重視し、感情より理論をベースにものごとを考える人
が特徴と言えます。
また、「効率」や「正確」を何より大事にするタイプが当てはまります。
※響く話し方(理解が早い)
- 「結論から言うと」
- 「理由は3つあります」
- 「データはこうです」
※褒め方(価値観にフィット)
- 「正確だね」
- 「分析が鋭いね」
※NGワード(信用が落ちる)
- 「とりあえずやって」
- 「感覚でいいよ」
まとめ図:タイプ別の“刺さる言葉”と“地雷ワード”
| タイプ | 刺さる伝え方 | 褒め方 | 地雷ワード |
|---|---|---|---|
| ビジョン | 面白い・未来・自由 | 発想・視点 | 根拠?計画性ない |
| ピース | 安心・共感・寄り添う | 丁寧・気配り | 気にするな・早く |
| ロジカル | 結論・理由・データ | 正確・分析力 | とりあえず・感覚 |
タイプ別のコミュニケーションを理解した上で、
「実践型のコミュニケーション」を学ぶための
『伝え方コミュニケーション検定』を解説していきます。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
6|伝え方コミュニケーション検定で学べること

「老害にならない」「相手に伝わる」「人間関係のストレスが減る」
これらすべての土台となるのが “相手理解 × 伝え方の技術” です。
伝え方コミュニケーション検定(中級)は、
その2つを体系的に学べる 実践型のコミュニケーション講座です。

「伝え方コミュニケーション検定」の特徴は
一般的な「話し方講座」とは違い、
性格統計学(12万人のデータ)をベースにしている点が大きな特徴なんだって。

ここでは、その「伝え方コミュニケーション検定」内容と
得られるメリットを、
実例を交えながら徹底的に掘り下げていきます。
① 自分の“本質タイプ”を知る ― まずは自分を整える
多くの人間関係のトラブルは、
実は 「自分を理解していない」ことが根本原因となっています。
たとえば——
- なぜ同じ指摘をされるのか
- なぜ誤解されやすいのか
- なぜ伝わらないのか
- なぜイライラしやすいのか
これらは「性格タイプの違い」が原因であることが多いと言われています。
※本質タイプがわかると何が変わる?
- 自分の強み・弱みが“言語化”される
- ストレスの元が理解できる
- コミュニケーションのクセがわかる
- 他人と比べなくなる

「自分らしく生きていいんだ」と感じられ、
自己肯定感が自然と上がるのも重要なポイントなんだ。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
② 3タイプ(ビジョン/ピース/ロジカル)の価値観を学ぶ
検定の中核となる学習が、
3タイプそれぞれの価値観を理解すること。
この理解があるだけで、
家族・同僚・部下・上司との行き違いが激減します。

さっき、「性格統計学で“伝わる伝え方”を理解する」で
学んだ、タイプ別の接し方がここで活きるんだね♬
人間関係のモヤモヤの多くは、
実は タイプの違いを知らないことが原因。
検定では、
「なぜ相手がその行動をするのか」が“見える化”するため、
イライラが驚くほど減ります。
③ 家庭(親子・夫婦)や職場でもすぐに使える実践スキル
伝え方コミュニケーション検定は
ビジネスだけでなく家庭での活用でも人気です。
※子育てでの効果
- 子どもが動かない原因が「やる気」ではなく「タイプ」だとわかる
- 兄弟・姉妹で「響く声がけ」が全然違うことに気づく
- 勉強が苦手な子のモチベの上げ方が変わる
※夫婦での効果
- 価値観の違いが「相性悪い」ではなく「タイプ違い」と理解できる
- ケンカの回数が激減
- 相手を尊重できるようになる
多くの受講者が
「家庭のイライラが明らかに減った」と実感しています。
上司・部下・同僚との関係でも効果は絶大。
「老害」という認識が産まれない組織作りに役立ちます。
※部下のタイプに合わせて指導できる
- 行動しない原因がタイプで理解できる
- 効果的なほめ方がわかる
- ダメ出しの仕方が変わる
→ 結果、離職率や不満が減る
※上司への報告もスムーズに
- ロジカル上司には結論→理由→具体例で報告
- ピース上司には配慮を添える
- ビジョン上司には未来の話から入る
→これだけで職場が円滑になること間違いなし。
④実績に裏付けられた“本物の資格”
資格認定団体である日本ライフコミュニケーション協会は、
文部科学省の調査研究事業を受託し、教育現場でも導入。
小学校教員の研修では、
**98%の先生が「関わり方を振り返るきっかけになった」**と回答。
つまり、
「人間関係の改善」に科学的根拠と実績がある手法なのです。

資格取得に向けてのステップも紹介しますね!
※内容
- 動画学習170分
- Web試験(15問・選択式)
- レポート提出
※時間
・最短3時間で取得可能。
※メリット
- 履歴書に書ける(ビジネスでアピール可能)
- 即日から実生活で使える
- 価格も比較的リーズナブル
- 「資格を取った後」が人生で長く役立つ
⑤老害にならないための“相手理解”が自然と身につく
この記事のテーマに戻ると、
伝え方コミュニケーション検定は
老害化を防ぐための技術と価値観を総合的に学べる講座です。
- 「正しさ」を押し付けない
- 「上下を作らない」
- 「相手のタイプに合わせて言葉を変える」
- 「否定で始めない」
- 「理解しようとする姿勢を持つ」
これらはすべて
老害と呼ばれないための必須スキルであり、
検定の学びと完全に一致しています。
すべての人間関係で、
あなたのコミュニケーションが劇的に変わります。

そして結果として、
老害ではなく“信頼されるメンター”になれるんだね~

これは40代からでも遅くありません。
むしろ“大人になった今だからこそ”学ぶ価値があるスキルです。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
まとめ|『メンターになる人、老害になる人』から学ぶこと

ここまで記事をお読みいただき、ありがとうございました。
今回は、前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』を取り上げながら、
「自分のちょっとした行動や言動が老害にならないように」
「良き上司・良き先輩を目指すために」
必要な教育論について解説してきました。
また、実践的コミュニケーションスキルの取得として
「伝え方コミュニケーション検定」についても紹介しました。

もしご興味を持たれた方は、
ぜひ、本書前田康二朗著『メンターになる人、老害になる人』
を書店やオンラインストアで手に取ってみてください。
きっと新しい気づきが得られることでしょう。

「伝え方コミュニケーション検定」も興味を覚えた方はチェックしてみてね♬
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
【関連記事:教養を得るには【まとめ記事】|現代人のための読書実践ガイド【2025年版】】
【関連記事:実体験からわかるパワハラ上司への対処法3つのポイント】