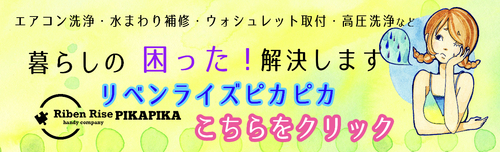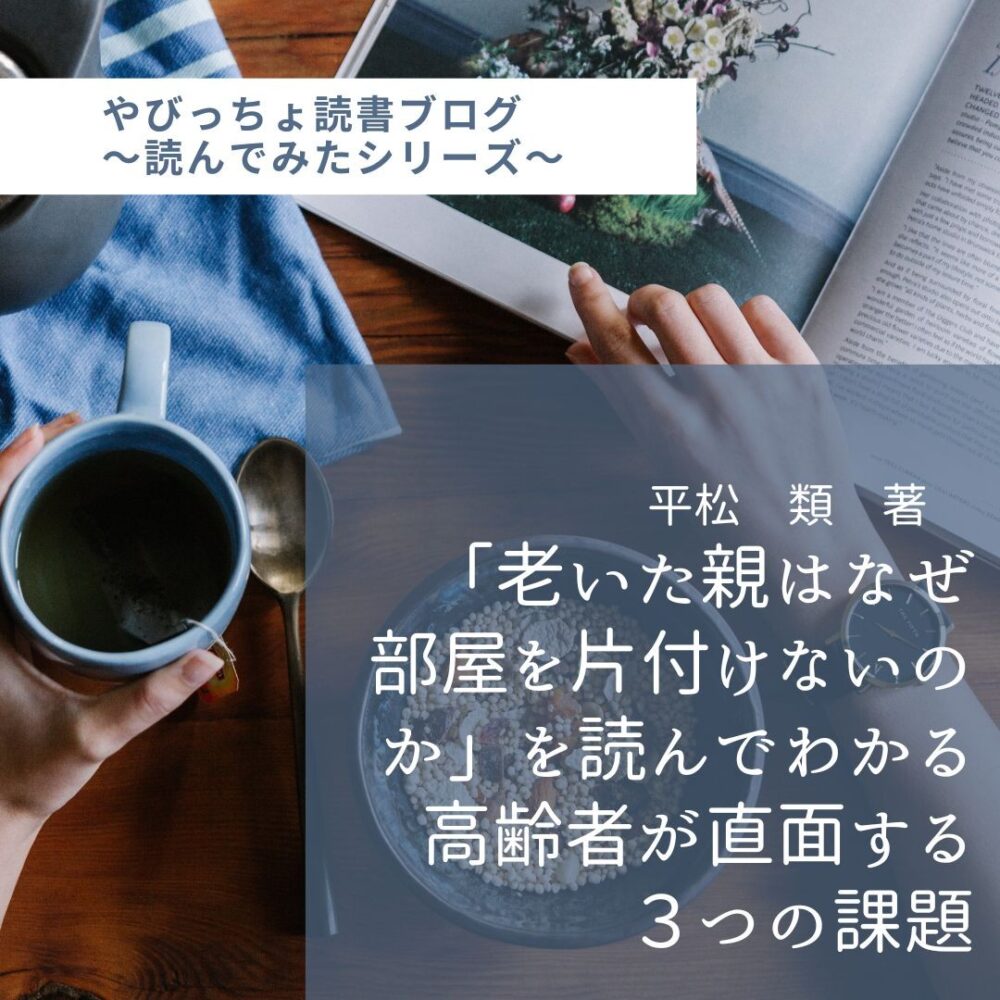今回は、読書感想ブログとして、延べ10万人以上の高齢者として接してきた医師が書かれた、「平松類著/老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」を紹介します。

実家に帰るたびに目にあまる物であふれた部屋。「どうしてこんなに物を溜め込むの?」「片付けてって言ってるのに全然聞いてくれない」──そんな思いを抱えたことはありませんか?
親との関係にひびが入るほど深刻な問題に発展することもある「高齢の親の片付け問題」。実はそこには、単なる“ずぼら”や“意地”では説明できない、高齢者特有の心理や身体的な課題が隠れているのです。
この本をずばり一言でいうと・・・
「年老いた親の理解できない行動には原因があった」という点について書かれた本だと言えます。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
この記事を読んでわかること

本記事では、本書、『老いた親はなぜ部屋を片付けないのか』をもとに、高齢者が部屋を片付けられない本当の理由を読み解き、彼らが直面する3つの課題とその背景を紹介します。
どうすれば感情的にならずに、親を傷つけずに、自宅の片付けをサポートできるのか──その具体的なヒントもお伝えします。

片付けをめぐる親子の衝突は、実は“老い”をどう受け止めるかという繊細な問題です。まずは、親の立場に立ってその気持ちを理解するところから、一緒に考えてみませんか?

最近、親が部屋を片付けることをおっくうに感じるのか?部屋がちらかってしかたありません。注意すると急に怒り出すし…、頑固になってきたようにも感じます。

一日、部屋に閉じこもってエアコンをつけないし、怪しい陰謀論を信じて話が通じなくて困っています。
親の行動に対して理解ができないことで、ご家族も「???」と心配になると思います。
本書、『老いた親はなぜ部屋を片付けないのか』を読むことで、年老いた親への行動を理解すると同時に、来るべき事態に備えるなど、そんな悩みへの対処法について、考えることができるかもしれません。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
※POINT:利用者の住まわれているご自宅を「ゴミ屋敷」と表現することに対して不快感を感じられるかたもいらっしゃると思いますが、この記事では便宜上「ゴミ屋敷」という表現を使用させて頂きます。ご了承ください。
こんな人にこそ読んでほしい
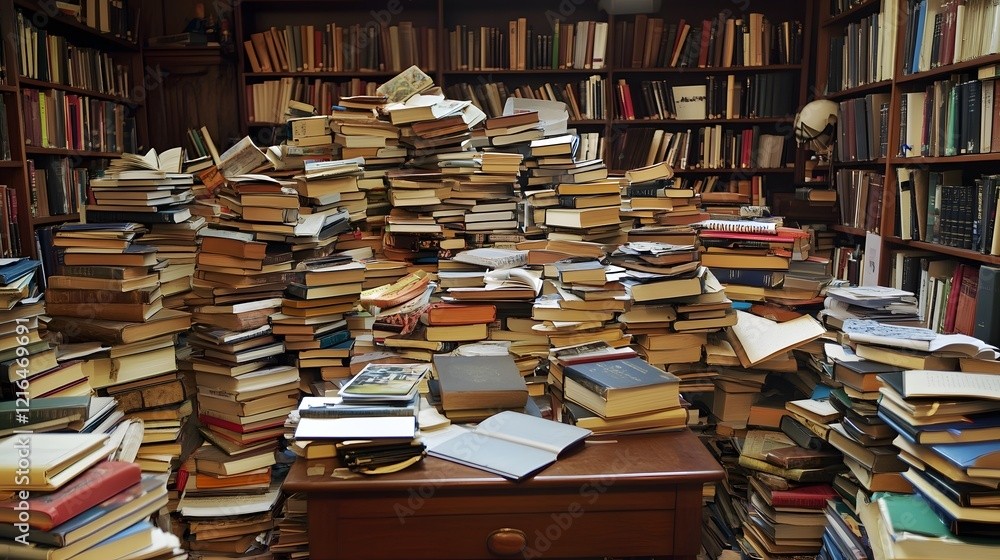
この記事は、「平松類著/老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」をテキストに親の介護について考える構成となっています。

自分の両親の行動が理解できない。昔はそんなことをする人ではなかったのに?などと、不可解な行動が続くと「自分の親の介護が始まるのでは?」と、不安になる気持ちもわかります。記事では、そうした不安や疑問を解説してく構成となっています。
- 自分の親は介護が必要になるのでは?と不安を感じているかた
- なぜ、歳を取ると部屋を片付けることが出来なくなるのか?と疑問に思うかた
- 実際のゴミ屋敷への事例について
近年、ゴミ屋敷という社会問題が認識されることで、自身の親の自宅を訪れた家族が「物が散らかっている」、「部屋が片付いていない」と、近い将来に介護が必要になるのでは?と心配されるかたも多くなっている印象がします。
本書では、歳を取ることによる心身の変化にも詳しくふれており勉強になる一冊です。機会があれば、「平松類著/老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」を書店などで直接、お手に取って読まれて下さい。
《PR:Amazonアフィリエイト広告を利用しています》
『老いた親はなぜ部屋を片付けないのか』を読んでわかること
働き盛りの現役世代が老いてきた親とどう向き合い、これから起きるであろうことに対してどう備えればいいのかを解説しています。
本記事で紹介する内容を読めば、親の老後生活に対して不安に思う方でも、老化が及ぼすであろう、心身への変化をとおして介護への理解が深まります。

ブログ管理人のやびっちょです。実際に私も両親の介護を経験しています。又、ケアマネージャーとしてゴミ屋敷となってしまった高齢者の支援を経験してきました。実体験の中で感じた課題や反省も含めてお伝えできると思います。
【関連記事:介護を成功させるための家族の役割3つのポイント】
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
著者の平松類先生ついて
平松類(ひらまつ・るい) 医師・医学博士、二本松眼科病院副院長。1978年生まれの愛知県田原市出身の眼科専門医・医学博士であり、現在は福島県の二本松眼科病院副院長を務めています。
筑波大学附属駒場高等学校を卒業後、昭和大学医学部および同大学院を修了し、医学博士号を取得しました。
これまでに昭和大学病院、今泉西病院、三友堂病院眼科科長、彩の国東大宮メディカルセンター眼科部長などを歴任し、全国から患者が訪れる眼科医として活躍しています 。
著書について
著書は累計100万部以上を売り上げており、代表作には『老人の取扱説明書』『1日3分見るだけでぐんぐん目がよくなる! ガボール・アイ』『老化って言うな!』今回、取り上げる『老いた親はなぜ部屋を片付けないのか』などがあります。
これらの書籍では、図解などを通して高齢者の体調や目のケアなど、専門の知識がなくても理解できるように解説しています 。
著書を通して、高齢者の心身の問題に関心のある方にとって非常に役立つ内容となっています。他にも、家庭や介護に関するテーマでいくつかの本を出版しており、読者の共感と反響を呼んでいます。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
YouTubeチャンネル「眼科医平松類チャンネル」を運営
YouTube「眼科医平松類チャンネル」で情報発信を行っています。登録者数は25万人を超えています。また、Yahoo!ニュースの公式コメンテーターや日経Goodayの連載執筆者としても活動し、一般の人々にもわかりやすい医療情報の提供に努めています 。
平松先生のYouTubeチャンネルを観ると、患者さんの生活の質(QOL)を真剣に考えていることが伝わってきます。
【平松 類先生のYouTubeを観るなら:目の病気があるからこそもっと自分を大切に!】
講演活動やメディアにも多数出演
平松先生は、医療現場での豊富な経験を活かし、講演活動も積極的に行っています。講演では、目の健康法や高齢者との接し方など、幅広いテーマで聴衆に合わせた内容を提供しています 。
メディア出演も多数あり、NHK「あさイチ」、TBS「ジョブチューン」、フジテレビ「バイキング」、テレビ朝日「林修の今でしょ! 講座」などに出演し、目の健康や高齢者の体調についての情報を発信しています 。
《PR:Amazonアフィリエイト広告を利用しています》
親の態度の変化に対してどこまで心配するべき?

著書の平松先生は、今現在も高齢者も含めて、コミュニケーションについて研究しているそうです。

相談の中で、現役世代(お子さん)の方から「自分の親の様子」について相談を受けることが多いそうです。

一番の心配は「自分の親の介護が始めるのでは?」という問題にあると思います。実際に介護が始まると、仕事だけでなはく家族にまで影響を及ぼします。
具体的に言うと「介護をするために仕事を休まなくてはいけない」、「家のことや子育てに手が届きにくくなる」または、「家族と離れて親と同居する」など一人では解決できない問題が山積します。
平松先生は、不安でいっぱいな思いのご家族にどのようなアドバイスをされるのか?確認してきましょう。
「介護」につながるかどうかで判断する
ご家族(主にお子さん)たちは、普段の親の行動が以前(若い頃)とは違うのでは?と、感じることで「親の様子がいつもと違う、なにかおかしい」と、不安を感じ病院に来られるそうです。平松先生は「歳をとったことによる体の変化」が原因とされるそうです。

親の自宅に行ったら、ゴミが散乱していて心配になりました。モノを片付けたら?と言っても聞いてくれません。
「歳をとったことによる体の変化」については、生活に支障をきたすような、急激な変化はないと解説されています。結論として、それほど慌てなくても大丈夫だと、著者の平松先生は言います。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
部屋が散らかっているのは目が悪くなったせい?
一方で、「歳をとったことによる体の変化」の中で、親の問題行動が出現することもあると解説されています。加齢による体の変化によって、問題行動がでる特徴の一つとして「見えかた」を挙げています。
例えば、「部屋を片付けなくなった」親は、単に視力が衰えたり視界が狭くなったりして、汚れやホコリに気づかなくなっている可能性もあります。子どもからすると「こんなに散らかして、物を捨てたり片付ければいいのに」と思っても、当の本人はそれらが目に入らないため気になっていないのかもしれません。
「平松類著/老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」28ページより引用

家族(子ども)たちからすると「なぜ、片づけないのだろうか?」と思いますが、本人からすれば、散らかっていることが「見えない(もしくは見えづらい)ために気にならない」という、親御さんと家族(お子さん)の認識の差が生まれる訳です。
早めに介護認定を受ける
自分の親が、まだ、自分で生活が出来ているので大丈夫だと思い、「介護認定」を受けることに対して二の足を踏むかたも多いと平松先生は説明します。
介護認定を勧めると、中には「介護なんてまだまだ先だ」と本人やご家族も、そう思うかたもいるかもしれませんが、自宅生活に対して不安を感じるなら早めの申請を勧めています。
部屋の掃除やゴミ出しの支援、衰弱(フレイル)を予防するためのリハビリテーション。福祉用具などもレンタルすることができます。
また、介護認定を受けたら「必ず介護保険サービスを使わなくていけない」という訳ではありませんので、ぜひ一度、お住いの地域包括支援センターや市役所などで相談してみることをお勧めします。

この本を読むことで、年老いた親への行動を理解すると同時に、来るべき介護に備えるなど、そんな悩みへの対処法についてなど学びが多い一冊です。詳しくは著書にふれてみて下さい。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
さいごに

最後までお読みいただきありがとうございました。戦後日本社会は「年老いた親」と「働き世代の夫婦」に「子どもたち」という家族モデル(サザエさん一家が例に挙げられます)を中心に社会制度を設計してきたと言われています。

ニュースで取り上げられる社会保障問題の「年金制度」や「医療・介護」も「家族がいるという前提」で制度設計されています。
今、少子高齢化社会の中で多様化を求める老後のライフスタイルとして「お一人様」が話題です。「老後も誰にも迷惑をかけずに一人で気楽に生活を送りたい」というライフモデルですが、私たちの暮らす社会システムは、「人生設計の多様化」には追い付いていません。
実際には、入院などで「ライフスタイルが変化」することにより、1人暮らしが困難になるケースも数多く存在しています。
誰もが、「老後も誰にも迷惑をかけずに一人で気楽に生活を送りたい」と思います。ですが、現実を正しく認識することも大事な作業だと言えます。
「終活」という言葉が流行しましたが、自身のライフエンディングをイメージすることも大切なことだと思います。
今回、「老いた親はなぜ部屋を片付けないのか」をテキストとして、さまざまな加齢(歳をとること)に伴う問題にふれてきました。又、別の形でこの問題にふれられればと思います。またの機会にお願いします。
《PR:アフィリエイト広告を利用しています》
【関連記事:理想のケアマネージャーを選ぶ3つのポイント】
【関連記事:介護を成功させるための家族の役割3つのポイント】
【関連記事:「老後ひとり難民」を読んでわかる独居高齢者が直面する3つの課題】